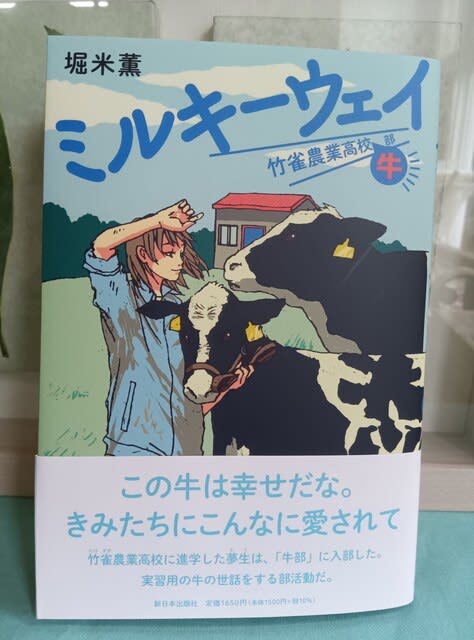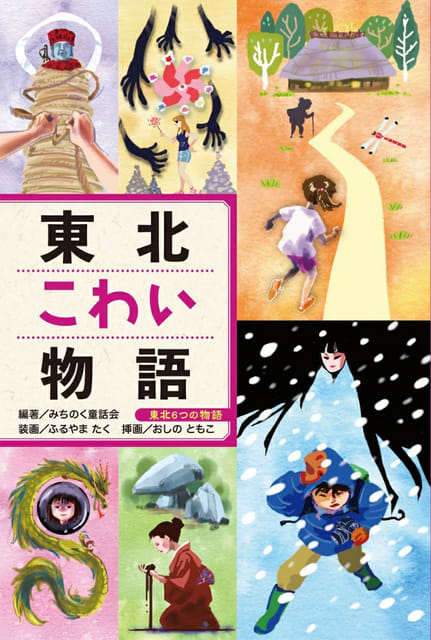佐々木ひとみさんが、絵本を出版されました!

大きな表紙には菜の花がいっぱい! 女の子が笑顔で両手を広げています。
この表紙がもう、「いいぞいいぞ」と誘ってくれているようです。
くるみは、参観日に「いちばんすきなものをかきましょう」と言われ、おかあさんと見た菜の花畑を描きました。そこだけお日様があたっているようなあざやかな黄色。
でも、男の子に「なんじゃそりゃ!」「まっきっきだあ」と騒がれ、笑われてしまいます。先生はは、「これはまだ途中だよね。気にしないで続きを描こうね」となぐさめてくれましたが、絵はもうとっくにできあがっているのです。このひと言、傷つくなあ。
でも帰り道、くるみはその菜の花畑へ行き、蜂飼いのおじいさんと出会います。
おじいさんが、くるみの絵を見て、なんと言ったのか、ぜひ読んでください。
上手じゃなくても、ほめてもらえなくても、描きたくて描いた絵なのです。くるみにとって、大事な絵なのです。そういうもの、誰にでもありますよね。人の批評に左右されず、自分の大切なものを守りたい。この絵本を読んで、そう思うことができました。
小学校低学年対象でしょうが、高学年~大人にも響くと思います。
絵本の力を感じました。