
オイノとは、オオカミのこと。東北地方で、呼ばれる名称です。
うんとむかしの きたの むら。 つまり昔の東北の話です。
いちろうの家は農家なので、畑を荒らすイノシシを落とす、ししあな(猪穴)をしかけています。
ある日、そこに一匹のオイノと二匹の子どものオイノが落ちていました。
いちろうはじいちゃんを呼びにいきます。
オイノは恐ろしい動物。でも畑を荒らす他の動物を駆逐するものとして、広く信仰を集めています。
最も有名なのが三峯神社。ここは東北のオオカミ信仰の元でもあるようです。それから、私が何度も訪れて作品にした青梅の御嶽神社。こちらは多摩川沿いにその信仰が広まっています。
そのオオカミへの畏怖からこの物語は生まれています。
いちろうとじいちゃんは、オイノの親子を助けます。ところが、その後、村にやめえいぬ、つまり狂犬病のようになったオオカミが現れ、いちろうとじいちゃんは襲われそうになります。そのとき……。
森元さんは、「季節風」会員。この作品は、「季節風」の大会に出して、推薦作になったものです。そのときは、このような絵本の形ではなく、長編だったものを、言葉を削って削って、見事な絵本に仕上げました。
小さい子どもも読んでもらって、オイノ親子といちろう、そしてじいちゃんとの結びつきをしっかり感じることができると思います。
そして、大人の人にも、ぜひ手にとっていただきたい。
オオカミ信仰は、なぜ、こんなに心ひかれるのでしょうか。『オオカミのお札』を書くために読んだ本のなかには、やはり東北のオイノのことを書いたものがありました。そこには、オイノの餌食になった人間のむごい事実もたくさん書かれていました。オイノボイ(オイノと追いはらうという意味)という言葉もありました。しかし、日本オオカミは絶滅したということもあるでしょう。かつて、オオカミを祀り、信仰した手を合わせたという事実に、私はひきつけられます。
伊藤さんの絵は、オイノをどこか優しく描き、ここという場面ではその険しさ、厳しさを出しています。
うちの4才のちびっこに読んでやったら、最初は気乗りしない様子もあったのですが、オイノの子どもが出てきたあたりから、身を乗り出して聞いていました。パウパトロールやすみっこぐらし、ポケモン好きな子ども達からしたら、別の次元の話ですからね。でもだからこそ、こういう物語にも触れてもらいたい。私、小学生のころは椋鳩十や「オオカミ王ロボ」に感動した記憶が、心の隅に残ってますもの。
「とうげのオイノ」は、年長向けのこどものともです。ちびっこには、2年早かったけど、よかった。次回は危険生物好きの小学生のお兄ちゃんのため、持っていきます(今回は持ち帰ったので)。
雑誌なので、書店にあるのは1ヶ月間。あとはバックナンバーでお求めになれます。

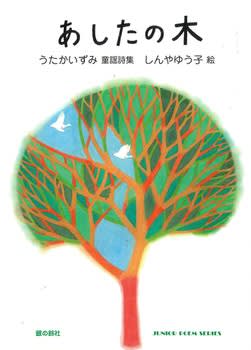

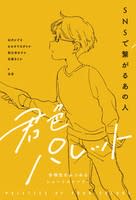












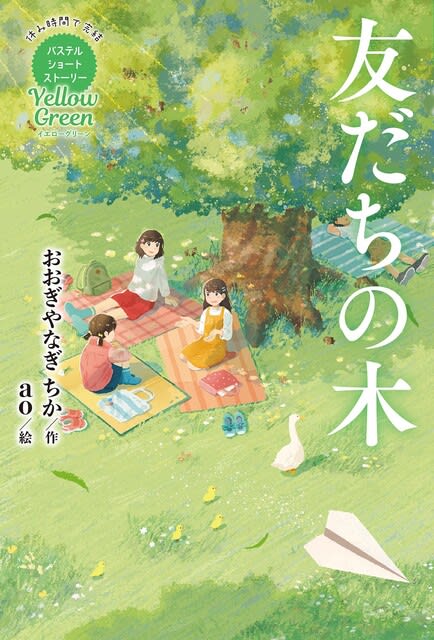 『友だちの木』
『友だちの木』