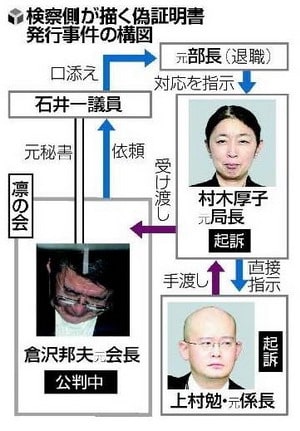一弦琴「漁火」は私の好きな曲の一つで、最近ではこの曲を奏でて一弦琴の稽古を始めることにしている。
「漁火」
詞 不詳 曲 松島有伯
もののふの 八十氏川の
網代木に いざよふ波の
音澄みて 影もかすかに
漁火の あかつきかけて
汀なる 平等院の 後夜の鐘に
無明の夢や さめぬらむ
演奏時間が5分少々の曲なので腕ならし声ならしにちょうどよい。その上、演奏で心がけたいポイントがたくさんあるので、そのたびに工夫をしてみる。なかなか満足できるレベルには至らないので、おそらく永遠に試みが続くことになるだろう。その意味でも稽古始めにもってこいの曲で、だからますます愛着が湧いてくる。
「漁火」で詠われる平等院を訪れたのは、私の記憶にある限りかれこれ半世紀も前のことである。この曲を知ってからあらためて訪れたいと思いながらも、これまで機会を逸していたが、ついに一昨日、訪れることが出来た。
東面する鳳凰堂を阿字池を挟んで眺めると、その左側のやや小高いところに鐘楼が建っていた。この梵鐘の音が歌に詠まれたのであろう。しかし現在つり下げられている鐘はレプリカなので、撞いて音を聞くわけにはいかない。国宝になっている実物は鳳翔館(平等院ミュージアム)に展示されていたので、つぶさに見ることが出来た。

この鳳翔館の展示物で私の目を引いたのが雲中供養菩薩像である。雲中供養菩薩像は52体が現存しているが、元来は鳳凰堂中堂の長押上の壁を飾る浮き彫りの菩薩像なのである。飛雲に乗り空中を飛び交っている菩薩様なのである。仏師定朝とその一門の工房で製作されたもので、この菩薩像すべてが国宝だというのが凄い。鳳翔館にはその半分の26体が展示されているが、そのなかに一弦琴を弾いているような像があったのにドキッとした。北20号像なのである。

館内に備え付けられた解説用パソコンで調べてみると、この像は総高が77.3cm、木造彩色で平安時代天喜元年(1053)の製作となっている。左右になびく雲の上に置かれた蓮華座に坐り、琴を弾く姿の像です、とのことである。しかし琴の種類の説明はない。私が一弦琴かと思ったのは、まずその長さである。身体の大きさから考えると、源氏物語絵巻若菜下などに描かれている宮廷での音楽練習場面に出てくる和琴、琴、箏などにくらべるて圧倒的に短いので、このような琴と異なることは明らかである。現在私の使っている一弦琴は110cmもあるのでそれよりも短いことになるが、サイズで言うと一弦琴であってもおかしくない。しかも左手を見ると、人差し指一本で弦を押さえているようである。しかし本当に一弦琴なのだろうか。
琴を弾いている菩薩像はほかにも2体ある。北1号像と南16号像で、琴の形は両者ともよく似ているので北1号像をつぎに示す。

琴の長さは北20号像のと変わらないが、左手の指の形が違っていて、どうも複数の弦を押さえているような感じである。さらに琴の右端には5ヶないしは6ヶの穴があり、これは弦を通すためのように見える。南16号像のも同じようなので、琴の大きさは一弦琴向きであるとしても、はたしてそうなのか断言出来ない。

この雲中供養菩薩の図説から菩薩像の過半数が琴以外にも笙、拍板、琵琶、縦笛、横笛、太鼓、鼓、鉦鼓などの楽器を奏でていることが分かる。ところが北25号像の持つ蓮華を除く各像のすべての持ち物は後補であるという。何時の時代での後補であるのか分からないが、いずれにせよ元来は楽器のモデルがあったはずで、おそらくは雅楽器がそれであろうと考えられる。しかし正倉院に残されている18種類58個の楽器に一弦琴は含まれていない。さらに群馬県で出土した埴輪の弾琴男子像は菩薩像と同じく琴を膝の上に抱えており、琴のサイズも菩薩像のとよく似ている。そして琴の弦数は埴輪につけられた線条から明らかに五本で、専門家はこれを和琴と断定している(埴輪弾琴男子像及び琴に関する部分は吉川英史著「日本音楽の歴史」にもとづく。下図の写真も同じ)。


ネットに増田修氏による論考「古代の琴(こと) 正倉院の和琴(わごん)への飛躍」が公開されており、木製の琴や埴輪の琴の52件の遺跡からの出土例が紹介されている。線条などから分かるものでは四弦、五弦のものがほとんどで、少数であるが二弦もある。そして
と一絃琴が紹介されているが、弓琴と記されているので明らかに板琴である一弦琴とは異なる。
しかし一方、日本後記に一弦琴の伝来が次のように記されており、その当時、弓琴か板琴かは定かではないが、一弦琴が入ってきていたことは確かであろう。
あとは想像である。小舟で參河國に漂着した印度人が板の一弦琴を携えていたことが、承和七(八四0)年に完成していた日本後記により上流階級には知られていたとすると、それに定朝とその一門仏師の想像力が刺戟され、印度渡来の菩薩様に和琴に加えて一弦琴を持たせてやろうということになった可能性はありうる。それが北20号像に結実したのではなかろうか。
そうだとしたら面白いなと思いながら「漁火」を奏でてみた。
「漁火」
詞 不詳 曲 松島有伯
もののふの 八十氏川の
網代木に いざよふ波の
音澄みて 影もかすかに
漁火の あかつきかけて
汀なる 平等院の 後夜の鐘に
無明の夢や さめぬらむ
演奏時間が5分少々の曲なので腕ならし声ならしにちょうどよい。その上、演奏で心がけたいポイントがたくさんあるので、そのたびに工夫をしてみる。なかなか満足できるレベルには至らないので、おそらく永遠に試みが続くことになるだろう。その意味でも稽古始めにもってこいの曲で、だからますます愛着が湧いてくる。
「漁火」で詠われる平等院を訪れたのは、私の記憶にある限りかれこれ半世紀も前のことである。この曲を知ってからあらためて訪れたいと思いながらも、これまで機会を逸していたが、ついに一昨日、訪れることが出来た。
東面する鳳凰堂を阿字池を挟んで眺めると、その左側のやや小高いところに鐘楼が建っていた。この梵鐘の音が歌に詠まれたのであろう。しかし現在つり下げられている鐘はレプリカなので、撞いて音を聞くわけにはいかない。国宝になっている実物は鳳翔館(平等院ミュージアム)に展示されていたので、つぶさに見ることが出来た。

この鳳翔館の展示物で私の目を引いたのが雲中供養菩薩像である。雲中供養菩薩像は52体が現存しているが、元来は鳳凰堂中堂の長押上の壁を飾る浮き彫りの菩薩像なのである。飛雲に乗り空中を飛び交っている菩薩様なのである。仏師定朝とその一門の工房で製作されたもので、この菩薩像すべてが国宝だというのが凄い。鳳翔館にはその半分の26体が展示されているが、そのなかに一弦琴を弾いているような像があったのにドキッとした。北20号像なのである。

館内に備え付けられた解説用パソコンで調べてみると、この像は総高が77.3cm、木造彩色で平安時代天喜元年(1053)の製作となっている。左右になびく雲の上に置かれた蓮華座に坐り、琴を弾く姿の像です、とのことである。しかし琴の種類の説明はない。私が一弦琴かと思ったのは、まずその長さである。身体の大きさから考えると、源氏物語絵巻若菜下などに描かれている宮廷での音楽練習場面に出てくる和琴、琴、箏などにくらべるて圧倒的に短いので、このような琴と異なることは明らかである。現在私の使っている一弦琴は110cmもあるのでそれよりも短いことになるが、サイズで言うと一弦琴であってもおかしくない。しかも左手を見ると、人差し指一本で弦を押さえているようである。しかし本当に一弦琴なのだろうか。
琴を弾いている菩薩像はほかにも2体ある。北1号像と南16号像で、琴の形は両者ともよく似ているので北1号像をつぎに示す。

琴の長さは北20号像のと変わらないが、左手の指の形が違っていて、どうも複数の弦を押さえているような感じである。さらに琴の右端には5ヶないしは6ヶの穴があり、これは弦を通すためのように見える。南16号像のも同じようなので、琴の大きさは一弦琴向きであるとしても、はたしてそうなのか断言出来ない。

この雲中供養菩薩の図説から菩薩像の過半数が琴以外にも笙、拍板、琵琶、縦笛、横笛、太鼓、鼓、鉦鼓などの楽器を奏でていることが分かる。ところが北25号像の持つ蓮華を除く各像のすべての持ち物は後補であるという。何時の時代での後補であるのか分からないが、いずれにせよ元来は楽器のモデルがあったはずで、おそらくは雅楽器がそれであろうと考えられる。しかし正倉院に残されている18種類58個の楽器に一弦琴は含まれていない。さらに群馬県で出土した埴輪の弾琴男子像は菩薩像と同じく琴を膝の上に抱えており、琴のサイズも菩薩像のとよく似ている。そして琴の弦数は埴輪につけられた線条から明らかに五本で、専門家はこれを和琴と断定している(埴輪弾琴男子像及び琴に関する部分は吉川英史著「日本音楽の歴史」にもとづく。下図の写真も同じ)。


ネットに増田修氏による論考「古代の琴(こと) 正倉院の和琴(わごん)への飛躍」が公開されており、木製の琴や埴輪の琴の52件の遺跡からの出土例が紹介されている。線条などから分かるものでは四弦、五弦のものがほとんどで、少数であるが二弦もある。そして
13 天理市荒蒔古墳 埴輪 (一絃) 粘土紐 六世紀前半 天理市教委 弓琴であろう
と一絃琴が紹介されているが、弓琴と記されているので明らかに板琴である一弦琴とは異なる。
しかし一方、日本後記に一弦琴の伝来が次のように記されており、その当時、弓琴か板琴かは定かではないが、一弦琴が入ってきていたことは確かであろう。
《卷八延暦十八年(七九九)七月是月》○是月。有一人乘小船。漂着參河國。以布覆背。有犢鼻。不着袴。左肩著紺布。形似袈裟。年可廿。身長五尺五分。耳長三寸餘。言語不通。不知何國人。大唐人等見之。僉曰。崑崙人。後頗習中國語。自謂天竺人。常彈一弦琴。歌聲哀楚。閲其資物。有如草實者。謂之綿種。依其願令住川原寺。即賣隨身物。立屋西郭外路邊。令窮人休息焉。後遷住近江國國分寺。(強調は私)
あとは想像である。小舟で參河國に漂着した印度人が板の一弦琴を携えていたことが、承和七(八四0)年に完成していた日本後記により上流階級には知られていたとすると、それに定朝とその一門仏師の想像力が刺戟され、印度渡来の菩薩様に和琴に加えて一弦琴を持たせてやろうということになった可能性はありうる。それが北20号像に結実したのではなかろうか。
そうだとしたら面白いなと思いながら「漁火」を奏でてみた。