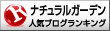古筆切(こひつぎれ)~わかちあう名筆の美~
2025/1/28 根津美術館
妹は、アラ還だけど大学生。
通信制の大学で書画を学んでいるので、
ときどきこういう展示会に誘われる。
今回は根津美術館で開催されている
「古筆切(こひつぎれ)」へ

古筆というのは
平安から鎌倉時代に染筆された、加州などの和洋の書のこと。
平安時代に「古今和歌集」などの和歌集や私家集などが
一流の能書家によって写された歌書をなどを室町時代以降、
鑑賞のために分割して掛け軸などにしたものを「古筆切」と言うらしい。
古筆を切っちゃったからよね。
今回の展示の古筆切については美術手帳の記事がわかりやすそう。
「古筆切 ―わかちあう名筆の美」(根津美術館)開幕レポート。様々なアプローチから知る名筆の楽しみ|美術手帖
根津美術館は都会のど真ん中にあるけれど、
長い長い竹のフェンスと竹の植栽の間を通って入り口に着くと、
ちょっと別世界に着いたようだ。

敷地内の庭園はとても広くて、迷ってしまいそうなくらい。
今回は寒いし時間もないし、花も咲いてないので、
庭園散策は割愛した。
それにしても、古の人たちってなんて字がお上手なんだろう。
大河ドラマの紫式部も
さらさらっと小筆を走らせていたっけ。
仮名文字を読むのは難しけれど
絵画とは違った美しさと奥深さに引き込まれる。
美しい柄の紙に書かれていたりすると
一層芸術的。
写真撮影は禁止だったので、ご紹介はできないけど、
前出の美術手帳の記事の中に
たくさん写真が載ってるので、ご覧ください。
実は私も書道を習っている。
習い始めたのは小学校1年生の時。
北海道の小さな町のお習字教室だ。
それほど熱心な生徒でもなかったが
なんとなく高校まで続けていて、
大学で地元を離れたときにやめてしまった。
その後結婚してなんとなく生活落ち着いたころ、
もう一度やりたくなった。
同じ団体の先生が違にいらっしゃったらご紹介いただこうと、
かつての先生に連絡してみたところ、通信で教えてくださる、
ってことになり、今日にいたる。
仕事や子育てで作品を送ったり送らなかったり・・・
昇段試験は途中であきらめたが、
楽しんで続けてくれればいい、とおっしゃる寛大な先生のお言葉に甘え、
だらだらと続けている。
先生もおそらく80代半ば。
先生がもうやめます、とおっしゃるまでは楽しませていただこうと思っている。
最近、先生の添削が少し甘くなってこともあってか、
以前より楽しくなってきた。
特に仮名


お手本を見ながらじゃないとなんて書いてあるかわからないし、
必死で書いていて
あれ、今、どこ書いてる?
ってなったりする。
最後のほうで失敗した時のがっかり感ったら!
でも何とか形になった時の達成感が最近たまらない。
いつか、解説なしで解読できたらいいな、
と密かに思っている。
美しい古筆に触れて、とても豊かな気持ちになった冬の午後でした。