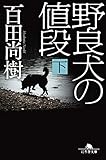小牧長久手の戦いにハマっている。今度は、角度を超えて、中間管理職から見た、小牧長久手の戦いである。主人公は、鉄砲大将、部下を数十人ほど持つ、企業で言えば、家康軍の中間管理職、部課長クラスかな。
主人公に、頼りない部下がいる。上司から預かるようにと、押し付けられたようだ。主人公は取り扱いに困っている。これも私、企業で経験済みだ。主人公は、片腕と言っていい、部下に頼み、OJTで戦い方を教えている。そして時々、チェックもしている。
真田昌幸も登場する、くせ者としてだ。相手は中堅企業だが、企業のトップ、こちから中間管理職、話のやり取りも当然、緊張する。
最後は、小牧長久手の戦いで、鬼武蔵と言われた、森長可が戦死する、その戦いの現場のことが詳細に書かれている。もちろん小説だから、どこまで正確に描写しているかわからないが。鉄砲隊の見せ所だった。
最後のシーンは、主人公が家康に意見を聞かれるところで終わる、小牧長久手の戦いでは織田信雄が、独断で秀吉と和議を結び、家康の立場は、微妙。戦いは、家康が有利に進んだ、それでも秀吉に臣下の礼を取るのか、と聞かれた時だ。中間管理職が社長から直接、意見を聞かれたときは緊張する。それがラストシーンだ。
視点を変えて、戦国時代を読むのもいいですね。