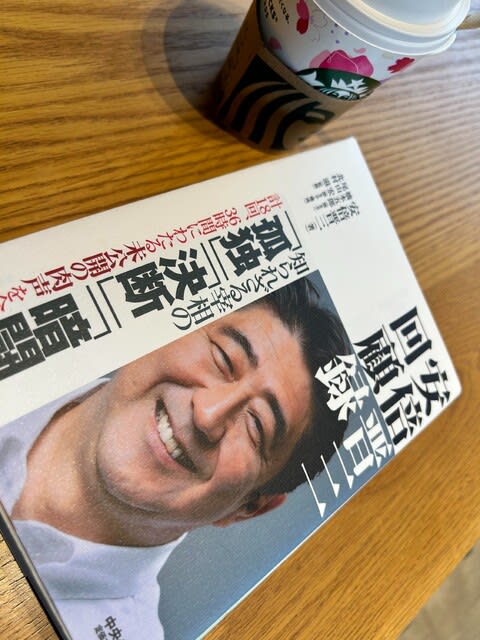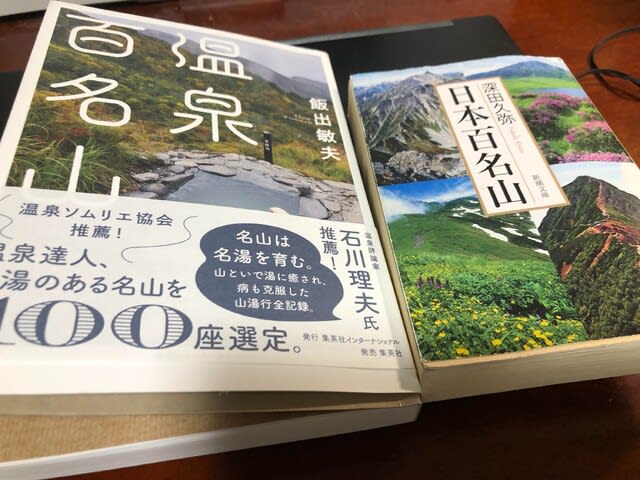しばらくぶりにお城の話。芥川賞の小説「塞翁の盾」に続いて、「蛍の城」を読む。どちらも戦国末期、関ヶ原の戦い直前の大津城の籠城戦を描いたものだ。違いは、主人公の穴太衆の動きが塞翁の盾だ。京極高次のリーダーシップを描いたのが蛍の城。ストーリーと登場人物の感想は、おそらくWebに沢山書かれているだろうから、私は違った角度から。
主人公の京極高次は、女系の家柄の良さから、尻が明るい「蛍大名」のニックネームがついている。そして部下に優しく、思いやりがある。ただ、戦は下手だった。もう一方、大津城を攻めてくる敵をバッタバッタと倒す、高次の部下の「豪傑」が何人も登場する。カラダがデカく、槍も強い、剛力だ。
世の中にはリーダーシップ論というのがある。中小企業診断士で、「企業研修」のプロになるための学校で、リーダーシップ論の変遷を学んだ。それによると、最初は、①資質特性論、リーダーシップは、個人の人相、骨格、性格など身体的、心理的な資質で決まるという研究。腕力の強い者がリーダー、大昔は単純にこれだったんだろうね。
次は、②リーダーシップのタイプ論。リーダーシップを仕事中心的機能と人間中心的機能に分け、どちらの要素が強いのか、4つのマトリクスで、タイプごとに決めていく研究。昔は仕事と人間両方に関心を持つのが一番いいとされた。私も管理職になりたての若い頃に、こういう風に教わった。
そして、③状況論、リーダーシップは、リーダーとメンバーの関係、状況の変化によって変わるとする研究。リダーシップの発揮はいつも同じじゃない。最近の研究は、これより、もう一段も二段も先を行ってる。
さて、京極高次は、②リーダーシップのタイプ論で、人間中心的機能の存在だ。結構今でもこれは人気がある。そして、豪傑は、①資質特性論の個人の骨格など身体的な特徴に優れた存在。相手より強いのは、それなりに人気はあるだろう。しかし、ただそれだけじゃ、という感じ。
最後は、この籠城戦のため、4万の西軍立花宗茂などが関ヶが原に間に合わず、東軍の家康が勝った。一旦高野山に入った高次だが、その後、家康が功多しと評価し、幸運にも、若狭の大大名にまでなってしまう。
この例では、リーダーシップタイプの影響もあっただろうが、籠城戦の降伏が、関ヶ原の前日か当日か、運不運で、高次の運命が決まってしまった。リーダーシップなんて、結局、何がいいか、わからないね。