司馬遼太郎の「花神」3巻を読む。文庫本の最後の解説に、対をなす小説に「世に棲む日日」があると書かれている。この「世に棲む日日」、吉田松陰と高杉晋作の物語、こちらは、かなり昔に読んでいた。従って小説の時代背景はすっと入って来る。
もう一つ、「花神」とは中国では「花咲かじいさん」のことだそうだ。つまり主人公は、革命家が倒れ、その後に革命の花を咲かせる役だというのである。大村益次郎。靖国神社に大きな像がある人だ。
というより、私は先日訪問した島根県は浜田城を、第二次長州征伐の時に、長州藩から打って出てきた部隊の隊長で覚えている。このときは、長州勢の勢いで、浜田藩は、城主が船で逃げ、藩兵は、浜田城に自ら火をかけた。侍である浜田藩兵は、農民の兵である長州勢に負けなかった、という証拠としたようだ。なんか情けないな。

そして明治の幕開けに、上野の彰義隊との対決のあと、いずれ薩摩藩が暴発するであろうことを見越して(西南の役はその10年近く先だ、この先見性ってすごい)、大阪に政府軍の施設を作り、瀬戸内海から航路で武器などをすぐ運べるようにした。そして、暴漢に襲われ、一時は助かったがその後、死亡した。
維新のいわゆる技術者だ。冷静に計算して、軍の配置を決める、ち密な計算からなるから、決して負けない。すごい人物だ。もし生まれ変わったら、このように生きてみたいと思う。
ここまで書いて気がついた。生まれ変わったら・・と書くのは初めてのような気がする。今までは、これを取得したら、これをやろうなど、現世でのことしか思い浮かばなかった。
だいぶ、トシ取ったかなあ。資格とっても使い道が少なくなり、現役からだんだん遠くなってきたように感じるが、まだ、受験指導も、登山も、お城も、温泉も、現役ですぞ。











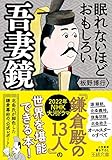

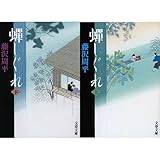








![[新版]日本国紀〈上〉 (幻冬舎文庫)](https://m.media-amazon.com/images/I/316HiG4jdQL._SL160_.jpg)
![[新版]日本国紀〈下〉 (幻冬舎文庫)](https://m.media-amazon.com/images/I/31STmq3aenL._SL160_.jpg)









