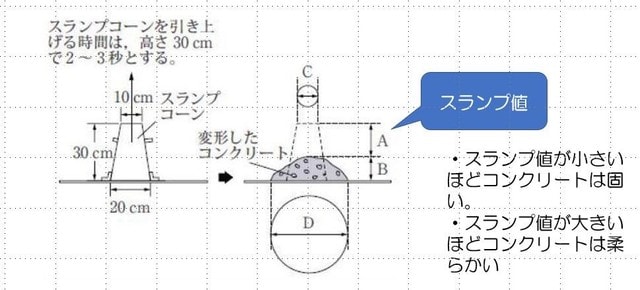1級土木動画講座の開発その8は、専門土木の「海岸・港湾」だ。この分野は、まず、堤防と護岸の建設。堤防とは、原地盤を嵩上げし築造するもので、護岸は、原地盤を嵩上げしないか、背後を堤体天端まで埋めた海岸堤防施設だ。ちょっと違う。
次に離岸堤とリーフ。あんまり聞いたことのない構造物だが、離岸堤は海の中の堤防、リーフは水中に沈んだ構造物だ。リーフはもともとはサンゴ礁のことだ。従って構造物のリーフは、人工リーフとなる。
さらに港などの浚渫、港の底を深くするなどの工事だ。あとは浜を作る養浜、さらに大型で海に沈める大箱ケーソン。このくらいかな。ここでは養浜について書く。養浜、ヨウヒンと読む。海岸の浜を作る作業だ。大量の砂などが必要だ。
これ、やっている場所がある。私の実家のある、石川県羽咋市千里浜(ハクイシチリハマ)だ。ここは砂浜を車が走ることのできる日本で唯一の(たぶん)浜だ。渚ドライブウエーともいう。延長は8kmもある。この浜、侵食を受けて年々その幅が狭くなっている。
原因は砂防ダムの建設で、砂が海岸まで行かなくなってしまったことだそうだ。海の流れや波があっても、運ぶ砂がないんじゃ浜は痩せていく。自分の子供の頃に比べて随分砂浜の幅が狭くなっている。若い頃は、田舎に帰省すると、ウチの車を借りて、ここを時速100k以上で走ったものだ。窓の外は海、潮風に吹かれて実に爽快である。
その浜が痩せているため、ずいぶんと前から養浜を行っている。なかなか回復しないようだ。写真は、石川県千里浜再生プロジェクト委員会HPより。

なお、これからは、この土木施工管理技士の記事は、こちらのブログで書いていきます。あまりに専門的なのでね。