



小学生対象の教室なのですが、まずは知らない子たちが集まっているので、野島さんはまずゲームを始めました。そのゲームとは1対1でまず向き合ってあいさつをして、自己紹介をした後、自分の背中に貼られた紙に書かれた生き物の名前を、1回だけ質問をして当てるゲームをしながら、みんなが仲良くしていました。
子供たちに一人に1本ずつ色鉛筆を選ばせ、その色を外の田んぼに行って、同じ色の生きものを見つけるゲームが次に待っていた。
以前の二丈町役場が図書館になっていた。ここはサイエンスキャラバンのとき来た以来で、この建物のすぐ裏が田んぼでした。








観察中でも子供たちと生きものの話をゆっくりていねいにひとつひとつされていました。











1時間弱の田んぼ周辺の観察を終えて、教室のある図書館へ。






教室に戻って子供たちが見つけた生物をていねいに確認しながら、いろいろな生きものの質問に野島(こうもり)先生はていねいに答えていかれた。大人でも分かりにくいことを、比ゆを使って、うまく説明されてた。紫外線や赤外線などの言葉を小学生がすでに知っていたことに驚いたりしました。子供たちの中にふざけたがる子供が数人いて、教室を引っかきまわそうとしても、野島先生は怒らない。マイペースをくずさず、さすがでした。
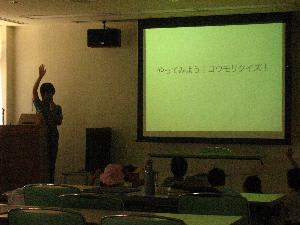
大学院でこうもりの研究をされていたという得意分野を生かして作られた、コウモリクイズが子供たちに受けていました。



コウモリが超音波で地形や生物を感知するということから、子どもたちに手を叩きながら壁に近づいていって、壁にぶつかる前にピタリととまるゲームが楽しそうでした。
コウモリの超音波音を聞こえる音にしたものを聴かしてもらった後、超音波を発生させる装置で実際に超音波を発生させる実験をしてくれるなど、意外とハイテクも駆使しての教室でした。小学生にどれだけ通じたかどうか不明でしたが、コウモリや超音波に興味を持てたのではと思いました。

子供たちを1時間以上集中させることの難しさ、甘やかされてわがままな子どもの扱いなど、知識の伝達以前のことが子どもの教育に立ちはだかっていることを感じました。やはり、教育をエンターテインメントにしなければならないし、それの脚本を創ったり、演出したり、演じる能力が先生に必要だと感じました。しかし、一番は忍耐力と、ユーモアのセンスであることを、野島先生が教えてくれました。

最後、アンケートを子どもたちに書いてもらっていたのですが、かなり熱心というか、長時間書いている子が多かったのが以外でした。
自然のことを教えてくれる大人が傍にいると、子どもは自然を好きになると思います。レイチェル・カーソンが言った「センス オブ ワンダー」を持った子どもでないと、心から環境は守らないと思います。まずは自然を好きになるために、自然の中で遊ばせてあげて下さい。
野島こうもり先生とはまたお会いしようと思って名刺交換しました。
野島さんの考え方があるサイトに連載されていました。
http://www.kosodate.pref.fukuoka.jp/column/archives/cat80/
野島さんがやっている「まいまい計画」のサイトです。
http://maimaikeikaku.net/concept.html
それには糸島がいいですよ。


















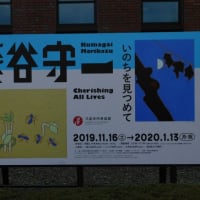
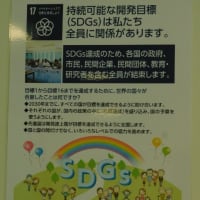
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます