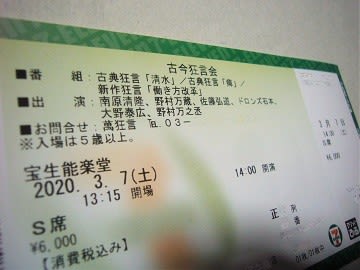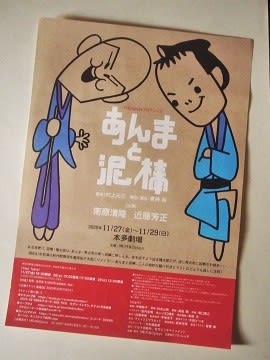お久しぶりでございます。
この3カ月、色々なことがありましたが、お元気だったでしょうか。
私はと言えば、幸い何ごともなく、相も変わらずという感じで過ごしております。
5月末に緊急事態宣言が解除され、ようやく日常が戻りつつある中、6月から末廣亭と浅草演芸ホールが再開。(鈴本演芸場と池袋演芸場は7月から。両館ともビルの中にあるホールなので外とつながる窓がなく、換気が難しいことが再開が遅れた原因かも)
ということで、早速、末廣亭6月上席夜の部へ行ってきました。

初日は昼夜入れ替えなしだったようですが、2日目からは昼と夜で入れ替え。
入場時に検温をしてジェルで手の消毒。マスク着用。
客席は、最前列を空けて2列目から、1席づつ空けて座り、桟敷席も一人空けて互い違いに市松模様柄で2列で座るソーシャルディスタンススタイル(笑)。
上限100名までの入場ということでしたが、私が行った3日目は70~80人くらい・・だったかな?
2階席は閉じたままでした。
陽気なマジックおじさん、ダーク広和さんはこの日も変わらず陽気なしゃべりとマジック。
二ツ目昇進の三遊亭ぐんまさんは、「ランプのぐんま人」という噺だそう。
群馬あるある面白かったです(全然わからなかったけど・笑)。
彦いち師匠は「長島の満月」。
実は、2月9日に末廣亭の昼の部に行ったのですが、その時、小ゑん師匠の代演でトリを務めた彦いち師匠が演ったのがこの噺。
あれから約4ヶ月ぶりに行った末廣亭で、またこの噺を聴けてうれしい限りでした。
ただ、今回はちょっと短めで、満月が出てこなかったのは残念でした。
それから、「初日は飛沫を飛ばして怒られた」そうで(笑)。
この日はマクラはちょっと控え気味で喋ってました(笑)。
はん治師匠は、お馴染みの「妻の旅行」。
寄席でも何度か聴いてますし、5月初めの第1回ABEMA寄席でもこの噺を演ってましたが、何度聴いても面白いな~。
ちょっと調べてみたら、桂三枝(文枝)師匠の創作落語のようですが、はん治師匠の哀愁ただよう姿がこの噺にピッタリでした(笑)。
きく麿師匠は「寝かしつけ」。
この噺を聴くのは2度目ですが、やっぱり面白~い(笑)。
終始大笑い。咳き込むほど笑ってしまいましたが、ちゃんとマスクをしてましたので飛沫は大丈夫だったと思います(笑)。
文蔵師匠は、黒マスクをして登場(笑)。
マクラもそこそこに、季節外れの「時そば」を披露(笑)。
こちらもお馴染みでしたが、面白さは変わらずでした。
そして、トリは喬太郎師匠。
「東京都の回し者じゃないけど」と言いつつ、この日の東京の感染者数を発表する喬太郎師匠(初日からずっと言ってるそう・笑)
皆さん、命知らずで・・みたいなことも言ってましたが、(クラスターが発生した)歌舞伎町にはこのあと行かないでくださいね。もし感染したら末廣亭も・・という話も。
いや、ホントに、もし、寄席に行った人が感染した、みたいなことになったら目も当てられませんので、喬太郎師匠の話は笑いごとではないと気を引き締めながら聞いてしまいました。
その後、夢の話に。
喬太郎師匠は、東京がステップ3になった夢(寝たときに見るほうの夢)を見たそうで。
普通に舞台に上がることが夢になるとは思わなかった・・・という話などもあり、ちょっとしみじみしたあと。
本編は「夢の酒」。
1月に鈴本で聴いて以来の「夢の酒」(笑)。
お馴染みの、やきもちやきのおはなちゃんや、色っぽいご新造とのやり取りを聞いて大笑い。
笑いながら、こうして落語を生で聴けることの喜びを、改めて実感。
何度も聴いた「夢の酒」に耳を傾けながら、いつも通りの日常のありがたさをかみしめた夜でした。

そして。
6月10日、6月上席夜の部の千秋楽。
開口一番の前座さんや、ダーク広和さんのロープマジック、ぐんまさんの「平林」(師匠の白鳥師から唯一教わった古典だそう・笑)などがあり。
続いて上がった柳亭左龍師匠、「(自分が舞台を)降りる時間まであと2分です」(笑)。
ぐんまさんの熱演などがあり、前半でかなり押してしまったようで。
左龍師匠はマクラもそこそこに「まめや」を口演。
その昔、ラジカセを初めて買ってもらいラジオ番組などを録音するのに凝っていた頃、繰り返し聴いていたのがこの噺。
理不尽な展開ですごく印象に残っていたのですが、今まで何度も落語会や寄席に行っても、この噺を聴いたことがなかったので、演る人いなくなっちゃったのかな?と思っていたらそんなことはなかったようで(笑)。
ウンん十年ぶりに聴けて僥倖でした(笑)。
ただ、この日は時間がなかったので、前半は大幅に割愛し、後半だけでしたが、それでもちゃんと落語になっていたのは流石でありました(左龍師は約7分の高座でした)。
彦いち師匠は「遥かなるたぬきうどん」という噺だそう。
演目名は聞いたことがあったけど、ちゃんと聴くのは初めて。
「MILLET(ミレー)の40リットルのザック」というリアルなディテールに、さすがホントにヒマラヤ行っただけのことはあるなと感心しながらも大笑い(笑)。
「ガッシガシ」と氷壁を登る姿が心に深く刻み込まれましたが(笑)、時間の都合で途中まで(左龍師匠が時間を調整してくれたのに、ここで自分が伸ばすわけにはいかない、みたいなことを話してました・笑)。
機会があれば、是非、全編聴いてみたい「遥かなるたぬきうどん」でした。
林家ぺーさんの漫談でも大笑いしつつ、

雲助師匠は「夏泥」。
季節柄なのか、ここ最近この噺は配信などでもよく聴きますが、演る人によって全然違うのが面白いところ。
雲助師匠の陽気な感じの「夏泥」も、面白かったです。
きく麿師匠は、3日目に続き、この日も「寝かしつけ」(笑)。
1週間ぶりに聴いても、やはり爆笑でした(笑)。
続いて登場した扇辰師匠。
いわく、昼夜ともに代演もなく、出演者の順番の入れ替えもない日のことを「寿(ことぶき)」と言うそうで。
この日はまさに「寿」で、珍しい体験&ミニ知識をお勉強してしまいました(笑)。
本編は「田能久」。
ヤニと柿渋は人間でもやだな~、と思いながら聴き入ってしまいました(笑)。
そしてトリは、喬太郎師匠。
「千秋楽は気が楽」という、お馴染みの言葉から(笑)、家から末廣亭に来る道すがらの話などありつつ。
寄席が始まって無事に千秋楽を迎えられて良かった。今はステップ2だけど、ステップ1に戻ったら寄席も出来なくなる。
末廣亭も色々ルールがあって、楽屋に入ると検温をして手を消毒・・・と言いかけますが、「あ、消毒してなかった」「前座さんジェル持ってきて」と言うと、舞台上で手の消毒をし始める喬太郎師匠(笑)。
このへんの自由な感じも千秋楽ならではという感じで大笑いでした。
そして、協会からは「コール&レスポンスの落語は禁止だと言われてるけど、コール&レスポンスの落語ってどういう落語だ?」という愚痴(?笑)や、「それなのにきく麿は歌ってた」という話なども(笑)。
その後は、相鉄線が埼京線に乗り入れた話などなど、お馴染みの話を約20分。
マクラだけでちょっと笑い疲れてしまいました(笑)。
が・・・本編の「一日署長」では、さらに爆笑爆笑また爆笑(笑)。
ついさっき、「コール&レスポンスの落語は禁止と言われてる」と言ってたのに、「東京ホテトル音頭」を熱唱する喬太郎師匠(笑)。
さらに、この日舞台に上がった人たち・・扇辰師、彦いち師、きく麿師、雲助師が噺の中に次々に出てきて、大爆笑。
モノマネをしながら、それぞれの師匠が演った落語の台詞や歌の一部を披露していたのですが、そのチョイスが絶妙で、さらに爆笑。
まるで、師匠方の落語がこの噺のための壮大な前フリになっていたかのような展開に、笑いながらも大感心。
もちろん、それぞれの落語が面白かったので、喬太郎師匠の落語の中でそれがより生かされたのだと思いますが、ライブならではの展開、寄席ならではの「一日署長」が聴けて大爆笑&大満足。
笑いっぱなしであっという間の15分でした。

千秋楽は2階席も開き、上限100名のソーシャルディスタンスの満員。
でも、前述した通り、お客さんは検温、手の消毒、マスクを着用。
客席も一席づつ空けて間隔を保ち、窓も常時開けて換気も十分。
場内の換気扇も勢い良く回っていて、舞台上の声がちょっと聴きづらいくらいに。
さらに、仲入りも普段より1回多く2回。仲入り後はトイレの掃除も念入りに行い、仲入りのときなどには従業員の人が柱などを拭いて消毒。
これ以上ないというくらいの対策をとっていましたので、感染症の専門家じゃないけど末廣亭でクラスターが発生することはないだろうと確信。
安心して楽しむことが出来ました(途中、マスクを外してたお客さんがごくわずかながら、一人、二人いたのが、唯一気がかりではありましたが)。
ここ数カ月、落語の配信が一気に増えて嬉しい限り。
どれも面白く、配信を楽しんでいたのですが、こうやって寄席に来てみると、配信と生の落語は、似てるけど全然別のエンターテイメントだな~と、改めて。
舞台上の噺家さんとお客さんで作る空気の中、生で聴く落語は本当に楽しいな~。
一期一会の舞台は最高!!というのを実感&再確認した、末廣亭の6月上席でした(笑)。