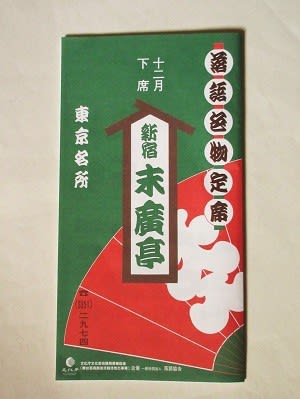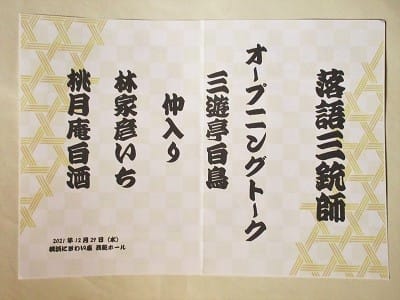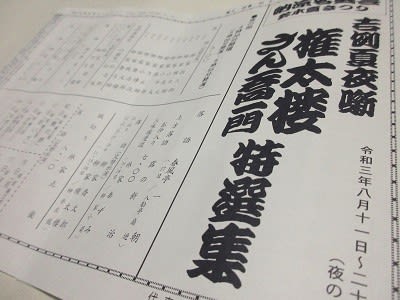♪今は~もう秋~♪の今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。
私はと言えば相変わらず・・ということで、相も変わらず今回も落語の話をあれこれと(笑)。
9月25日は、有楽町よみうりホールで行われた"よってたかって秋らくご'21"の昼の部へ。

前座の三遊亭しゅりけんさんに続き。
発芽の会でお馴染みの萬橘さんが登場。
発芽の会のメンバーは間近で何度も落語を聴いてるだけに自然と応援したくなりますが、この日の萬橘さんは絶好調という感じ(笑)。
名古屋市長の話や、この頃ちょうど話題になっていた総裁選の話などなど、大爆笑のマクラを約10分。
老若男女のお客さんを笑わしてました。
本編の「真田小僧」も客席爆笑。
昔の話なのか現在の話なのかわからないよう細かな工夫がされていて、とても面白かったな~。
こうして発芽の会のメンバーが活躍してる姿を見られて、喜ばしくも嬉しい限りです(笑)。
続いて、喬太郎師匠が登場。
喬太郎師匠が出てくる前に、前座さんがめくりを捲って座布団も裏返し、高座の前を手ぬぐいで拭いていたのですが、出てきた喬太郎師は「前座さん、懐かしい」「いいですね、汗を拭いただけでウケる」(笑)。
あれは飛沫ではなく熱演の萬橘さんの汗を拭いていたんだ!?と、ちょっと感心してしまいましたが、それはそれとして。
マクラでは、今のアイドルなどはみんな同じ顔に見える、でも、高畑充希さんはわかる、「今夜、ケンタッキーにしよう」と映画で共演してる高畑さんネタをさらりと話したり(笑)。
石田ゆり子さんも良い、という話から、白鳥師が昔宝くじに当たった話などなど、こちらも爆笑のマクラを約6分。
本編は「宿屋の富」。
喬太郎師版は初めてでしたが、"柳家"の「宿屋の富」はやっぱり主人公の客はなまってるんだな~と、妙なところで感心しつつ(笑)、喬太郎師らしい工夫もあって大笑い。
まだ、ちょっとこなれてないかな~という場面もありましたが、約20分終始楽しかった「宿屋の富」。
初めて喬太郎師でこの噺を聴けて僥倖でした。
仲入りをはさみ。
百栄師の「修学旅行の夜」という噺に続き。
白酒師匠が登場。
マクラでは、楽屋で喬太郎師と萬橘さんを間違えて挨拶してしまい「何で萬橘に・・」という話や、厄払いに行ったほうがいいけど「萬橘は何をやっても無理」という話など、萬橘さんイジリが何度か出てきて大笑い(笑)。
それ以外にも、サラリと毒を吐くマクラに客席爆笑でした。
本編は「死神」。
白酒師の「死神」は何度聴いても面白いな~。
あんなに血色が良くて世話好きで明るくて、ぜ~んぜん怖くない死神は他にはないな(笑)。
あ、それから、呪文も大笑い。
前述した通り、この時はちょうど総裁選の頃だったので、呪文は「あじゃらかもくれん総裁選本当は嫌がらせで出たんだろ?」
続けて、「野田?野田?」とツッこんでたのも大笑いでした(笑)。
萬橘さん、喬太郎師、白酒師と、お目当ての人の落語を満喫して楽しい一日でした。
10月16日は、さいたまスーパーアリーナにあるTOIRO(たまアリ△タウン)で行われた、第56回TOIRO寄席・林家彦いち独演会へ。

さいたまスーパーアリーナへは初めて来ましたが、アリーナではこの日はもも〇ロの人のコンサートをやっていたようで。
どうりで赤い服の人がゾロゾロと大勢いたわけです(笑)
落語会が行われたTOIROは、200席ぐらい(?)の可動式の椅子があるスタジオ。
チビッこや夫婦などなど、老若男女のお客さんでした。
開口一番は、彦いち師匠の弟子のきよ彦さん。
マクラでは、今日はも〇クロのコンサートや、ホールの下ではアウトドアのイベントをやっているので、アウトドア好きの彦いち(師)はいなくなってるかも、という話などがあり。
本編は「反抗期」という噺。
以前にも聴いたことありますが、元ヤンのキャラがよき彦さんに合っていて面白かったです。
彦いち師匠は、若草色の着物を着て登場。
彦いち師いわく、TOIRO寄席は今回で56回目だけど今まで出なかった。白鳥が出てるのに彦いちが呼ばれないわけはないのに・・と思ったら、土曜日はラジオやっていたので呼ばれなかった。去年の9月にラジオが終わって依頼が来たけどコロナで延期になり、今日初めて来た、とのこと。
確かに、白鳥師が呼ばれて彦いち師が呼ばれないのは道理に合いませんので、今回彦いち師の会が開催されて何よりでした(笑)。
その後は、今日はアウトドアのイベントをやっていて、その昔「BEE-PAL」というアウトドア雑誌で知り合ったライターやカメラマンがいたので挨拶したら、色々思い出した・・・という話から、長良川河口堰反対のイベントに呼ばれて2000人くらいの前で落語をやった話に。
私も「BEE-PAL」を購読してたことがあるので、彦いち師匠がアウトドア落語家として雑誌に載ってたことを思い出したり、CW・ニコルさんや野田知佑さんという名前が出てきて、当時のことを懐かしく思いながら大笑いして彦いち師の話を聴いてしまいました。
まさか、「BEE-PAL」に載ってた彦いち師匠を見てからウン十年して、師匠の独演会に来るようになるとは!?夢にも思いませんでしたが、これも縁というものなのかもしれません(笑)。
あとは、弟子の山びこさんの話や、緊急事態宣言中の「寄席は社会生活に必要?」というお馴染みの話(笑)など、大笑いのマクラを約30分たっぷり。
このへんの自由なところは、独演会ならではという感じでした。
本編は「天狗裁き」。
彦いち師でこの噺を聴くのは二度目(かな?)ですが、嫌味なく陽気な感じで、とても面白かったです。
仲入りをはさみ。
あずき色の着物に着かえた彦いち師匠が登場。
「白鳥は同じ着物だと思いますけど」という話から、「あんな嘘つき見たことない」という話に。
詳細は割愛しますが、白鳥師の嘘つきっぷりに大笑いでした(笑)。
その後、彦いち師が嘘をついて大変なことになったという話から。
本編は「神々の唄」。
この噺も以前、聴いたことがありますが、"スーザン・ボイッ"に大笑い。
マクラの嘘の話からの流れで、とても面白かったです。

TOIRO寄席は演者とお客さんとの距離も近く、ライブ感満載。
また、機会があれば是非行ってみたい、林家彦いち独演会でした。
10月21日からは、末廣亭十月下席へ。

まずは初日。
末廣亭の高座に飛沫防止のアクリル板が設置されている、というのは彦いち師や喬太郎師などが話してるのを聞き知ってはいましたが、じかに見るのは初めて。
そんなに大きくはありませんが、違和感は感じるアクリル板。
ちょっと邪魔だけど、演者さんはあのアクリル板に自分の顔が映ってるのね・・などと考えると思わず笑いそうにはなります(笑)。
一席づつ空けたソーシャルディスタンスではなく、普通にお客さんを入れた夜の部の客席は、最終的には8割くらいの入りでした。
この日は早い出番に変更になっていた小猫さんの、お馴染みのウグイスや初めて聴く八色鳥の動物モノマネ。
翁家社中の太神楽(小花さん復帰したようで何よりです)などがありつつ。
仲入りのあと。
きく麿師匠が登場。
「おもち」という噺のようで。
「もち好きですか?」というフレーズがやけに耳に残る、不思議な噺・・・。
今まで聴いたきく麿師の高座はいつも爆笑でしたが、この日は笑いはあまりなし。
ずいぶんシュールな落語だな~と思っていたら、きく麿師はツイッターで「意気込んでやるとすべる」とつぶやいていましたので、シュールではなくただ単に滑ってただけみたいです(笑)。
左龍師匠の代演で登場の甚語楼師匠。
「猫と金魚」という噺だそう。
グッチ裕三さん似の甚語楼師匠(笑)、(たぶん)初めてでしたが面白かったです。
続いて、彦いち師匠が登場。
マクラでは、寄席は入れ代わり立ち代わり不思議なおじさんたちが出てくる・・という話から、きく麿師が「もちを・・」と言ってたけど受けてるわけでもなく・・と、きく麿師をフォローしたりしつつ(笑)。
先日のTOIRO寄席でも話していた、緊急事態宣言中の話などもたっぷり。
アクリル板の上から首が出てしまう市馬会長の話を、本家本元、本場の末廣亭で聴けたのは僥倖でした(笑)。
その後は、羽織を脱ぐと見せかけてまた着直してみたり(笑)、約15分の長めのマクラのあと。
本編は「遥かなるたぬきうどん」。
マクラが長かったぶん、ガッシガッシと氷壁を登っている途中で終わってしまいましたが、客席は終始爆笑。
さすがでありました。
小菊師匠の三味線をはさみ
トリの喬太郎師匠が登場。
「アクリル板にも慣れてきて・・」という話など、短めのマクラのあと。
本編は「居残り佐平次」。
かっつぁんと調子良すぎの佐平次のやりとりに大笑い。
以前 鈴本で「歌う居残り佐平次」の「ニッポン居残り時代」は聴いたことがありましたが、歌わないほうの「居残り~」は初めて(オチの前に一節だけ歌ってましたが・笑)。
彦いち師匠が出てくるくすぐりもあったり、喬太郎師匠らしい工夫も随所にあり、とても面白かったです。
この日の客席は全体的に重たい感じでしたが、仲入り後は、彦いち師が長めのマクラで爆笑させ、最後は喬太郎師が大笑いの古典でしめ、めでたしめでたしでした(笑)。

末廣亭十月下席6日目
前日の5日目から舞台上のアクリル板がなくなったそうで。
普段の光景が戻った末廣亭。
初日にイレギュラーなアクリル板を体験しておいて良かったです(笑)。
権之助師の「粗忽長屋」や、琴調師の講談「愛宕山梅花の誉れ」などありつつ(この日は琴調師の師匠の馬琴師の命日でこの噺は昭和天皇の前で披露したそう)。
雲助師の「洒落番頭」でも大笑い。
雲助師匠の独特の口調は聴いていてクセになります(笑)。
仲入り後は入場料が半額の1500円ということもあってか、お客さんがゾロゾロ。
老若男女で場内は満員に。
若い女性も多く入ってました。
仲入り後、まずはきく麿師匠。
マクラで得意の小林旭さんの歌を歌ったあと(笑)。
本編は「だし昆布」という噺だそう。
最初はどんな噺なんだ???と、不思議な感じで聴いていたのですが・・・。
途中からは、爆笑、爆笑、また爆笑。
笑い過ぎて涙出た!
どうやったらこんな噺を思いつくんだ!?と笑いながらも感心してしまいました(笑)。
ネタバレな内容は割愛しますが、初日とは打って変わって大爆笑の高座でした。
続いて登場の小猫さんは、きく麿師の噺のネタをちょっと織り込みづつ(笑)。
お馴染みの初春のウグイスやヌーなどなど、安定の面白い高座でした。
左龍師匠。
「きく麿は変わってる。キ〇ガイで外に出しちゃいけない・・」みたいなことをマクラで話したりしながら(笑)。
本編は「宮戸川」。
こちらも、安定の高座という感じで面白かったです。
続いて、彦いち師匠。
きく麿師匠のことを「変わってる」と話していた左龍師について、彦いち師は「左龍さんも変わってる」「男梅みたいな顔して・・」と話していて場内爆笑(翌日から左龍師のツイッターのアイコンが男梅に変わってました・笑)。
その後、緊急事態宣言が解除されお客さんが戻って来た・・という話から、初日の末廣亭の話に。
常連さんもいれば、初めての人もいる客席。
甚語楼師匠の「猫と金魚」を聴いてたお客さんの反応が・・・という話に大爆笑。
この後もどこかでこの話をするかもしれませんので詳細は割愛しますが、初日に現場にいただけに、彦いち師匠の話により爆笑してしまいました(笑)。
そんな爆笑のマクラのあと、本編は「つばさ」。
お馴染みの噺ですが、何度聴いても面白いパラレルワールドの落語でした。
正楽さんの紙切りをはさみ。
ひときわ大きな拍手のなか登場した喬太郎師匠。
「ヒザ前に正楽師匠、ヒザに彦いちさん、そして弟弟子の左龍がいて自分がトリを務める、こんなうれしいことはない・・」という話があり。
「夢は五臓六腑の疲れが・・」という話に。
ん?もしかして「夢の酒」かな?と思っていたのですが・・・。
始まったのは、左龍師が演った「宮戸川」の続き。
お花と半七が一晩過ごした後の話・・。
喬太郎師匠の「宮戸川(下)」は噂では聞いてましたが、ここで聴けるとは!?
まさに僥倖。
静まり返る満員の客席、聴こえてくるのは空調の音と舞台上の喬太郎師匠の声、そして三味線の音色だけ・・・。
固唾を呑んで喬太郎師の噺に聴き入ってしまいました。
終演後は、万雷の拍手。
この日に行って良かったな~と、つくづく思った、末廣亭十月下席6日目でした。
仲入り後は、大爆笑からジッと聴かせる話まで盛りだくさん。
それぞれの演者さんの想いがつながった高座は最高!
大満足の夜でした。

末廣亭十月下席8日目。
当初は、今席は3日くらい行ければいいかな~と思っていたのですが、6日目が素晴らし過ぎたので、我慢できずにこの日も参戦(笑)。
(7日目の居太郎師匠は「任侠流山動物園」だったというのを聞いて、前日も行けばよかったと激しく後悔・笑)
夢葉さんのお馴染みのマジックや翁家社中の太神楽に感心したり、権之助師の「紙入れ」、馬玉師の「もぐら泥」などの古典で笑いつつ。
講談の琴調師は「忠臣蔵」の話。
もうそんな季節なのか!?と、ちょっとびっくりしながらも、吉良邸討ち入り後の赤穂浪士の話に聞き入ってしまいました。
仲入りになると、この日も大勢のお客さんが入り満員に。
最終的には立ち見も出る盛況ぶりでした。
仲入り後まずは、きく麿師匠。
お客さんの期待度も高めという感じで、それまでとは桁違いに大きな拍手。
きく麿師が「仲入り後は変な空間に・・」と言い、始まったのが「暴ソバ族」という噺。
確かに、一気に変な空間になり、きく麿師ワールドに引き込まれ場内大爆笑(笑)。
途中、噛んでしまったり上下も間違えたりしていたきく麿師匠でしたが、それもネタにして最後まで爆笑の高座でした。
続いて登場した小猫さんいわく、「きく麿師匠カミカミだったとうなだれていた」とのこと(笑)。
きく麿師→小猫さんの、このちょっとしたやり取りが、とてもいい感じで場内爆笑でした。
モノマネのほうは、お馴染みの初春のウグイスをはじめ、以前子供からリクエストされたというクラゲ(「喬太郎師匠のクラゲとは流派が違う」とのこと。これは2日目(だったかな?)に喬太郎師匠が演ったらしい「母恋くらげ」を受けての話でしょう)、パンダの日ということでパンダの鳴き声などなどを披露してました。
左龍師匠は「のめる」
きく麿師匠が作った変な空間とは一線を画す古典でしたが、面白かったです。
続いて登場の彦いち師匠。
「落語の登場人物は、熊つぁん八っつぁん、一生懸命なのはムアンチャイ・・」と話し始めると、客席からは拍手(笑)。
「何でここで拍手が・・」言いつつ、「仲入り後は変なおじさんが入れ代わり立ち代わり」「きく麿でゴングが鳴った」と続ける彦いち師匠に大笑い。
で、本編は、やはり「かけ声指南」(笑)。
久しぶりにムアンチャイに会えてうれしい限り(笑)。
健気で一生懸命なムアンチャイに爆笑、また爆笑。
何度聴いても面白い「かけ声指南」でした。
この日は正楽さんはお休み。
代演のストレート松浦さんは、「ムアンチャイのあとでこの名前・・」と言って場内爆笑。
そして、「仲入り後は変なおじさんが・・」「それだったら断ってた」とぼやき、また爆笑でした(笑)。
お馴染みのパフォーマンスで大きな拍手を受けていたストレート松浦さんでしたが、中国コマでは"伊藤夢葉"という技を披露したり(夢葉さんの趣味のムチを振るマネ・笑)、「どこかで見たかも・・」と言いながら皿回しをやってみたり(翁家社中がやってた)、この日登場した人たちの「一日を振り返る」パフォーマンスに、場内さらに大きな拍手でした。
最後のシガーボックスも成功し、いつにも増して大きな拍手のなか退場したストレート松浦さん。
仲入り後の変なおじさんたちに負けず劣らずの素晴らしいパフォーマンスでした(笑)
そして、大きな拍手のなか登場したトリの喬太郎師匠。
この日はマクラはなしで「死神」を熱演。
細かなくすぐりや、呪文で笑わしたりしつつも、徐々に怖~い展開に。
ラスト10分くらいは、固唾を呑んで聴き入ってしまいました。
一昨日に続き、静まり返る満員の場内。
そして、万雷の拍手で幕。
喬太郎師匠の「死神」を聴いたのは、2018年の夏のかめありリリオホール以来。
この時から、喬太郎師匠の落語を本格的に聴くようになったので、個人的に感慨深い噺。
そんな「死神」を久しぶりに聴けて良かったです。
それにしても、この噺は、演る人によって全然違うな~。
喬太郎師は、前半笑わせながらも、最終的には怖~い「死神」。
白酒師は、血色がよくて世話好きで爆笑の「死神」(笑)。
小三治師匠は、可笑しくも哀しい「死神」。
・・・改めて、落語の魅力に触れた夜でした。

末廣亭十月下席9日目
昨日が楽し過ぎたのでまたまた参戦、連日の末廣亭(笑)
権之助師匠の「長短」や馬玉師匠の「紙入れ」、雲助師匠の『粗忽の釘」など、夜の部の前半は安定の高座。
この日は仲入りで2階席も開き、満員のお客さんでした。
仲入り後。
きく麿師匠は「客席から笑わせろという圧がすごい・・」と言いながらも、その圧に負けずにこの日も爆笑の高座(笑)。
「やさしい味」という噺だそうですが、ず~~と笑いっばなしで、笑い疲れた(笑)。
「やさしいお味」という言葉が耳に残って仕方がない、「やさしい味」でした。
大爆笑と大きな拍手のなか、退場したきく麿師匠が楽屋口で「あっためておきました」と言う声と、それに対しての楽屋の笑い声が聞こえてきて、客席も大笑い。
そして、続いて登場した小猫さんが開口一番「きく麿さん、ご満悦でした」と言うと、客席はまた大笑い(笑)。
さらに、お馴染みの初春のウグイスでは「いつになくやさしい音色」と、きく麿師匠の噺を受けての言葉に、またまた客席爆笑でした。
その後は、普段あまり聴かないサイのやゴリラのモノマネなどがあり、大盛り上がりのうちに小猫さんも退場。
きく麿師→小猫さん、の流れは、やはり良いな~。
左龍師匠は「初天神」。
絶妙な間と顔芸(笑)が面白く、さすがという感じで大笑いでした。
彦いち師匠は、「仲入り後は寄席の多様性を・・」と言い、この日も初日の「猫と金魚」を聴いたお客さんの話をしていて大笑い。
何度聴いても面白いマクラになっていて、この後もあちこちで聞けるかも?(笑)
その後は、寄席では同じような噺はしないことになっている・・と言いながら「お父さん連れてってよ!」と左龍師の「初天神」と同じ台詞を言い出して大爆笑。
「今席、何やってもいいと思ってるだろ?」「後の人がどうにかしてくれる」「楽しくて仕方ない」と、楽しそうに話す彦いち師匠(笑)。
確かに、舞台上の楽しさが客席にも伝わってくる高座で、聴いていても楽しくて仕方ありませんでした。
その後も「お前、今日自由だな」「明日で終わるのが寂しいな」という彦いち師の心の声をはさみつつ(笑)。
本編は「二月下旬」という噺だそう。
喬太郎師匠の「八月下旬」は聴いたことがありましたが、「二月下旬」は初めて。
ちょっと調べてみると「二月下旬」は「八月下旬」を改作した作品のようで。
確かに、似たテイストの噺ですが、どちらも面白いですし、喬太郎師とはまた一味違う彦いち師の噺を聴けて(たぶん途中まで)、良かったです。
正楽さんは、ハサミ試しで喬太郎モデルの"相合傘"を切ったあと、お客さんの注文で"白川郷"と"ハワイの雪"も切っていましたが、喬太郎師の"ハワイの雪"のラストの部分を切った作品は見事で大感心でした。
大きな拍手の中、正楽さんも退場。
そして、トリの喬太郎師匠。
日大出身の柳家喬太郎です・・で爆笑をとったあと(定期的に日大はネタになるな・笑)、末廣亭の周辺でソーシャルディスタンス無視して飲んでる人たちに「死んでしまえ!」と悪態をついたりしつつ(大笑)。
本編は「ハワイの雪」。
まさか「ハワイの雪」が聴けるとは!?
紙切りのお題で出たけどやらないよ・・なのかと思ったら、あえてのこの噺。
文字通り僥倖でした。
客席もちょっとザワつくなか始まった「ハワイの雪」は、爆笑、爆笑、また爆笑。
そして・・・。
徐々に噺に引き込まれ、途中から自然と涙が出ていました。
場内からも、鼻をすする音があちこちから聞こえてくるなか、鳴りやまない万雷の拍手で終演。
「ハワイの雪」は何度か聴いていますが、前に聴いた時には、今現在の話として語るにはちょっと時代の整合性が取れなくなってるのかな??という場面も・・・。
でも、この日はそんな違和感は全く感じさせず、初めから終わりまで集中して聴くことができました。
気付かないよう微妙に修正したり工夫をしていたのだと思いますが・・とまれ、最高の「ハワイの雪」を聴けて良かったです。
爆笑に涙にと、彦いち師匠が言っていた「寄席の多様性」を体現していた末廣亭9日目。
本当に最高の夜でした(この日だけではなく毎晩最高なのですが・笑)。

末廣亭十月下席千秋楽
土曜日ということで、昼の部の後半から末廣亭に行きましたが、すでにほぼ満員。
昼の部が終わると帰るお客さんも多かったですが、入れ替わりで多くのお客さんが入り、17時前には2階も開き老若男女で満員でした。
権之助師の「熊の皮」という噺や、琴調師の講談などを聴いたりしつつ(8日目と同じ「忠臣蔵」でしたが、2回目だと話がよくわかる)。
この日代演の歌奴師の「掛け取り」に大笑い。
狂歌好きの大家さんに続いて、寅さん好きの掛け取りの人が来て「男はつらいよ」の場面を再現(笑)。
喬太郎師匠の「掛け取りバンザイ」を彷彿とさせ爆笑でした。
そして、翁家社中のお馴染みの太神楽・・と思ったら、普段は前座さんが出てくる包丁を使った皿回しのところで、前座としてきく麿師が登場!?
とぼけた笑顔を客席に向けるきく麿師匠に大笑い(笑)。
高座に横になり、包丁を軸にした皿回しを下から見上げ、最後は、這う這うの体という感じで、這って袖に帰っていくきく麿師匠。
仲入り前から自由なきく麿師匠に爆笑でした。
雲助師匠に「身投げ屋」で笑ったあと、仲入り。
仲入りでさらにお客さんが入り、2階席の奥まで満員になり、数多くの立ち見も出て大入り満員でした。
仲入り後。
大きな拍手のなか登場したきく麿師匠。
「前座のきく麿です」という挨拶で爆笑をさらったあと。
「おい、ロボ公」「ウィーン、ウィーン、ウィーン」と言いながら噺がスタート。
何だこれ??と思っていたら「ロボット長短」という噺だそうで。
いや~、笑った笑った(笑)。
爆笑、爆笑、また爆笑、咳き込むほど笑ってしまいました(笑)。
途中、「喬太郎師匠の芝居のくいつき(仲入り後の出番)で緊張してる」と言いつつも、大爆笑の高座。
どうしてこんな発想になるのか、それも不思議で面白いですが、とまれ、笑いっぱなしで疲れました(笑)。
大きな拍手を背に楽屋に戻ったきく麿師匠。
「あたためておきました」という大きな声がこの日も聞こえてきて、客席はさらに大笑いでした(この日はわざと聞こえるように言ってたみたい・笑)。
続いて登場した小猫さん。
「きく麿師匠とは切り替えて・・」と言い、普通に初春のウグイスの話が始まったので、今日はきく麿師のネタはないのかと思いきや・・・。
ウグイスを鳴くために指を口元に持っていくときに、小猫さんの口からも「ウィーン」(大笑)。
ロボット小猫さんになっていて、大爆笑でした。
いや、ホント、きく麿師→小猫さんの、この流れは、毎回楽しかったです。
その後は、アンデスイワドリなど初めて聴くモノマネなどもあり、軽妙なおしゃべりを交えた小猫さんの出番は終了。
変なおじさんが入れ代わり立ち代わりするなか、毎回、それに負けない小猫さんの高座はさすがでした。
左龍師匠は「馬のす」という噺だそう。
文蔵師匠や川柳川柳師匠も登場して、面白かったです。
続いて、彦いち師匠。
いわく「仲入り後は自由演技」とのことでしたが、きく麿師は仲入り前から翁家社中に飛び入り参加したりして、自由だったな~と思いつつ(笑)。
この日もマクラでは、初日の「猫と金魚」のお客さんの話(笑)。
すでに3回目ですが、何度聴いても面白いマクラです。
本編は「私と僕」という噺。
以前にも聴いたことがありますが、多層的で不思議な噺だな~。
彦いち師匠の創作落語は、面白いだけではなく切なさや甘酸っぱさも感じさせる噺が多い感じ。
この「私と僕も」、爆笑しながらも余韻を残して終了。
彦いち師らしい高座でした。
正楽さんは、♪こんにちは赤ちゃん♪のお囃子にのせて"双子のパンダ"を切ったりしつつ。
トリの喬太郎師匠が、大きな拍手のなか登場。
マクラでは、ハロウィンの話などがあり、いざ本編に入ろうとしますが・・。
いきなり噛んでしまう喬太郎師匠(笑)。
でも「噛まないで流暢にやってるうちはまだ青いんだよ!」と逆切れ(笑)。
場内爆笑でした。
そんな中始まったのは「一日署長」。
♪東京ホテトル音頭♪
♪東京イメクラ音頭♪
♪大江戸ホテトル小唄♪
を大熱唱の喬太郎師匠(笑)。
客席からは大きな手拍子で大盛り上がりでしたが、3曲続いてさすがに長いと思ったのか「途中からは仕方ない手拍子を・・」「でもやめられないんだよ」と自虐ネタもあり、さらに爆笑(笑)。
今回の「一日署長」は、犯人が喬太郎師匠で、説得に来るのが正楽さんと彦いち師匠という組み合わせ。
以前、聴いた時は市馬会長が犯人だったり、扇辰師が犯人だったりしましたが、その時々で変わるのがこの噺の面白いところです。
とまれ、テンション高い喬太郎師匠に終始大笑い。
あっという間に30分が過ぎてしまいました。
最後は、「みんな!コロナに負けるな!じゃあな!!」と言い残して幕。
大きな大きな拍手のなか、大団円で終了した末廣亭十月下席でした。

今席は、10日のうち5日参戦。
前述した通り、最初は3日ぐらい行ければ良いかな~と思っていたのですが、あまりにも楽し過ぎて連日末廣亭に通ってしまいました(笑)。
特に、仲入り後の楽しさは尋常ではありませんでした(笑)。

この並び、最高過ぎます。
きく麿師匠は連日大爆笑の高座。
小猫さんは、きく麿師を受けてのひと言が毎回素晴らしく、おしゃべりもモノマネも最高!
左龍師匠は古典で大笑い。
彦いち師匠はマクラで爆笑、本編も爆笑。
正楽さんは安定のおしゃべりと紙切り。
そして、喬太郎師匠は、爆笑、熱唱、じっくり聴かせて、泣かせて、また爆笑と、変幻自在の高座。
連日本当に楽しい時間を過ごすことができました。
初日は微妙な空気ではありましたが(きく麿師匠も笑いほとんどありませんでしたし・笑)、後にその時の様子を彦いち師が爆笑のマクラにしていましたので、妙な空気の初日の現場に居合わせたのも、逆にラッキーでした(笑)。
それから、初日からお客さんが徐々に増えていき、千秋楽は2階席も開き大勢の立ち見が出るほどの大入りに。
お客さんの期待と熱気が日々高まっていくのを、身をもって感じることが出来たのも嬉しいことでした(客席は一席づつ空けることはなく通常どおりでしたが、マスク着用、食べ物禁止、空調は全開、窓は開けっ放しで換気をして感染対策をしてました)。
改めて、末廣亭十月下席最高でした!!