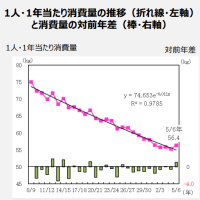昨日、NTT docomoから「iモード」に実装されていた「絵文字」の提供を終了する、と発表した。
Impress Watch: 「ドコモ絵文字」新機種に搭載されず 26年の歴史に幕
そもそも「iモード」というサービスそのものを知らない、デジタル世代が多くなってきていることを考えると、既に来年の3月末でサービス終了が決まっている「iモード」に実装されていたのだから、順次発売されるスマートフォンに搭載されなくなるのは、仕方ないというか当然なのかもしれない。
とはいえ、今やスマホに「絵文字」は欠かせない表現の一つであり、定着している、と考えてもよいだろう。
この「絵文字」が、携帯電話のメールの文字の一つとして登場した時、「言葉で表現できないほど、言語力が落ちたのか?」という趣旨のことが言われたような記憶がある。
当初「絵文字」そのものは、あまり快く思われない存在だったのだ。
その理由として挙げられるのは、当時の携帯電話という通信機器の社会的位置づけだ。
当時の携帯電話ヘビーユーザーとして考えられていたのは、ビジネスパーソンだったからだ。
学生やOL、家庭の主婦は携帯電話のヘビーユーザーという位置づけではなかったのだ。
ビジネスシーンでデータ送信の一つとして「(ビジネス)メールを送る」のであれば、「絵文字」そのものは必要ない、と考えられていたのだ。
それを大きく変えたのが、「iモード」に実装されていた「絵文字」ということになる。
そしてこの「絵文字」は、潜在的携帯電話ユーザーであった学生を中心に、爆発的な人気を呼ぶことになる。
その理由は「文字や言葉では表現できない、その時の自分の気持ち」を、「絵文字」として伝えるツールとして、使われるようになったからだ。
考えてみれば、日ごろ私たち日本人が使っている「漢字」は「象形文字」の一つと言われている。
物や出来事の状況をカタチとしてあらわし、それを文字(=漢字」として発展させてきたのだ。
そのことを、漢文学者・白川静博士は「白川文字学」として、まとめている。
白川博士の考えが正しいのか?という、議論があることは知っているが、それでもその解釈には納得ができるところがある。
そのような「漢字」が持つ背景に、現代的な日本人の感性が合わさったモノが「絵文字」という、表現だったのでは?と、考えている。
だからこそ、海外では「日本のカワイイ文化」の一つの表現手段としての「絵文字」が注目され、海外でも「emoji」として使われるようになったのではないだろうか?
そう考えると、「絵文字文化」を定着させたdocomoの「iモード」や「FOMA®」は、携帯電話文化を大きく発展させてきた、と言っても過言ではないと思うし、このような文化をつくってきたサービスが通信技術の発展などにより、終了するのは残念な気がする。
とはいえ、「docomoの絵文字」は新しいdocomoのスマホの機種から使われなくなるとしても、「絵文字文化」が定着した現在では、代わりとなる「絵文字」がある。
ユーザーは、それほど心配していないかもしれない。
考えてみれば、日本の非言語表現力は、もっと世界から注目されてもよいのでは?
今や世界で当たり前に使われている「ピクトグラム」などは、その代表格だろう。
様々なハンディの有る人達にとっても、「わかりやすさ」を表現する発想の中には、日本語という複雑な言語だからこその「思いやり」の表現なのかもしれない。
最新の画像[もっと見る]