amazonで買ったUnsung Heros~ですが、一向に読み進まず(汗)ようやくメリーの章の原作について書かれた部分を読み終わりました。これでメリーの章の3分の一くらいかなー(汗)
このメリーの章のタイトルが「Merry as a knowledgeable hero」なのですが、このkowledgeable heroが上手く訳せないので「ものしりヒーロー」とか投げやりな訳をつけてみました(汗)変な訳なのはわざとやったのです、わざと。(吹き替えギムリ風(笑))
各章には全部「なんとかヒーロー」というタイトルがついています。要するにこの本、各々のキャラクターの英雄性について書いているんですよね・・・
という訳で、メリーを3分の一読んだ時点で、なんとなくピンと来ないものを感じていたりして。
いや、間違ったことは書いてないのですが、なんとなく私が感動した部分とはズレたところについて書いてあるのですよね。
読んでいて「なるほど~」と思うような斬新な解釈も特にないし。私がちゃんと英語理解してないだけかもしれないけど・・・
でも、引用されていた他の人の説には「ほう」とか思ったりしましたからねえ(汗)「メリーの堅実さ、ピピンの勇気?は、セオデン、アラゴルン、デネソールの性質を受け継いでいる」というような。(超適当訳ですのでご容赦を(汗))
書いてあっただいたいの内容は、メリーがブランディバック家の館主になるべくしかるべき教育を受けていたため、知識欲があり、バック郷でも、ビルボの家でも様々な本を読んで知識を得ていたのだろうということ、裂け谷でももちろん時間を上手く使ってましたし、そういったメリーの知識がホビットたちの行動の指針となり、仲間たちを助けた、ということでした。
そして、旅をして行く中で、様々な知識や経験を得て、それらがホビット庄での指導者的位置につくのに役立った、と。
うーん、そうなんだけど・・・メリーが物知りなのは話の都合上という気がしなくもないんですが(汗)
まあ、メリーがその後たくさんの書物を書き残したというあたりが、学者のトールキンらしいキャラクター造形だ、みたいな話はちょっと「なるほど」と思いましたけど。
確かにメリーはものしりで頼りになりますが、メリーの魅力ってものしりなところなのか? と思うとなんだか違うような。頼りになるところは魅力ではあるんですけど。
また、一般的な物語の主人公が辿る、旅立ちのイニシエーション=通過儀礼を経て成長していくというパターンを象徴している、なんとことも再三出て来てました。
「ホビット庄の掃蕩」では、そのメリーの英雄的なところが発揮されて云々で締められていたのもうーん、でした。確かにそうなんだけど、メリーやピピンの活躍は、フロドとの対比として描かれていると思うので、そのことに全く触れないで締めてしまうとなあ・・・
まあ、HoMEを読むと、「ホビット庄の掃蕩」では、最初はフロドの台詞だったのが完成版ではメリーの台詞になった、という箇所が随分あるようなのですが。
ただ、続きの映画のメリーについての文章をちょっと読んだら、メリーが「ピピンがちょっと年上になった感じ」のキャラクターになっているという指摘などあって、ちょっとうんうん、とうなずいてしまったのですが。
この微妙な違和感は、やはりこの本が書かれた意図にあるのかなあと。そもそも9.11のテロのことと絡めて「無名の人々の英雄性」みたいなことを序章でも書いてましたからねえ・・・
確かに「指輪物語」の脇役たちにもそれぞれに英雄性はありますが、それを前面に押し出されるとなんだか違和感があるんですよね。うーん。
まあ、もう少し、せめてメリーの章を読み終わってから判断したいと思いますが。この後は映画と原作の比較に入るようなので・・・
このメリーの章のタイトルが「Merry as a knowledgeable hero」なのですが、このkowledgeable heroが上手く訳せないので「ものしりヒーロー」とか投げやりな訳をつけてみました(汗)変な訳なのはわざとやったのです、わざと。(吹き替えギムリ風(笑))
各章には全部「なんとかヒーロー」というタイトルがついています。要するにこの本、各々のキャラクターの英雄性について書いているんですよね・・・
という訳で、メリーを3分の一読んだ時点で、なんとなくピンと来ないものを感じていたりして。
いや、間違ったことは書いてないのですが、なんとなく私が感動した部分とはズレたところについて書いてあるのですよね。
読んでいて「なるほど~」と思うような斬新な解釈も特にないし。私がちゃんと英語理解してないだけかもしれないけど・・・
でも、引用されていた他の人の説には「ほう」とか思ったりしましたからねえ(汗)「メリーの堅実さ、ピピンの勇気?は、セオデン、アラゴルン、デネソールの性質を受け継いでいる」というような。(超適当訳ですのでご容赦を(汗))
書いてあっただいたいの内容は、メリーがブランディバック家の館主になるべくしかるべき教育を受けていたため、知識欲があり、バック郷でも、ビルボの家でも様々な本を読んで知識を得ていたのだろうということ、裂け谷でももちろん時間を上手く使ってましたし、そういったメリーの知識がホビットたちの行動の指針となり、仲間たちを助けた、ということでした。
そして、旅をして行く中で、様々な知識や経験を得て、それらがホビット庄での指導者的位置につくのに役立った、と。
うーん、そうなんだけど・・・メリーが物知りなのは話の都合上という気がしなくもないんですが(汗)
まあ、メリーがその後たくさんの書物を書き残したというあたりが、学者のトールキンらしいキャラクター造形だ、みたいな話はちょっと「なるほど」と思いましたけど。
確かにメリーはものしりで頼りになりますが、メリーの魅力ってものしりなところなのか? と思うとなんだか違うような。頼りになるところは魅力ではあるんですけど。
また、一般的な物語の主人公が辿る、旅立ちのイニシエーション=通過儀礼を経て成長していくというパターンを象徴している、なんとことも再三出て来てました。
「ホビット庄の掃蕩」では、そのメリーの英雄的なところが発揮されて云々で締められていたのもうーん、でした。確かにそうなんだけど、メリーやピピンの活躍は、フロドとの対比として描かれていると思うので、そのことに全く触れないで締めてしまうとなあ・・・
まあ、HoMEを読むと、「ホビット庄の掃蕩」では、最初はフロドの台詞だったのが完成版ではメリーの台詞になった、という箇所が随分あるようなのですが。
ただ、続きの映画のメリーについての文章をちょっと読んだら、メリーが「ピピンがちょっと年上になった感じ」のキャラクターになっているという指摘などあって、ちょっとうんうん、とうなずいてしまったのですが。
この微妙な違和感は、やはりこの本が書かれた意図にあるのかなあと。そもそも9.11のテロのことと絡めて「無名の人々の英雄性」みたいなことを序章でも書いてましたからねえ・・・
確かに「指輪物語」の脇役たちにもそれぞれに英雄性はありますが、それを前面に押し出されるとなんだか違和感があるんですよね。うーん。
まあ、もう少し、せめてメリーの章を読み終わってから判断したいと思いますが。この後は映画と原作の比較に入るようなので・・・











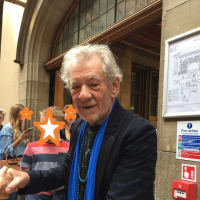



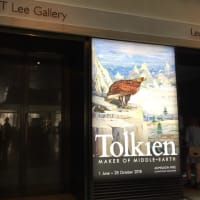




私は今、日本語版の「指輪物語」を読み返してます。英語なんて学生時代赤点を取ったくらいなので、ハナから原文で読む気も起きませんが、英語原作を読まれる方々は心底スゴいと思います。
で、ちょうど「踊る子馬亭」の場面にきてますが、黒の乗手のせいでメリーは気を失って、何時までたっても現れない彼に苛立ったピピンが「メリーのおばかさんはどこに行ったんだろう?(キミに言われたくない)」の台詞はあります。ピピンの天然ボケ振りは笑える。
改めて読んで、ビルボが去った後押しかけたロベリア夫妻への対応といい、メリーはホント、しっかり者だと思います。ピピンも確かトウック家の跡継ぎでしたよね?なのに次男か末っ子みたい。
>「ホビット庄の掃蕩」では、最初はフロドの台詞だったのが完成版ではメリーの台詞になった、という箇所が随分あるようなのですが。
あ、やっぱり!もし、フロドが指輪をもらわなければメリーのような生涯をおくったのでは、と思ってました。
桜井輪子さんのこのメリピピマンガは笑えます。
http://www.jfast1.net/~wakos/WUdata/041024.html
トゥック家ではあまり家長の教育に熱心ではなかったのか、はたまたピピンがどんな教育にも屈さない奔放な精神の持ち主なのか・・・(笑)
ピピンのガンダルフへの命知らずな暴言の数々は、まさにピピンにしか言えないですよね!(笑)メリーとは逆の意味で育ちの良さを感じるような気もしますが(笑)
(桜井輪子さんのマンガの「原作ママ」という注釈がすごくウケました(笑))
「ホビット庄の掃蕩」では、賞賛を受けるメリーやピピンやサムに対するフロドの対比をよりはっきりさせるため、フロドの戦いに積極的な台詞をメリーの台詞に変えたような気がします。
「ホビット庄の掃蕩」でのメリーとピピンはカッコイイのですが(笑)もし主人公があのように立派になってめでたしめでたし、というような話だったら、こんな深みはなかっただろうなあ、と思うと、改めてすごいなあ、と思いますね。