僕は梶井基次郎という小説家は大変好きだ。
「Kの昇天」という作品がある。水死した若い男の知人へ、その若い男と偶然海辺で知り合った「私」なる人物が思い当たる節を手紙にしたためるだけの内容である。
ここではシューベルトの「ドッペルゲンガー」(普通影法師と訳される。正確には二重人格といった意味だが、そう訳すのも何だか抵抗がある。訳すというのはやっかいだな。梶井はドッペルゲンガーとドイツ語の発音をそのまま写し取っている)が重要な役割を果たしている。
「私」が夜の海辺でKをはじめて見たとき、その不思議な行動は「私」の存在に気付かぬせいかもしれないと思い、口笛でドッペルゲンガーの旋律を吹く。
Kはそれすら聞こえていないような様子であるが、後に話を交わすようになったとき、君はさっきドッペルゲンガーを口笛で吹いていましたね、と言う。
この小説の内容とドッペルゲンガーが似つかわしいかは措いておこう。話の設定上、他の曲を持ってくるのは難しかったのだろう。
シューベルトの世界は、果てしなく深い深淵を思わせる。それに対して梶井の描くドッペルゲンガーはどこか幻想的で、それは彼の「桜の樹の下には」のような耽美的な世界と通じるものがある。「闇の絵巻」のようなものでも、ドッペルゲンガーの世界のような、そうね、僕たちに過去というものがあることへの呪いとでもいうべき、そんなものは無い。泉鏡花などから流れてくるような感じかな。「Kの昇天」の構造は漱石の「こころ」を下敷きにしているのだろうが。
例によって脱線しそうだ。梶井の作品は少ない。薄い文庫本1冊ですべてだ。関心を持った人は読んでみて欲しい。
で、僕が作品と直接関係なく興味を持ったのは、次のようなことだ。
海辺で偶然出会った2人の男が、ドッペルゲンガーという、今では音大生ですら(というか、音楽を専門にしようとするがゆえに、と言った方が正確なのかもしれない)声楽科以外は知らない曲を共通して認識していたということだ。
この共通認識無くしては「Kの昇天」は成り立たない。もちろん、この小説自体が、当時の文学愛好者たちへ向かって書かれたものだ。ドッペルゲンガーが一般に知れ渡っていたはずもない。それでも、文学を志す人たちの間では、知っていて当然、というに近かったことをうかがわせる。
彫刻家の高田博厚さんが音楽について書いたものによれば、音楽は文学志望の青年達のあいだで盛んに聴かれるようになった。片山敏彦という仏文学者(ロマン・ロランの作品など、翻訳家として名を残した)の安アパートで、若い芸術志望者たちが、蓄音機!から流れるベートーヴェンの作品に心躍らされている様子が記されている。
ここではすでに「喇叭」の時代は過去のものとなり、鳴っているものはベートーヴェンである。夜更け、若い青年達がひとつの蓄音機から流れ出る音楽に耳を傾ける様を想像してみて欲しい。
日本には音楽の歴史こそないかもしれないが、こうした「共同体験」とでもいうものがあった。それを、はるか時代を経た僕は羨ましい気持ちで眺める。
「Kの昇天」はそんな情景を背後に持つことを知らないと、あまり理解しにくい世界なのだ。
梶井も、親しかった三好達治らと、そのようにして音楽に接し始めたのに違いない。小林秀雄、河上徹太郎、青山二郎らのグループも同様だ。










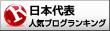

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます