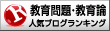僕は絵の鑑賞において本物志向が薄い人間である。昔から、絵画展で満員電車の思いをするよりは家で茶をすすりながら好きな画集を眺めているほうが好きであった。いいなあという気持ちだけは本物なのである。
できることならば美術館で見たいという気持ちくらいはあるのだ。常設展などは行く。山梨県に白樺派の人たちゆかりの清春美術館という小さな美術館がある。ここには今も木工をする人たちの工房があったりする。小さな礼拝堂がありルオーの作品が取り囲んで架けられている。そのような小さいところで見るルオーは落ち着いていてよい。
でも正直に考えれば僕の眼なぞ知れているわけだから、本物を見たところで何かが違って見えるわけではあるまい。ずっとそう思ってきた。好きな画家は画集で見たって好きだと思ってきた。それは今でもその通りだと思う。
ただひとりだけ、本物を見て好きになった、いやそれどころか心底感心してしまった例外がいる。ピーター・ブリューゲルである。この人の絵を画集の小さな写真で見ていたころは、決して好きな画家とはいえなかった。
素朴な画家たちというのが流行った時期があって、それらの画家は素人くさい描きかたで細かく人物や風景を描きこんである。素人くさくどころか、正真正銘の素人や素人に毛が生えたようなのが好まれたのではなかったか。
それらのさきがけのような印象を持ってしまってそれ以上見ようともしていなかった。ゴッホが手紙の中で何べんもブリューゲルに言及しているのは当然読んでいたのだが。農民を描いたと言われたってそれが何さ、といった感じ。農民を描けというのなら僕だって描いてやるわい。下手だけどね。下手でいいんだろう?そんな気持ちが少しあった。
初めてウィーンの美術館で期せずしてブリューゲルを見たときびっくりした。まずその色彩の美しさ。
どう言おうか。パッと遠目に見たときの印象は、どんな絵でも一種の模様でしょう。その色調が落ち着いているのに鮮やかなのだ。
僕は古いペルシャ絨毯が好きだが、それはシルクではいけない。絶対にウールでなければ深みのある色彩は出ない。
なんだかそんなことを思い出させる目触り?感だ。ルーベンスのような鮮やかな色もなく、レンブラントのようなずっしりと心に響き渡るような重みでもない。何ともいえず心地よい落ち着き。
近くに寄ってみると、また本当に細かいところまで描き込んでいて、それにもびっくりする。
最も評価の高い(と思われる)「冬」の画面左手では女たちが焚き火をしている。左上方に吹き上がる火は、火の粉の音まで聞こえてきそうだ。北風の痛さも感じるようだ。
凍った池では大勢の人がスケートを楽しんでいる。狩人たちは今ようやく日常の風景を取り戻したのだ。いったい何人が描かれているのだろう、今度数えてみよう。
数えてみるで思い出したが、カラスもたくさん描かれている。これがじつに効果的である。冷たい風や張り詰めた空気を伝えている。うまいとしか言いようがない。
葉っぱが一枚もない枯れ木(実際は枯れていないのだろうが)も画面を分ける働きをしているだけではなく、村という存在を強調しているように思える。
もうひとつ、犬好きな僕が思わず笑ってしまうのが、左手前にいる犬の群れ中一番端にいる猟犬である。しゃがんで用を足しているのだ。その背中の曲がり具合といい、首の角度といい、よく見ているというのか、犬たちと狩人の関係までが見て取れる。
ブリューゲル自身も犬が好きだったに違いない。ユーモラスで、しかも心打たれる。
できることならば美術館で見たいという気持ちくらいはあるのだ。常設展などは行く。山梨県に白樺派の人たちゆかりの清春美術館という小さな美術館がある。ここには今も木工をする人たちの工房があったりする。小さな礼拝堂がありルオーの作品が取り囲んで架けられている。そのような小さいところで見るルオーは落ち着いていてよい。
でも正直に考えれば僕の眼なぞ知れているわけだから、本物を見たところで何かが違って見えるわけではあるまい。ずっとそう思ってきた。好きな画家は画集で見たって好きだと思ってきた。それは今でもその通りだと思う。
ただひとりだけ、本物を見て好きになった、いやそれどころか心底感心してしまった例外がいる。ピーター・ブリューゲルである。この人の絵を画集の小さな写真で見ていたころは、決して好きな画家とはいえなかった。
素朴な画家たちというのが流行った時期があって、それらの画家は素人くさい描きかたで細かく人物や風景を描きこんである。素人くさくどころか、正真正銘の素人や素人に毛が生えたようなのが好まれたのではなかったか。
それらのさきがけのような印象を持ってしまってそれ以上見ようともしていなかった。ゴッホが手紙の中で何べんもブリューゲルに言及しているのは当然読んでいたのだが。農民を描いたと言われたってそれが何さ、といった感じ。農民を描けというのなら僕だって描いてやるわい。下手だけどね。下手でいいんだろう?そんな気持ちが少しあった。
初めてウィーンの美術館で期せずしてブリューゲルを見たときびっくりした。まずその色彩の美しさ。
どう言おうか。パッと遠目に見たときの印象は、どんな絵でも一種の模様でしょう。その色調が落ち着いているのに鮮やかなのだ。
僕は古いペルシャ絨毯が好きだが、それはシルクではいけない。絶対にウールでなければ深みのある色彩は出ない。
なんだかそんなことを思い出させる目触り?感だ。ルーベンスのような鮮やかな色もなく、レンブラントのようなずっしりと心に響き渡るような重みでもない。何ともいえず心地よい落ち着き。
近くに寄ってみると、また本当に細かいところまで描き込んでいて、それにもびっくりする。
最も評価の高い(と思われる)「冬」の画面左手では女たちが焚き火をしている。左上方に吹き上がる火は、火の粉の音まで聞こえてきそうだ。北風の痛さも感じるようだ。
凍った池では大勢の人がスケートを楽しんでいる。狩人たちは今ようやく日常の風景を取り戻したのだ。いったい何人が描かれているのだろう、今度数えてみよう。
数えてみるで思い出したが、カラスもたくさん描かれている。これがじつに効果的である。冷たい風や張り詰めた空気を伝えている。うまいとしか言いようがない。
葉っぱが一枚もない枯れ木(実際は枯れていないのだろうが)も画面を分ける働きをしているだけではなく、村という存在を強調しているように思える。
もうひとつ、犬好きな僕が思わず笑ってしまうのが、左手前にいる犬の群れ中一番端にいる猟犬である。しゃがんで用を足しているのだ。その背中の曲がり具合といい、首の角度といい、よく見ているというのか、犬たちと狩人の関係までが見て取れる。
ブリューゲル自身も犬が好きだったに違いない。ユーモラスで、しかも心打たれる。