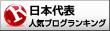先日反エコロジーについての本を紹介した折り、抗議のコメントがあった。
僕がエコ派と反エコ派の双方を(たとえばテレビで)徹底的に紹介させたら良かろう、さもないと僕らには何が正しいか分からない、といった趣旨の文を書いたところ、そういう人任せの態度が悪い、自分で調べろ、たとえばこんなサイトだ、とURL を貼り付けてあった。
実は僕は全く同じコメントを他のサイトで見ていた。エコロジー運動に疑問符を投げかけていると思われるサイトにコメントをしてあるく人なのかもしれない。
違うのは僕がテレビで討論でもしてくれたら有り難い旨を書いたことに対して言及していたことくらいかな。
内容自体は当然だと思われるのでそのままにしておいた。
で、紹介してもらったサイトを覗いてみた。僕が知らないサイトもあったが、すでに大方の見方は承知しているものだった。
「偽善エコロジー」の著者が様々なデータを歪曲していると公開質問状を出した機関もあったようである。
問題はその先にあるのだと僕は言いたいのだ。
著者はこの公開質問状に答える義務を負う。当然のことである。
仮にデータを恣意的に改竄してあるのならばそれは明らかにすべきだ。
コメントで自分で調べろと言い残していった人は、こうした経緯や事情について詳しいのだろう。また自分で調べろというのはこれらの事情をきちんと把握してくれということなのだろう。
しかし元のデータそのものの信頼度となると話は急にややこしくなる。どんな場合でも正確に客観的なものはない、データを集める際に自分の立場や意見に合致した数値を挙げるのはエコロジー運動に限ったことではあるまい。
本当に僕が知るためにはあらゆるデータを解析する能力だけでは足りない。化学物質の性質から地質学、林業などへの理解等、万能の神さながらの智を持つ必要がある。
そんなことを要求されたら地上の誰一人口を開くことが許されないだろう。僕が著者を盲信するのも敵視するのも危険だろう、できれば(テーマの性質上)継続して且つ簡単に人目に触れるところで論議をしてもらいたいというのはそういう意味である。
著者が昔勤務していた会社寄りの本を出したなどと、反論する人たちはそんな詰まらぬというか根も葉もない、証明不可能なこと、それもプライベートなことを持ち出すのはかえって説得力がなくなるのだと知ることだ。
また、僕が(怠け者のね)みた限りにおいて、武田氏の書いたすべての項目に対して反論がなされているわけではない。たとえば家庭で生ごみを肥料にするのは危険だという意見。今や食品にはどのような添加物が混入されているか分からず、うっかり重金属の類を一緒に捨てる過ちを犯さないとも限らない。それを土に返すことを繰り返せば残留する有害物質の濃度は増す、という指摘はよく吟味する必要があるだろう。
といって武田氏の書いたすべての項目に僕が頷いたのでもない。ただ「エコロジー」というよい響きに心動かされる一方ではいけないぞと自戒の念を抱いたのだ。
コメント氏は自らを「理系」人間と認める人のようだったが、その一方的な感情の発露は、現代東アジア系ピアニスト顔負けであった。「理系」の人間はなかなか感情豊かなようである。
まあ公平に見て、人間はこんなものだというところ。憤りに駆られているときに理系の憤慨も文系の憤慨もありはしない。
そもそもコメント氏が紹介してくれたのは、武田氏のデータは嘘であるという調子の論難、もしくは武田氏が間違いだと主張するデータだったりして、それを読んだだけで納得するのは不可能であった。前述のように僕には(たぶん大抵の人には)それらを正確に解析する力はなさそうだから。
こうやって僕たちがあらゆるデータとやらを把握し尽くすことが不可能である以上、テレビで繰り返し討論をしてほしいという僕の真意はそんなにばからしいものでもあるまいと思われる。
せっかく公開質問上が出たのであるから、武田氏の正式な回答は文書で公開するとして、ぜひ真面目に諸見解について討論してもらいたいと改めて思った。
何といっても次々にでる学術的な本を書う人は少ないだろうと思うから。
むかしロッキード事件で全日空の社長だったかな、国会証人喚問が中継された。その時の社長の動揺ぶりが余りに激しくて、それ以後証人喚問の中継は禁止されたと記憶している。
人間がどのように話すか、その時の身振り、顔つき、すべてを総合して僕たちは「判断」するのである。この時ほど映像の「魅力」を実感したことはなかった。
すでに書いたように、このテーマはある立場や意見の問題ではない。僕たちの日常に大いに関わっていることだ。なるべく多くの人の目に触れることが大切だろう。
このような話題に関しては、あらゆる専門家が専門知識を動員して調べあげたものを、専門外の僕たちの前できちんと示し、論駁しあうのはむしろ義務といっても差し支えないだろう。
僕は科学的なこと及び統計学上のことについては素人だが、生活人としての権利くらいは持ち合わせている。もちろんこれを読むあなたも。
僕がエコ派と反エコ派の双方を(たとえばテレビで)徹底的に紹介させたら良かろう、さもないと僕らには何が正しいか分からない、といった趣旨の文を書いたところ、そういう人任せの態度が悪い、自分で調べろ、たとえばこんなサイトだ、とURL を貼り付けてあった。
実は僕は全く同じコメントを他のサイトで見ていた。エコロジー運動に疑問符を投げかけていると思われるサイトにコメントをしてあるく人なのかもしれない。
違うのは僕がテレビで討論でもしてくれたら有り難い旨を書いたことに対して言及していたことくらいかな。
内容自体は当然だと思われるのでそのままにしておいた。
で、紹介してもらったサイトを覗いてみた。僕が知らないサイトもあったが、すでに大方の見方は承知しているものだった。
「偽善エコロジー」の著者が様々なデータを歪曲していると公開質問状を出した機関もあったようである。
問題はその先にあるのだと僕は言いたいのだ。
著者はこの公開質問状に答える義務を負う。当然のことである。
仮にデータを恣意的に改竄してあるのならばそれは明らかにすべきだ。
コメントで自分で調べろと言い残していった人は、こうした経緯や事情について詳しいのだろう。また自分で調べろというのはこれらの事情をきちんと把握してくれということなのだろう。
しかし元のデータそのものの信頼度となると話は急にややこしくなる。どんな場合でも正確に客観的なものはない、データを集める際に自分の立場や意見に合致した数値を挙げるのはエコロジー運動に限ったことではあるまい。
本当に僕が知るためにはあらゆるデータを解析する能力だけでは足りない。化学物質の性質から地質学、林業などへの理解等、万能の神さながらの智を持つ必要がある。
そんなことを要求されたら地上の誰一人口を開くことが許されないだろう。僕が著者を盲信するのも敵視するのも危険だろう、できれば(テーマの性質上)継続して且つ簡単に人目に触れるところで論議をしてもらいたいというのはそういう意味である。
著者が昔勤務していた会社寄りの本を出したなどと、反論する人たちはそんな詰まらぬというか根も葉もない、証明不可能なこと、それもプライベートなことを持ち出すのはかえって説得力がなくなるのだと知ることだ。
また、僕が(怠け者のね)みた限りにおいて、武田氏の書いたすべての項目に対して反論がなされているわけではない。たとえば家庭で生ごみを肥料にするのは危険だという意見。今や食品にはどのような添加物が混入されているか分からず、うっかり重金属の類を一緒に捨てる過ちを犯さないとも限らない。それを土に返すことを繰り返せば残留する有害物質の濃度は増す、という指摘はよく吟味する必要があるだろう。
といって武田氏の書いたすべての項目に僕が頷いたのでもない。ただ「エコロジー」というよい響きに心動かされる一方ではいけないぞと自戒の念を抱いたのだ。
コメント氏は自らを「理系」人間と認める人のようだったが、その一方的な感情の発露は、現代東アジア系ピアニスト顔負けであった。「理系」の人間はなかなか感情豊かなようである。
まあ公平に見て、人間はこんなものだというところ。憤りに駆られているときに理系の憤慨も文系の憤慨もありはしない。
そもそもコメント氏が紹介してくれたのは、武田氏のデータは嘘であるという調子の論難、もしくは武田氏が間違いだと主張するデータだったりして、それを読んだだけで納得するのは不可能であった。前述のように僕には(たぶん大抵の人には)それらを正確に解析する力はなさそうだから。
こうやって僕たちがあらゆるデータとやらを把握し尽くすことが不可能である以上、テレビで繰り返し討論をしてほしいという僕の真意はそんなにばからしいものでもあるまいと思われる。
せっかく公開質問上が出たのであるから、武田氏の正式な回答は文書で公開するとして、ぜひ真面目に諸見解について討論してもらいたいと改めて思った。
何といっても次々にでる学術的な本を書う人は少ないだろうと思うから。
むかしロッキード事件で全日空の社長だったかな、国会証人喚問が中継された。その時の社長の動揺ぶりが余りに激しくて、それ以後証人喚問の中継は禁止されたと記憶している。
人間がどのように話すか、その時の身振り、顔つき、すべてを総合して僕たちは「判断」するのである。この時ほど映像の「魅力」を実感したことはなかった。
すでに書いたように、このテーマはある立場や意見の問題ではない。僕たちの日常に大いに関わっていることだ。なるべく多くの人の目に触れることが大切だろう。
このような話題に関しては、あらゆる専門家が専門知識を動員して調べあげたものを、専門外の僕たちの前できちんと示し、論駁しあうのはむしろ義務といっても差し支えないだろう。
僕は科学的なこと及び統計学上のことについては素人だが、生活人としての権利くらいは持ち合わせている。もちろんこれを読むあなたも。