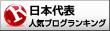https://youtu.be/7Wpn4MoC7wE
このピアニストは懐かしい。
僕の学生時代、学内で公開レッスンがあった。その時大変良い印象を受けたのだ。
後に武蔵野音大で教鞭をとっている旨を知った。武蔵野音大関係者は多大な影響を受けたのではあるまいか。
エドウィン・フィッシャーに学んだと知ったのもこの頃ではなかったろうか。
ハンゼンもフィッシャーのアシスタントをつとめていたから覚えていた。夢見るような若者だったという。今回知ったが、彼はハンガリー人でドイツに行く前はバルトークに師事したのだそうだ。
僕は帰国後も武蔵野音大での演奏会に足を運んだものである。生徒にも勧めて何人かが行き、その1人がこの映像を見つけてくれた。
武蔵野音大にはもしかしたら映像などが残っているのではあるまいか。この様な時代になったのだから有ればアップロードしてくれたらありがたいのだが。