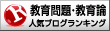僕の名前はヤン坊、じゃなかった、しげまつで、ローマ字で書くとShigematsuになる。もう何十年もそう書いている。
ドイツで暮らしていた時分、親しいドイツ人たちから尋ねられたものである。君はなぜ自分の名前を、書き記した通りに発音しないのだ、と。
いやぁ、これには困ったね。だって僕の名前は僕が知っているとばかり思っていたからな。そうか、僕は自分の名前を知らなかったのか。目から鱗どころか、眼が落ちてしまった。
仕方なく、ではどう発音るれば良いのさ、と訊き返す。するとスィゲマツーと記す以外なさそうな発音を教えてくれる。ツーは思い切り口をとんがらせて、アクセントもここにある。
うーむ、そうだったのか。僕の名前はスィゲマツーなのか。それ以来僕は電話に出て名乗ることが苦手になってしまった。
時折生徒や家族から冷やかされる。電話に出るとススススィゲマツです、と名乗るのできっと相手はビックリしているだろうと。
きっと僕の脳内では受話器を取り上げた瞬間、あらゆる神経が超高速で自分の名前を求めて空回りを始めるのだ。
ドイツの友達の頑迷さを時折懐かしく思い出す。
ドイツで暮らしていた時分、親しいドイツ人たちから尋ねられたものである。君はなぜ自分の名前を、書き記した通りに発音しないのだ、と。
いやぁ、これには困ったね。だって僕の名前は僕が知っているとばかり思っていたからな。そうか、僕は自分の名前を知らなかったのか。目から鱗どころか、眼が落ちてしまった。
仕方なく、ではどう発音るれば良いのさ、と訊き返す。するとスィゲマツーと記す以外なさそうな発音を教えてくれる。ツーは思い切り口をとんがらせて、アクセントもここにある。
うーむ、そうだったのか。僕の名前はスィゲマツーなのか。それ以来僕は電話に出て名乗ることが苦手になってしまった。
時折生徒や家族から冷やかされる。電話に出るとススススィゲマツです、と名乗るのできっと相手はビックリしているだろうと。
きっと僕の脳内では受話器を取り上げた瞬間、あらゆる神経が超高速で自分の名前を求めて空回りを始めるのだ。
ドイツの友達の頑迷さを時折懐かしく思い出す。