今回の記事は、主にこれから企業に就職を希望している人に向けてです。
春らしくなって、丸の内やビジネス街ではネイビー・ブルー(女性の場合はなぜかみんな黒)のスーツで身を固めた就職希望者が闊歩しています。ウン十年前の自分の姿と重ねあわせて、単純に「若いっていいな~。」と無条件で応援したくなります。
そのような就職希望者の皆さんの中に、履歴書に「英検1級」とか「TOEIC 950点」とか書ければ有利になるのではないか、と考えている人もいるのではないでしょうか?
長いサラリーマン生活から、少し採用に携わったことのある僕の、企業側からの論理で言えば、そんなものは(仮にもっと難易度が高いと言われる弁護士や会計士の資格があったとしても)”参考”程度です。
”参考”程度とはどういうことかというと、一つは足切りです。昨今の不況で、一般に言われる人気企業ではわずかの募集人数に何千、何万という応募者が殺到します。企業にも余裕があったころは、一人採用するにあたり、200万円~300万円の費用をかけられましたが、いまはそんな余裕はどの企業にもありません。面接人数を最初から絞るために、てっとり早くTOEICのスコアを足切りに使おうというわけです。人気企業(僕は世間で言われる人気企業がその人にあった”最適企業”とは思いませんが)では、どの企業も公にしていませんが、その足切りラインは800点前後だと思われます。(単なる足切り、にしては年々水準は上がっていますが。)
次に、足切り後にいよいよ面接ということになって履歴書に「英検1級」や「TOEIC 950点」と書き、応募者が「英語が出来ます。」というと必ずその英語で「何をしたのか?」必ず聞かれます。(面接官のマニュアルのようなものです。)
応募者「英語はかなり出来ます。」
面接官「履歴書に「英検1級」とあり、そこそこ英語が出来るのはわかりましたが、
それで何をしましたか?」
応募者「・・・・・」
と、その時点で詰まれば、そこでアウトです。(もちろん形だけの面接は続きますが。)
応募者「日本では餓死する人はいませんが、広く世界を見渡せば、飢餓線上にいる人は地球全体の人口の3分の1に達します。僕も何か出来ることはないかと考え、NPO組織を立ち上げ、英語がある程度できるので、ケニアに飛んで、ケニアを拠点にアフリカ諸国10か国に、3か月間10歳未満の児童を中心に食糧支援活動を行いました。」(NPOには限りませんが)このように答える人は企業側から見れば”買い”です。なぜならば、自分なりの着想があり、自分の得意技を生かして、実際に行動した、ということがわかるからです。
もちろん、応募者「日本語と同じぐらいの精度で英語に翻訳(通訳)することが出来ます。」というのも、それが出来る人が非常に限られているので、“売り”かもしれません。確かに一昔前は、企業には法務部や特許部などといったところにそういうセクションがあり、揶揄を込めて「英語屋」といわれる人がいました。しかし、今ではみなアウトソーシングしています。恒常的に人員をかかえるより、その都度アウトソーシングする方がずっと経費が安くつくからです。
また、単に「英語屋」がほしいのならば、昨今は帰国子女が日本にもあふれているので、帰国子女を採用すれば済むだけです。(ただ、帰国子女の中には日本語が出来なくなり、翻訳出来ない人もいますが。)
TOEICを運営するIIBC(国際ビジネスコミュニケーション協会)も英検を運営する日本英語検定協会も旺文社ももちろん営利団体、早い話が金儲けをしなければ存続出来ません。またそれを取り囲む英語教育業界もほとんどが営利団体(金儲け団体)です。
金儲けは全く否定しません。が、僕は人の命を救う医業と人を創る教育(英語教育も含め)と人の心を救済する宗教は、金儲けとは切り離さなければならない、と考えていますが、日本はその3つとも(まっとうな対価ならいいのですが、不当に高価な)金儲けの手段になっている、世界でも珍しい国です。(もちろん、まれに”赤ひげ先生”のような医者もいますが。)
TOEICや英検やそれを取り巻く英語業界は、金儲けをしなければならないので、おもな財源の受験者数、付髄出版物の売上を伸ばさなければならないので、「こういった人気企業ではTOEICのスコアをこんなに重視している。」とか「英検1級があればこんなに就職(転職)に有利。」とか色々書いています。有名企業の就職=高収入という日本人が好きなメンタリティーにつけこんだものですが、これは営利団体が自分の事業を悪くいうはずもなく、当然のことです。(コマーシャルと考えて下さい。)また、それに便乗したいわいるTOEIC産業もしかり、です。
実社会の経験が浅い若い人たちはそういった情報に振り回されやすいですが、現実の企業の立場では、”参考”程度です。いいかえれば、How ではなく、What、どれだけ英語が出来るかではなく、英語で何をしたのか、あるいは出来るのか、あるいは何をしたいのかを十分に考えて頂きたいと思います。
僕の場合は、英検1級やTOEIC 950点すら持っていませんが、すでに企業の中で毎日英語が必要とされる仕事についており(ただし英語はあくまでも手段です。)今後英検1級、TOEIC 950点をクリアーしても年収も1円も上がりませんし、これ以上役職も上がりません。(つまり収入には全く関係ないということ。)
なぜ受けるかというと、前にも書きましたが、英語の必要な部署であり、日本でなにもしないと英語力はどんどん落ちますが、生来怠け者なので、なにかシバリを入れないと絶対に勉強しない、ということと、そもそも英語(というか異文化との遭遇)が好きということ、(好きに論理的な理由はありません。)最後に英検1級でもあればカッコイイんじゃない、というTOEIC、英検を逆手にとって自慢したいという下心だけです。(書いちゃった!)
企業における英検やTOEICのポジション・見方とはその程度のものです。
これから企業に入る若い人には、もし英検1級やTOEIC 950点以上あれば、帰国子女でなければ、その努力は買いますが、オールマイティなどと思わず、ぜひ英語で何をしたのか、何が出来るのか、今後何が出来る可能性があるのか、を深めて頂きたく。イチローがアメリカで高額の収入を得ているのは英語が出来るからではなく(アメリカ人はみんな英語が出来ます。)、世界でも通用する超一流の野球技術があり、それを維持するために努力しているからです。
また、広い世の中には英語の研究そのものを目的とする言語学者や翻訳者、通訳者という職業もあり、その場合にはHow とWhat、すなわち目的と手段が一致する場合もありますが、その場合には、TOEIC 950点や英検1級程度の限定的な力ではおそらく生活していけないでしょう。また翻訳者や通訳者のプロになるためにはむしろ相当の日本語力、日本歴史、文化、思想の勉強が必要になります。



















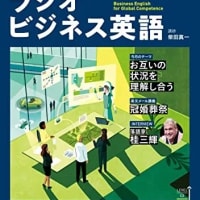





みい子さんのところからたどって参りました。
企業で採用を担当したことがありますが、各種資格に対する見方はだいたいこちらの記事に書いてあるとおりだと思います。
判断材料というよりは、その応募者の行動・思考パターンを探る話題として使うように思います。
こう考えて→こうしてみたら→こうなった
というパターンを観察して、それが企業で働くときも再現されるのではないかという仮説ですね。
Shira さん
ご指摘の通りです。TOEIC,英検ともまず設問があり、合否やスコアをだすために、正解、不正解が明確に決まっています。高得点を挙げることは意味のないことではありませんし、かつてのバブル期までの企業では短時間に大量に間違いなく処理し、正解を出す人が評価もされてきました。僕はその世代の人間です。
しかし、どのような企業でも昨今の一瞬先もまっくら、という状況では、ようやく企業側もその能力だけでは立ちいかないと重い腰を上げ始めました。(企業内部にいる僕からみれば経済情勢などの外圧から変わらざるをえなかった、というのが実態で自主的にではないので、まだまだ端緒についたばかり、という感じですが。)
具体的には、問題を解いて正解に到達する能力よりも、問題(課題と言い換えてもよいと思います。)すら与えられない状況の中で、課題を自ら作り出し、その課題を自分で徹底的に考えぬき、仮設を立てて、仮設実行出来る、という能力に重きを置かれるようになってきた、ということです。
したがって100点か50点か、正解か不正解か、という絶対的な尺度で評価するのではありません。(評価は簡単ではなく、面接官の力量が問われます。)
自らどのように問題意識を持ち、どのように考え、どう行動したか?のプロセスを自分の言葉で自分のエピソードを語れる人は、企業側から見て以前にもまして、魅力的になっています。これはどんな就活対策本にも書いてあるような陳腐なことかもしれませんが、就職活動だけでなく、これから社会に出る若い人には必ず必要となる視点ですので、アチーブメントテストも意味がないわけではありませんんが、こちらのプロセスの方も時間がある若い間に磨いておいて下さい、ということです。
米国、欧州の大学以上の高等教育では、従来よりその思考プロセスに重点が置かれていますので、なにも欧米が全ていいわけではありませんが、この様な先行き不透明な時代では、高等教育だけに限れば(ピンからキリまでありますが)ブレークスルーを生み出す力がありそうで、日本よりは先行していると思います。(まったりとブログを書いていますので、その辺の事情はおいおいブログの記事にも書いていきます。)