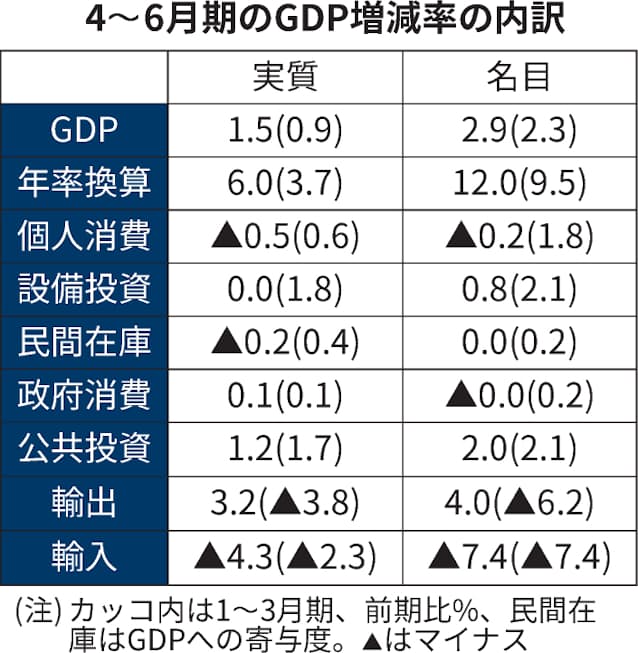人口が中国をぬいてインドが世界一、中国のGDPが3.5%と目標の5%を大きく下回るというニュースが流れた。それだから中国よサヨナラ、インドよコンニチワというわけではない。
経済発展での話だ。インドのGDPは昨年からかつて宗主国であった英国を追い抜くと言うことが英国では言われてきて、実際そうなった。グローバル化の時代、自国の企業だけでなく世界の企業から如何に多くの投資を呼び込むかによって経済の発展が決まる。中国は開放政策により、米国、ドイツ、日本の企業を呼び込み世界第3位の大国にのし上がった。サプライチェーンでコロナ下いかに中国が大きな地位を占めていることが判った。
ところが習近平1強体制になり、企業への干渉が激しくなり、ゼロコロナ政策でその凄まじさが明確になった。また最近ではビザの発給停止といった経済活動を規制するような手段をとるということまで始めた。これでは中国への投資はリスクが大きすぎる。村田製作所やパナソニックが中国への新規投資をすると発表しているが、考え直さざるを得ないだろう。
一方、2018年9月、インド政府は、電気通信セクターへのFDI(海外直接投資)流入を2022年までに1000億米ドル(約10兆3800億円)に増やすことを想定した、2018年国家デジタル通信政策を発表している。新興市場プライベートエクイティ協会(EMPEA)が実施した最近の市場魅力度調査によると、インドは2019年から2020年にかけて、グローバルパートナー(GP)投資にとって最も魅力的な新興市場だという。インドで長い投資歴を持つスズキ自動車だけでなく、ソフトバンクグループは、2022年までにインドで100億ドル(約1兆829億円)を投資すると発表している。中国で苦労しているアップルもインドをサプライチェーンの一環とすることを発表している。