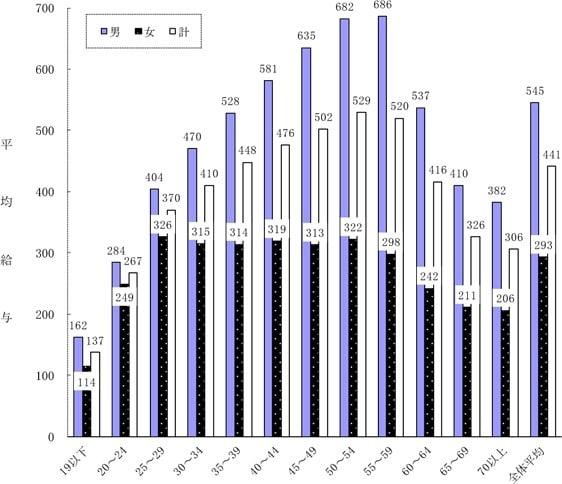就活や投資の参考になるホワイト企業リスト
何回かこのブログで、世界でも不思議、日本の有休取得率最低!!、アジアを見ても有給は100%取得することが当然なのに。この2019年4月から、年次有給休暇が10日以上付与される労働者......
昨年は有給休暇の取得率からホワイト企業をとりあげたが、今年はもっと広く「働き方改革」の視点からネットで評判の企業リストが提供されている。就職・転職のための口コミサイトを運営するオープンワークという企業があり、各企業の評判がここで良きにつけ悪しきにつけ掲載されている。ネットのおかげで運営できる広告企業だ。
オープンワークは昨年末、「令和の働き方企業ランキング」を発表した。口コミサイトに投稿された社員のコメントの中から、「風通しの良さ」「待遇の満足度」「有休消化率」の3ポイントに絞ってランク付けをしている。
ベストテンは1位「グーグル」、2位コンサルティング会社の「A.T.カーニー」でフラットな組織で風通しが良いことを挙げている。3位は、ソフトウェアなどを販売している「アシスト」で有給やリフレッシュ休暇のとりやすさを挙げている。4位は「サントリーホールディングス」5位「旭化成」と伝統的企業が登場。6位「シスコシステムズ」7位なじみのない油田探査「シュルンベルジェ」と外資系企業が続く、8位はなんと「特許庁」霞が関というと不夜城と言われ、残業のメッカと思っていたが役所でも改革は進んでるところもある。以下リクルート、三井不動産、アップルで、製造業は分が悪い。米国だけでなく日本もこのままだと人材が集まらず製造業の劣化が進みそうだ。
処遇面ではグーグルが断トツで、「給与制度は30代前半で約1900万円。その他に年間100万円の自己学習支援なども存在し、語学や資格取得に活用可能。家賃の給与天引きプログラムや三食の食事、カフェ、ジムなどの福利厚生も手厚いので、感覚的には年収より数百万円以上のインパクトがある」と広告取りでかなり稼ぐ。寡占企業のおかげでこの処遇は例外中の例外だろう。