人間は理性の動物ではなく、感性の動物である。人様々な感性を個性という。戦国時代に天下の覇者を目指した3武将の個性は、よく知られているように人とホトトギスの関係で次のように言われている。、
「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」 徳川家康
「泣かぬなら鳴かせてみせようホトトギス」 豊臣秀吉
「鳴かぬなら殺してしまえホトトギス」 織田信長
これは人の個性の違いを人と生物との関係を例にして言っているが、人は生物に対して「愛護」を語るが、「尊厳」は語らない。一般に生物に対しては上から目線なので、気に入らないホトトギスは殺してしまえ、と言われてもギョッとはしない。一方、ドイツ憲法やEU憲法では「人間の尊厳」を柱にしているが、日本人は仏さまに尊厳は感じても、他者に尊厳を感じることは普通はない。日本の憲法では天皇は国民の象徴とされているが、「日本の尊厳」としてきた長い歴史がある。
「人間の尊厳」が世界の常識となるのは何時のことであろう。
「自然と人、人と人」の関係を考えることを、このブログの中心課題としているが、人間も生物の一員であり、生まれつきの感性の違いと、生きてきた様々な環境において、何を感じ、何を大切にするかの違いが、判断や行動に大きく作用している。人は誰も「犬」を識別できるが、他の動物も言葉は持たないが、人間を識別しているはずだ。理性は画像処理により身についたもので、画像処理とは人間でも動物でも神経細胞の結合による論理的な作業である。この論理的な作業はAIで各分野で進められている。スピードは人間より早く、多くの情報を処理できるであろうが、判断に必要な情報が確かに集められているかどうかは、これを使う人間の責任だ。
また、画像処理は連続し、次の画像により情報は変化していくはずだが、処理により得られた情報は慣性の法則のように、残像になったり無意識から意識に変換されて残っている。心でモノを見るとは、無意識の世界から意識を作る作業であり、画像から意識になるまでの神経回路の生成は無限なので、出来上がった回路の知識からモノを見るのではなく、心で見ることも大切だ。また、画像の変化に心身の反応する速度には個人差と年齢差があり、スポーツの能力や高齢者のボケにも関係しているのだろう。
いずれにしても、個人、組織、国の判断と行動は人間の責任だが、これを支配するトップの考え方と行動で、歴史は大きく変わる。
徳川家康,(2),(3),(4)については、いろいろ紹介されている。信長からはヒットラーを連想するが、彼はある意味ではヨーロッパに憧れる流通型の大名だった。信長、秀吉は楽市・楽座で知られているように、彼らの時代が続くと流通型の日本となっていただろう。しかし、「地方ごとに農業を盛んにし、領国を富ませていくべきだ」とする家康が天下を取った。それが260年も続いたので、江戸時代の徳川政権が今の日本を造ったと言えよう。「鎌倉時代の武士は農業で生計をたてていた」と言われるように、武士だけでは生活できない。江戸時代も武士だけでは生活できないので、副業として、寺子屋の先生、剣術道場の師範と農業は許されていたが、武士が絶対やってはいけなかったのは「商い」だったそうだ。
信長は足利義昭を第15代征夷大将軍に奉じて、全国統一を目指し、室町幕府に代わって支配をする者であるという支配の正当性を求め、「本能寺の変」で倒れた。何故、明智光秀は謀反を起こしたのか?
まだ定説はないが、光秀は文化人でもあり室町幕府という伝統を愛し、信長に従属しただけでなく、足利義昭を守り戦ったこともある。日本の伝統を破壊する信長を、義昭の「鞆幕府」と繋がり倒した可能性を私は支持したい。倒すことが第一で、そのチャンスを重視し、次に何をするかが目的ではなかったように見える。
家康も1566年、朝廷から従五位下三河守に叙任され、同時に「徳川」に改姓している。源氏の出ではない家康も「支配の正当性」を求め、権威が必要だったのだろう。秀吉は「関白」となったが、家康は朝廷ともつながり「征夷大将軍」の地位に就いた。「征夷」は、蝦夷を征討するという意味で、日本は狭い国土の為か、飛鳥時代から他者の排除の意識が強かったようだ。
政権を維持するためには、「下克上」を防止しなければならない。「鳴くまで待とう」の家康には、その資質はあった。さらに徳川政権を揺るぎないものにするために、3代将軍家光は「参勤交代」を始め、藩との主従関係を強固なものにした。
江戸幕府は農業を重視した政権であったが、政権は何時の時代でも長く続けば財政危機に陥る。 幕府は発足当初の理念や、それを支えた制度や既得権益を守ろうとした。江戸中期の老中田沼意次は、悪化する幕府の財政赤字を食い止めるべく、重商主義政策を採ったが、時代に生きる人達に受け入れられず失脚した。しかし、幕末になると攘夷のために武器を購入し、財政難に陥る藩も多く出た。
徳川御三卿の一つ第8代将軍徳川吉宗の血統である「田安徳川家」に生まれ、後に福井藩主となる松平春嶽は、身分に関係なく有能な藩士を登用し藩政の力とした。松平春嶽が登用した橋本佐内の意見により、攘夷論から開国論に考えも変え、将軍継嗣問題で一橋派を幕末の四賢侯を中心にして動かした。橋本佐内は若き藩医にして英語やドイツ語を独学で習得し、幕末の政治に関わり西郷隆盛や坂本龍馬の考え方にも大きな影響を与えた。まさに橋本佐内が福井藩主(トップ)の下で幕末を動かした。橋本佐内も松平春嶽も維新側でなかったので、名を残していないが、「安政の大獄」で26歳にして斬首の極刑を受けたことは幕末を動かした中心的人物であった証明であろう。また、福井藩も幕末の軍事費が藩財政に大赤字を生んだが、松平春嶽が登用した福井藩士・油井公正(録画参照)が、開国後、藩札により農産物(生糸、お茶)を増産し、外国に輸出することで財政を回復させた。油井公正は明治維新後も政府の財政体制を確立している。
参考:英雄たちの選択「参勤交代を緩和せよ」~松平春嶽 幕政の根幹に物申す
英雄たちの選択「橋本左内~維新を先駆けた男 安政の大獄に死す」 動画
歴史秘話ヒストリア「橋本佐内と由利公正~知られざる維新の天才たち」 動画
知恵泉「みんなの心をつかむ突破力~由利公正」 動画
今、日本は明治維新150年を祝っている。明治維新を祝うとき、松平春嶽、橋本佐内、油井公正への感謝を大きく取り上げることはない。この150年、我々は未来に向かって理想を持ち、新しい理念で歩んできたであろうか。政権が長続きすると財政赤字と既得権益を守る人々が増大するのは、いつの時代、どの世界でも同じこと。日本は今、それが独裁政権となって国民を支配しようとしている。固定観念を打破し、政治に夢を取り戻そう! 参考:「長州レジーム」から日本を取り戻す!,(2)(動画)
科学は論理的であり、人間の欲望により便利な道具を開発し、我々は時代と共に人工的な世界に囲まれながら生きている。しかし、我々の原点は自然の一員であり、生物の一員であることを忘れてはいけない。人には色々考え方があるが、自然の一員として世界を見て、自然を破壊せず、自然の力を利用して生きることを第一に考えたい。それは、考え方というよりも人類の宿命だと思う。
台風や地震で大きな被害が出たが、これもこの地球に生きる生物の宿命だ。北海道で酪農の被害が報道されている。酪農業界は規模拡大を目指しているが、ミルクプラントを拠点とした電気と水のバクアップ体制を考える必要を教えてくれた。また、地震に強い土地基盤を探して建物配置を考えることも、酪農だけでなく生活を始める第一歩として重要なこともあろう。
田沼意次が失脚した背景には、天明の大地震、天明の大飢餓、浅間山の大噴火があった。老中首座であった阿部正弘(備後福山藩第7代藩主)が、堀田正睦を震災担当の老中とし、ついで首座の座を譲ったのも安政の大地震対策を重視したことによる。
地方から東京への人口集中も危ない。地方の良さや安全性をもっと生活条件として考えるべきだ。私の生まれ育ち、暮らしている「松永」は、あの義昭の「鞆幕府」で知られる瀬戸内の「鞆の浦」が近い北方の山沿いにあり、自然条件の立地は最高だ。それでも駅前商店街は寂れていく。松永を魅力ある街にするには、これまでの発想を変えたシステムが必要だ。そう発想する若者が育ってほしい。
資源の再利用をビジネスとして成功させ、さらに夢を追いかけている石坂典子さんがいる。彼女は知恵泉「みんなの心をつかむ突破力~由利公正」 に出演し、地域に貢献することが「見えないブランド」だとして、会社で「里山管理」を実践している。「見えないブランド」を里山に牛を放牧することでビジネスとして定着させ、日本の荒れる里山をビジネスで守ろうじゃあないか。
参考: 大谷山里山牧場
初稿 2018.9.18 更新 2018.9.29










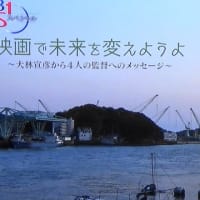



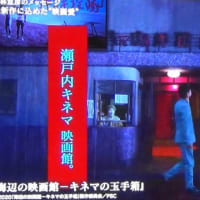
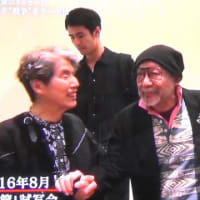

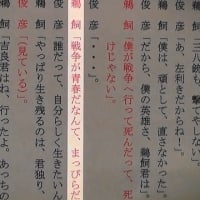



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます