イスラエルとパレスチナ、アメリカとイラク。
こういう中東のゴタゴタを見るにつけ私たち日本人は「お呼びでない」という感に堪えない。
人権問題や差別などという以前に、この人たちの紛争の原因はキリスト教、ユダヤ教、イスラム教による「今どき」宗教戦争。
そこへまったく関係のない仏教徒の日本人が割り込んで「戦いはやめようね」と言ったところで往年の植木等ではないが、
「お呼びでない、お呼びでない、こりゃ待った失礼いたしやした~」
となるのが関の山だ。
ところで私たちが歴史で習うキリスト教とイスラム教の戦いで最も有名なのが十字軍。
アメリカのジョージ・ブッシュ君は9.11テロの時「我々は現代の十字軍だ」と言ってイラクに押入って行ったが、もしあのときにこの本「アラブが見た十字軍」を日本人の多くが読んでいたら、自衛隊の派遣はきっととどまることになっただろう。
なぜなら、十字軍はアラブから見ると野蛮人の侵略者以外の何者でもないのだから。
私たち日本人は一般に西洋人の立場で世界史を眺める習慣を身に付けさせられている。
これは戦後歴史教育のたまものと言うよりも、明治維新以来、西洋を手本にして国造りに励んできた結果でもある。
そんなわけで十字軍も西洋の立場から眺めてきたわけで「アラブから見たらどうなのよ」という仮説にはまったくタッチしてこなかった。
そのアラブから見た十字軍とはどんな連中だったかを記したのが本書なのだ。
で、本書によると当時のアラブから見た西洋人は、
・野蛮人
・人食い人種
・科学を知らずオカルト(加持祈祷など)に頼る
・烏合の衆
に要約できる。
決して現代キリスト教の精神に則った正義の軍団ではなく、本国で食いっぱぐれたならず者集団であったらしい。
目から鱗とはこのことで、確かに11世紀から12世紀にかけての西欧はアラブから見ると危険きわまりない未開の原人といった趣であったようだ。
本書の最大の魅力は、このようなアラブの先進性をその後どうしてアラブは維持発展させることができなかったのか。逆に押入ってきた西洋がアラブの技術や芸術を模倣し、発展させ、それがやがて来るルネッサンス、大航海時代に至り繁栄していったのかを分析しているところだ。
そこには世界共通の「驕る平家は久しからず」が存在する。
「アラブが見た十字軍」
この中には現代日本に強烈なメッセージが秘められているような気がしてならない。










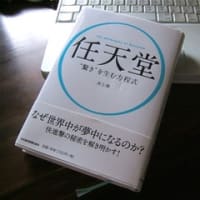








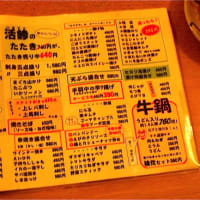
そのツケを払わされた結果がイラク戦争