
1983年のクリスマス。
当時大学生だった私は大阪の玩具店でアルバイトをしていた。
クリスマスは今もそうだろうが玩具店にとってはその1週間後の正月と並んでかき入れ時だ。
ところが、同じかき入れ時でもこの年のクリスマスは例年とかなり異なっていた。
玩具が売れにくい、という現象が生じていたのだ。
その原因は......
ニンテンドー・ファミリーコンピュータ。
この年末、玩具市場は任天堂に席巻されてしまっていた。
来る客来る客が「ファミコンありませんか?」という質問ばかり。
あまりの人気に商品は入荷とともに売れきれてしまい、100台やそこらでは対応しきれない異常な事態に陥っていたのだ。
「梅田の阪急百貨店が20分で1000台を売りきった」
という伝説や、
「○○という玩具店はソフトとセットで数万円で売っていた」
というけしからん話しまで、さまざまな噂や実話が飛び交ったのだった。
その後の任天堂のサクセスストーリーはご存知の通り。
井上理著「任天堂 驚きを生む方程式」はそんな任天堂の歴史と人々を綴った珍しいノンフィクションだ。
京都は「我が道をゆく」という変わった会社が多いことで知られており、とりわけ任天堂の謎は厚いベールで包まれていた。
花札やトランプを作っていた、いわば零細に近いような会社が、いかにして世界企業に躍り出たのか、一般に知られることはなかった。
そういう意味でかなり興味を誘った一冊だった。
ところが読書中、さらに読後、そのサクセスストーリーも色あせるくらい、任天堂のビジネスに対する考え方が今の停滞している日本経済に教えてくれるものが多いかを知った。
その考え方とは「飽き」との戦いだ。
確かにゲームという製品は飽きられる。
飽きられたら消費者が離れて、もしかすると二度と手に取ってもらえないかも分からない。
しかし、それはゲームだけの話しにとどまらず、自動車然り、テレビ然り、あらゆる製品とサービスが同じ問題を抱えているのだ。
任天堂の成功はこの「飽き」をどのようにとらえ、勝負していくのかにあり、この姿勢は大いに参考になるのであった。
とはいえ、一昨日発表になったように任天堂でさえ利益を大幅に減少させ、本書に示されているような驀進できる経済状態ではないことを現在の世界は示している。
「マリオは最初の頃は単なる『オッサン』と呼ばれていたんです。」
と本書。
単なるオッサンが「マリオ」となったように、任天堂は経済沈滞でも「何か”おもろいもの”を生み出すのでは」という期待感のある企業であることは間違いない。
元気をもらえる一冊なのであった。
~「任天堂 "驚き"を生む方程式」井上理著 日本経済新聞出版社~
当時大学生だった私は大阪の玩具店でアルバイトをしていた。
クリスマスは今もそうだろうが玩具店にとってはその1週間後の正月と並んでかき入れ時だ。
ところが、同じかき入れ時でもこの年のクリスマスは例年とかなり異なっていた。
玩具が売れにくい、という現象が生じていたのだ。
その原因は......
ニンテンドー・ファミリーコンピュータ。
この年末、玩具市場は任天堂に席巻されてしまっていた。
来る客来る客が「ファミコンありませんか?」という質問ばかり。
あまりの人気に商品は入荷とともに売れきれてしまい、100台やそこらでは対応しきれない異常な事態に陥っていたのだ。
「梅田の阪急百貨店が20分で1000台を売りきった」
という伝説や、
「○○という玩具店はソフトとセットで数万円で売っていた」
というけしからん話しまで、さまざまな噂や実話が飛び交ったのだった。
その後の任天堂のサクセスストーリーはご存知の通り。
井上理著「任天堂 驚きを生む方程式」はそんな任天堂の歴史と人々を綴った珍しいノンフィクションだ。
京都は「我が道をゆく」という変わった会社が多いことで知られており、とりわけ任天堂の謎は厚いベールで包まれていた。
花札やトランプを作っていた、いわば零細に近いような会社が、いかにして世界企業に躍り出たのか、一般に知られることはなかった。
そういう意味でかなり興味を誘った一冊だった。
ところが読書中、さらに読後、そのサクセスストーリーも色あせるくらい、任天堂のビジネスに対する考え方が今の停滞している日本経済に教えてくれるものが多いかを知った。
その考え方とは「飽き」との戦いだ。
確かにゲームという製品は飽きられる。
飽きられたら消費者が離れて、もしかすると二度と手に取ってもらえないかも分からない。
しかし、それはゲームだけの話しにとどまらず、自動車然り、テレビ然り、あらゆる製品とサービスが同じ問題を抱えているのだ。
任天堂の成功はこの「飽き」をどのようにとらえ、勝負していくのかにあり、この姿勢は大いに参考になるのであった。
とはいえ、一昨日発表になったように任天堂でさえ利益を大幅に減少させ、本書に示されているような驀進できる経済状態ではないことを現在の世界は示している。
「マリオは最初の頃は単なる『オッサン』と呼ばれていたんです。」
と本書。
単なるオッサンが「マリオ」となったように、任天堂は経済沈滞でも「何か”おもろいもの”を生み出すのでは」という期待感のある企業であることは間違いない。
元気をもらえる一冊なのであった。
~「任天堂 "驚き"を生む方程式」井上理著 日本経済新聞出版社~










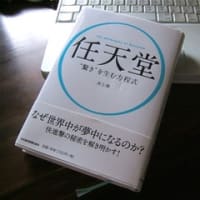








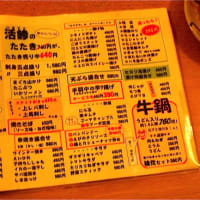
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます