 『アラスカを追いかけて』 ジョン・グリーン 伊達淳・訳
『アラスカを追いかけて』 ジョン・グリーン 伊達淳・訳
面白かった。面白くて、面白くて・・・
本を閉じたとき、思わず、立ち上がって拍手を送りたくなった。ブラボー
ある時期から、アメリカ的なものより、ヨーロッパ的なものに惹かれることが多く、
文学においても、つい、(どんなに面白くても)一つか二つ、文句をつけたくなる
性格の悪い私ですが、この本は・・・・・・・・文句なしに面白かった!!!
物語全体に漂うアメリカ的軽さも、子ども達の抱える、マリファナや煙草や酒やSEX、
貧富の差という問題もひっくるめて、全部、全部、面白かった。
物語は、ある寄宿高校が舞台。
主人公は、「偉大なるもしかして」~フランソワ・ラブレーの言葉~を探して、この
学校に転校してきた少年です。
何でもない自分から抜け出したい主人公の姿は、きっと、多くの子ども達が自分を重ね
るのでは、ないでしょうか。もちろん、かつての私もその一人。
主人公は、偉大なるもしかしてを探しあてることができるのか?
そして、少年と、その友人達につきつけられた
「一体どうやってこのラビリンスから抜け出せばいいんだ」という命題。
少年たち、それぞれが見つける、答えとは・・・・・。
ラビリンス。
青春期の子ども達の思考回路は、何を考えても、すべてがラビリンス。
それこそが、青春なんだろうなと思います。
ラビリンスに入り込んだ主人公が、答えを見つけようともがく苦しみが、読み手にストレートに
伝わってきて、「あの日」を境に、最後のページまで、涙は止まることがありませんでした。
そしてまた、「いつでも、自分が物語の主役」である子ども達が、その傍らで頭を抱えている
友人もまた、同じ、ラビリンスの住人だと気付くことができた瞬間の感動に、言葉もなく
立ち尽くしている私がいます。ブラボー!
こういう本に出会えるんだから、読書は、やめられないなー。
いつか、主人公たちが抱える問題をひっくるめて、理解できるような年齢になったら、
是非、息子にも手渡したい!と思った本でした。












 『アメリカ61の風景』 長田弘
『アメリカ61の風景』 長田弘 読んでみたいと思った本・・・『祟り』トニー・ヒラーマン
読んでみたいと思った本・・・『祟り』トニー・ヒラーマン 『カモ少年と謎のペンフレンド』ダニエル・ぺナック 中井珠子訳
『カモ少年と謎のペンフレンド』ダニエル・ぺナック 中井珠子訳 『みずうみ』 いしいしんじ
『みずうみ』 いしいしんじ 『たんぽぽのお酒』レイ・ブラッドベリ
『たんぽぽのお酒』レイ・ブラッドベリ 『満月をまって』
『満月をまって』  『心をゆさぶる平和へのメッセージ
『心をゆさぶる平和へのメッセージ 『絵本と私』 中川李枝子
『絵本と私』 中川李枝子
 『シモンとクリスマスねこ』
『シモンとクリスマスねこ』 )
)
 )
) 『役にたたない日々』 佐野洋子
『役にたたない日々』 佐野洋子
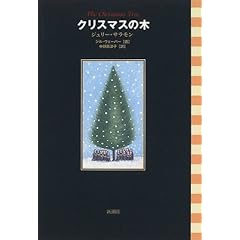 『クリスマスの木』
『クリスマスの木』  『エリック・ホッファー自伝~構想された真実』
『エリック・ホッファー自伝~構想された真実』