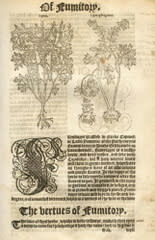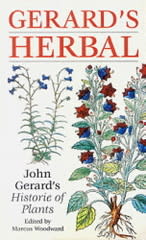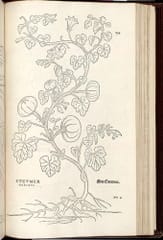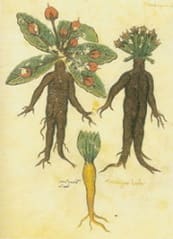コーヒータイム④ オスマン帝国と出合った運
イスラム圏へのコーヒーの伝播
現存最古の資料は、パリ国立図書館にある通称『コーヒー由来書』のようだ。
この本は、1587年にアラビアのイスラム教徒アブダル・カディーによって書かれ、
迫害されるコーヒーを擁護する本だ。
この本が出るまでに、
1511年 メッカ事件といわれるコーヒー禁止令、
1524年 メッカでのコーヒー店禁止、メジナではコーヒーに重税を課す
1534年 カイロでコーヒー店襲撃事件
などの迫害があり、統治者が禁止したくなるほどの危惧とその普及のインパクトがあった証左でもある。
オスマン帝国とめぐり合った“運”
また、迫害がありながらもコーヒーがアラビアで普及していくこの時期は、
オスマン帝国が、アラビアまで領土を拡大し、1517年にはカイロ、1536年にはイエメンが征服された。
オスマン帝国(1299-1922年)は、アジア・アフリカ・ヨーロッパ3大陸にまたがる領土で、
コーヒーは、更に大きな渦に飲み込まれ、グローバル化する下地が用意された。
オスマン帝国の首都、コンスタンティノープルにコーヒーが伝わったのは、1517年。
1554年には、コンスタンティノープルに世界最初のコーヒーハウスが開店した。
1454年のアデンで、イスラム寺院の門外不出の秘薬“カフワ”が公開された。
ほぼ1世紀で、氏素性がよくわからない“カフワ”が、弾圧などを乗り越え
コーヒー嗜好飲料としての基盤を獲得する切符を手にいれたともいえよう。

コーヒーとタバコ
コーヒーとタバコは、ほぼ同時期にハイスピードで世界中に普及する。
グローバル社会への登場もほぼ同じ時期だ。
コーヒーとタバコの普及の類似性と違いをみるために、いずれタバコに関しても調べるが、
両者のハイスピードでの普及は、商業主義だけでは説明つかないものがありそうだ。
17~18世紀は、近代化というその当時にはよくわからなかったであろう大革命での
“興奮”と“覚醒”、これに答えてくれる薬が欲しかったのであろうか?
或いは、こころの交換、意思の交換、コミュニケーションを支援する道具が欲しかったのであろうか
コーヒーハウスの誕生
コーヒー・タバコは、ともに、“神との交信”で使われていたようであり、
寺院から飛び出したコーヒーは、寺院に変わる新たな場・入れ物を必要とし、
その場を創出したのは、当時のグローバルNo1オスマン帝国の首都コンスタンティノープルだ。
世界からの貴人(ヒト)・珍品(モノ)・カネ・情報が集まり、
これらを流通・交換する場が必要であった。
それが“コーヒーハウス”だ。
コーヒーハウスは、ヒトが重要な情報を持っている時代の
コンテンツであるヒトを入れる容器でもあり、メディアでもある。
いわば、双方向型のニューメディアでもあった。
ただ、コーヒーが世に普及していく過程で、危機感を抱かれ迫害されたように、
コーヒーハウスも迫害を受けることになる。
この運命は、すでに誕生した時から内在していた。
コーヒーを媒介とした意見の交換は、“興奮”と“覚醒”そして“権力との戦い”へと拡張する。
“近代化”という“知”が求めたコーヒーとタバコ。
最近は、惰性になっており、感動もなくなった。
これは、低カフェ・低ニコチンなど、安全を求めるがゆえの犠牲なのであろうか?
蛇足ではあるが
コンテンツ(であるヒト)を入れる容器、或いは、乗り物をビークルとかメディアと言っているが、
教室とか牢屋などはメディアとはいえない。
何故だろう? いくつか答えを考えてみたが・・・・・
1.権力と戦ってはいけないから
2.コンテンツではないから
3.価値の交換が出来ないから
4.質問の設定が間違っている
5.その他
その他の答えが結構あるのだろうか?
イスラム圏へのコーヒーの伝播
現存最古の資料は、パリ国立図書館にある通称『コーヒー由来書』のようだ。
この本は、1587年にアラビアのイスラム教徒アブダル・カディーによって書かれ、
迫害されるコーヒーを擁護する本だ。
この本が出るまでに、
1511年 メッカ事件といわれるコーヒー禁止令、
1524年 メッカでのコーヒー店禁止、メジナではコーヒーに重税を課す
1534年 カイロでコーヒー店襲撃事件
などの迫害があり、統治者が禁止したくなるほどの危惧とその普及のインパクトがあった証左でもある。
オスマン帝国とめぐり合った“運”
また、迫害がありながらもコーヒーがアラビアで普及していくこの時期は、
オスマン帝国が、アラビアまで領土を拡大し、1517年にはカイロ、1536年にはイエメンが征服された。
オスマン帝国(1299-1922年)は、アジア・アフリカ・ヨーロッパ3大陸にまたがる領土で、
コーヒーは、更に大きな渦に飲み込まれ、グローバル化する下地が用意された。
オスマン帝国の首都、コンスタンティノープルにコーヒーが伝わったのは、1517年。
1554年には、コンスタンティノープルに世界最初のコーヒーハウスが開店した。
1454年のアデンで、イスラム寺院の門外不出の秘薬“カフワ”が公開された。
ほぼ1世紀で、氏素性がよくわからない“カフワ”が、弾圧などを乗り越え
コーヒー嗜好飲料としての基盤を獲得する切符を手にいれたともいえよう。

コーヒーとタバコ
コーヒーとタバコは、ほぼ同時期にハイスピードで世界中に普及する。
グローバル社会への登場もほぼ同じ時期だ。
コーヒーとタバコの普及の類似性と違いをみるために、いずれタバコに関しても調べるが、
両者のハイスピードでの普及は、商業主義だけでは説明つかないものがありそうだ。
17~18世紀は、近代化というその当時にはよくわからなかったであろう大革命での
“興奮”と“覚醒”、これに答えてくれる薬が欲しかったのであろうか?
或いは、こころの交換、意思の交換、コミュニケーションを支援する道具が欲しかったのであろうか
コーヒーハウスの誕生
コーヒー・タバコは、ともに、“神との交信”で使われていたようであり、
寺院から飛び出したコーヒーは、寺院に変わる新たな場・入れ物を必要とし、
その場を創出したのは、当時のグローバルNo1オスマン帝国の首都コンスタンティノープルだ。
世界からの貴人(ヒト)・珍品(モノ)・カネ・情報が集まり、
これらを流通・交換する場が必要であった。
それが“コーヒーハウス”だ。
コーヒーハウスは、ヒトが重要な情報を持っている時代の
コンテンツであるヒトを入れる容器でもあり、メディアでもある。
いわば、双方向型のニューメディアでもあった。
ただ、コーヒーが世に普及していく過程で、危機感を抱かれ迫害されたように、
コーヒーハウスも迫害を受けることになる。
この運命は、すでに誕生した時から内在していた。
コーヒーを媒介とした意見の交換は、“興奮”と“覚醒”そして“権力との戦い”へと拡張する。
“近代化”という“知”が求めたコーヒーとタバコ。
最近は、惰性になっており、感動もなくなった。
これは、低カフェ・低ニコチンなど、安全を求めるがゆえの犠牲なのであろうか?
蛇足ではあるが
コンテンツ(であるヒト)を入れる容器、或いは、乗り物をビークルとかメディアと言っているが、
教室とか牢屋などはメディアとはいえない。
何故だろう? いくつか答えを考えてみたが・・・・・
1.権力と戦ってはいけないから
2.コンテンツではないから
3.価値の交換が出来ないから
4.質問の設定が間違っている
5.その他
その他の答えが結構あるのだろうか?