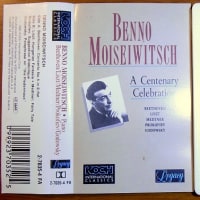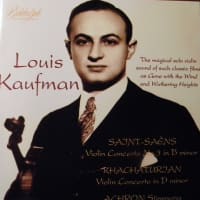【以前のあらすじ】
7日間世界1周小旅行で脳不全を悪化させたバニーちゃんはパブロフ博士とともに帰宅した。子犬にベルを鳴らせて餌をやるのを10年以上続けたら犬が死んだといふパブロフの実験は有名である。(パブロフ博士のお話を読みたい方は、土屋先生の「ツチヤの軽はずみ」文春文庫を購入して読まれることをお勧めする。立ち読みは許されないらしい。)
さて、ミハウォフスキのショパンだが、子犬のワルツ、軍隊ポロネーズ、お腹の痛くなる前奏曲に続いてワルツ嬰ハ短調も大変味わい深い表現に満ちてゐるのでご紹介したい。
ミハウォフスキは、哀愁に満ちたこのワルツでも、今までに聴いたことのないフレージングで歌い、他の誰にも真似のできない装飾や間合いを聴かせてくれる。どの部分を取り出しても音楽的で、無駄は何一つ無い。最高のショパン弾きと言はれる所以だ。
このワルツも2種の録音が残されてゐるが、同じ時期に録音された「子犬のワルツ」とは異なり、一つは1905年、もう一つは1912年9月21日に録音されたもので、7年の隔たりがある。2つの演奏は開始のテンポから全く異なり、表現も12年の方が落ち着きと味わいの深さを感じる。05年の演奏には躍動感と面白さがあり、いずれも現代では聴くことのできない国宝級の演奏だ。
中でもルバートとアルペジオによるメロディーの浮き立たせ方は独特で、おそらくショパン自身がこのやうな表現をとってゐたのだらう。ショパンとリストの録音は残されてゐないため、その弟子のスタイルから推察するしかない。リストの場合は、存命中にエヂソンの蝋管が発明されてゐたくらいだから、その弟子の録音はかなりの量が残されてゐる。しかし、ショパンは19世紀前半にその短い生涯を閉じてしまった。そのため、ミハウォフスキ、プーニョらの伝説上の洋琴家の演奏がレコヲドを通して聴けることは奇跡とも思える。
ショパンの祖国ポーランドは第2次大戦で壊滅的な打撃を受け、ミハウォフスキやミクリの弟子たちも戦争の犠牲となってしまったといふ。そうして、ミハウォフスキが第1回の審査員を務めたショパン・コンクールは、彼の死後、無能な「自称ショパン弾き」たちによって完全に歪められ、その後、現代の実につまらないピアニズムを形成してしまった(と僕は曲解してゐる)。
今からでも遅くはない。過去の文献や楽譜への書き込み、貴重なレコヲドやロールピアノなどの資料を基に、ショパンの演奏スタイルを歴史研究から蘇らせてほしいものだ。丁度、マンロー、ブリュッヘン、クイケンら古楽演奏家たちがやってきたのと同様に、もっと血の通ったショパンが聴きたいのだ。
ミハウォフスキの弾くショパンとの出会ひは、僕にとって久々の衝撃だった。5回続けた連載も、今回で一応打ち止めにしたいが、ミハウォフスキのレコヲドはこれ以外にもまだ幾つも残されてゐる。クララ・シューマンやフランツ・リスト本人とも協演したミハウォフスキの演奏は、どれをとってもミファソラシだ。機会を改めてご紹介したいと思ふ。
盤は、英國Appian P&Rによる蝋管の復刻CD APR5531。
7日間世界1周小旅行で脳不全を悪化させたバニーちゃんはパブロフ博士とともに帰宅した。子犬にベルを鳴らせて餌をやるのを10年以上続けたら犬が死んだといふパブロフの実験は有名である。(パブロフ博士のお話を読みたい方は、土屋先生の「ツチヤの軽はずみ」文春文庫を購入して読まれることをお勧めする。立ち読みは許されないらしい。)
さて、ミハウォフスキのショパンだが、子犬のワルツ、軍隊ポロネーズ、お腹の痛くなる前奏曲に続いてワルツ嬰ハ短調も大変味わい深い表現に満ちてゐるのでご紹介したい。
ミハウォフスキは、哀愁に満ちたこのワルツでも、今までに聴いたことのないフレージングで歌い、他の誰にも真似のできない装飾や間合いを聴かせてくれる。どの部分を取り出しても音楽的で、無駄は何一つ無い。最高のショパン弾きと言はれる所以だ。
このワルツも2種の録音が残されてゐるが、同じ時期に録音された「子犬のワルツ」とは異なり、一つは1905年、もう一つは1912年9月21日に録音されたもので、7年の隔たりがある。2つの演奏は開始のテンポから全く異なり、表現も12年の方が落ち着きと味わいの深さを感じる。05年の演奏には躍動感と面白さがあり、いずれも現代では聴くことのできない国宝級の演奏だ。
中でもルバートとアルペジオによるメロディーの浮き立たせ方は独特で、おそらくショパン自身がこのやうな表現をとってゐたのだらう。ショパンとリストの録音は残されてゐないため、その弟子のスタイルから推察するしかない。リストの場合は、存命中にエヂソンの蝋管が発明されてゐたくらいだから、その弟子の録音はかなりの量が残されてゐる。しかし、ショパンは19世紀前半にその短い生涯を閉じてしまった。そのため、ミハウォフスキ、プーニョらの伝説上の洋琴家の演奏がレコヲドを通して聴けることは奇跡とも思える。
ショパンの祖国ポーランドは第2次大戦で壊滅的な打撃を受け、ミハウォフスキやミクリの弟子たちも戦争の犠牲となってしまったといふ。そうして、ミハウォフスキが第1回の審査員を務めたショパン・コンクールは、彼の死後、無能な「自称ショパン弾き」たちによって完全に歪められ、その後、現代の実につまらないピアニズムを形成してしまった(と僕は曲解してゐる)。
今からでも遅くはない。過去の文献や楽譜への書き込み、貴重なレコヲドやロールピアノなどの資料を基に、ショパンの演奏スタイルを歴史研究から蘇らせてほしいものだ。丁度、マンロー、ブリュッヘン、クイケンら古楽演奏家たちがやってきたのと同様に、もっと血の通ったショパンが聴きたいのだ。
ミハウォフスキの弾くショパンとの出会ひは、僕にとって久々の衝撃だった。5回続けた連載も、今回で一応打ち止めにしたいが、ミハウォフスキのレコヲドはこれ以外にもまだ幾つも残されてゐる。クララ・シューマンやフランツ・リスト本人とも協演したミハウォフスキの演奏は、どれをとってもミファソラシだ。機会を改めてご紹介したいと思ふ。
盤は、英國Appian P&Rによる蝋管の復刻CD APR5531。