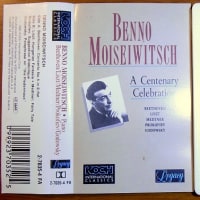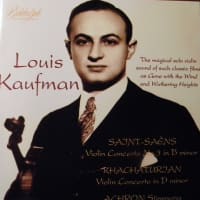名盤中の名盤、説明の必要もない歴史的名演奏のブラームス提琴協奏曲を何十年ぶりかに聴いてゐる。上品さを失しないクライスラーのロマンティシズムは流石だと、つくづく思ふ。しかし、この演奏の素晴らしさのもう一つの理由がブレッヒの伴奏にあることは、今回聴いてみて初めて痛感したのである。昔、聴いた名盤も、齢を重ねて聴きなおすと面白い発見の連続である。興味が尽きない。
冒頭のアッチェレランドなどは、フルトヴェングラーとメニューヒンの演奏を聴いて育った僕にとっても、とてもしっくりとくる。いかにも独逸的な伴奏に乗った生粋の維納人の典雅な提琴がなんともいへぬ美しいバランスを醸し出す。
クライスラーらしさが最も際立つのは、第2楽章ではないだろうか。独特の強弱の付け方やそれにぴったりと寄り添うブレッヒのタクトは冴え渡ってゐる。浪漫派の時代の息遣いが存分に楽しめ、しかも現代の耳にも非常に音楽的に新しい。こういった演奏が時代を超えた名演奏として歴史的な評価を得るのだ。
第3楽章も第1主題のテヌートをたっぷりとかけたクライスラーの独特の歌の邪魔をしないやうにブレッヒは控え目な伴奏をつけてゐる。派手な解釈で聴きなれた第3楽章をこのやうな音楽的な演奏で聴くと、なにかとても得をしたやうな気になるものだ。
野村光一氏は1923年に来朝した折に、クライスラーを聴き、1930年代後半のレコヲドの新譜評で『十数年前に實演で聴いた時の如き繊細と甘美の限を盡くした音色も失はれてゐる。』と云ってゐる。レコヲドと實演を比べて語るのは間違いであるが、実際に聴いた人の言葉は重い。野村光一氏に高く評価され、維納に渡った友人TUは、その後どうしてゐるのだろう。今でも頑固な便秘に苦しんでゐるのだろうか、と不意に気になる。
このレコヲドは来朝の4年後に当たる1927年の録音である。絶頂期にあったクライスラーの演奏を生で聴いた日本国民は本当に幸せな人たちだと思ふ。

盤は、英國Biddulph社のSP復刻CD LAB050。
冒頭のアッチェレランドなどは、フルトヴェングラーとメニューヒンの演奏を聴いて育った僕にとっても、とてもしっくりとくる。いかにも独逸的な伴奏に乗った生粋の維納人の典雅な提琴がなんともいへぬ美しいバランスを醸し出す。
クライスラーらしさが最も際立つのは、第2楽章ではないだろうか。独特の強弱の付け方やそれにぴったりと寄り添うブレッヒのタクトは冴え渡ってゐる。浪漫派の時代の息遣いが存分に楽しめ、しかも現代の耳にも非常に音楽的に新しい。こういった演奏が時代を超えた名演奏として歴史的な評価を得るのだ。
第3楽章も第1主題のテヌートをたっぷりとかけたクライスラーの独特の歌の邪魔をしないやうにブレッヒは控え目な伴奏をつけてゐる。派手な解釈で聴きなれた第3楽章をこのやうな音楽的な演奏で聴くと、なにかとても得をしたやうな気になるものだ。
野村光一氏は1923年に来朝した折に、クライスラーを聴き、1930年代後半のレコヲドの新譜評で『十数年前に實演で聴いた時の如き繊細と甘美の限を盡くした音色も失はれてゐる。』と云ってゐる。レコヲドと實演を比べて語るのは間違いであるが、実際に聴いた人の言葉は重い。野村光一氏に高く評価され、維納に渡った友人TUは、その後どうしてゐるのだろう。今でも頑固な便秘に苦しんでゐるのだろうか、と不意に気になる。
このレコヲドは来朝の4年後に当たる1927年の録音である。絶頂期にあったクライスラーの演奏を生で聴いた日本国民は本当に幸せな人たちだと思ふ。

盤は、英國Biddulph社のSP復刻CD LAB050。