酒田出身の写真家土門拳は、記念館案内パンフが空港から道の駅から行く先々に置かれていて、山形が誇る著名人といった感じだったが、

鳥海山を臨んで、池に囲まれ、記念館の建築、庭、彫刻、「自然と建物」にまず驚かされ、

まず、記念館にかかわった才能を楽しんだ。
設計を建築家・谷口吉生、作庭とオブジェを華道家・勅使河原宏、中庭設計・彫刻と石のベンチをイサム・ノグチ、エントランス銘板をグラフィックデザイナー・亀倉雄策
今季の展示は
・古寺巡礼 第一集
いうまでもない土門拳のライフワーク、法隆寺、中宮寺、飛鳥・白鳳・天平、いずれもどこかで見た覚えのある有名なものだ。
一作ごとの迫力に加えて、ずらりと並んだ展示に圧倒された。
・こどもたち
1950年代の江東、浅草、の貧しくても元気いっぱいな子供たち、この中にマルガリータも写っていそうと、思わず見入ってしまった。

土門拳賞受賞作品展「不知火海」桑原史成
『半世紀を超える”水俣病”事件の通史』、これ以上ない「リアリズム写真」を前に、旅の最後に現実に戻されたような衝撃だった。


鳥海山を臨んで、池に囲まれ、記念館の建築、庭、彫刻、「自然と建物」にまず驚かされ、

まず、記念館にかかわった才能を楽しんだ。
設計を建築家・谷口吉生、作庭とオブジェを華道家・勅使河原宏、中庭設計・彫刻と石のベンチをイサム・ノグチ、エントランス銘板をグラフィックデザイナー・亀倉雄策
今季の展示は
・古寺巡礼 第一集
いうまでもない土門拳のライフワーク、法隆寺、中宮寺、飛鳥・白鳳・天平、いずれもどこかで見た覚えのある有名なものだ。
一作ごとの迫力に加えて、ずらりと並んだ展示に圧倒された。
・こどもたち
1950年代の江東、浅草、の貧しくても元気いっぱいな子供たち、この中にマルガリータも写っていそうと、思わず見入ってしまった。

土門拳賞受賞作品展「不知火海」桑原史成
『半世紀を超える”水俣病”事件の通史』、これ以上ない「リアリズム写真」を前に、旅の最後に現実に戻されたような衝撃だった。















 ;右方が別館
;右方が別館
























































 副題が[1866-1886 ジャポニスムの成熟]、
副題が[1866-1886 ジャポニスムの成熟]、


















 夏物の入荷待ちで今一つさえない。
夏物の入荷待ちで今一つさえない。



 <思索空間>
<思索空間>












 千住明・オペラ
千住明・オペラ  坂東玉三郎
坂東玉三郎






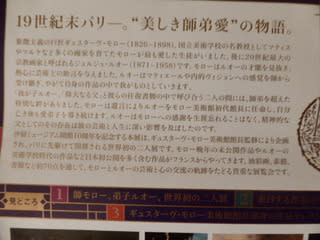
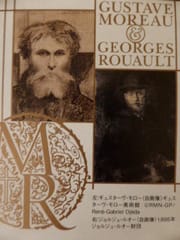
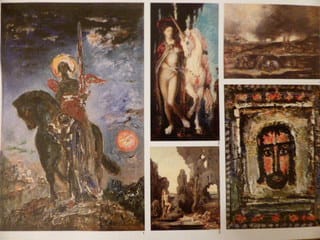





 風間サチコ
風間サチコ  サイモン・フジワラ
サイモン・フジワラ 柳 幸典
柳 幸典 






