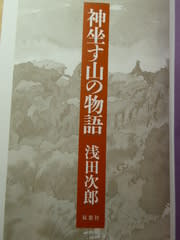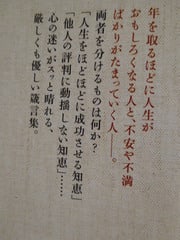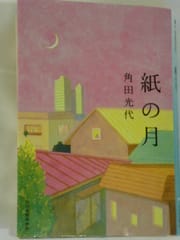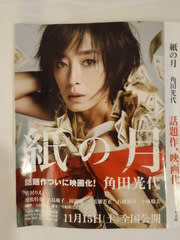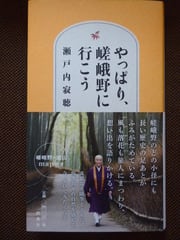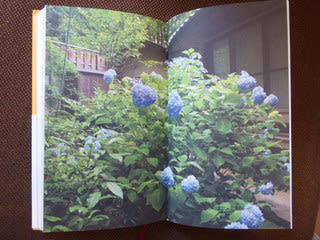JR八王子駅の大型書店、友人との待ち合わせ時間までの所在なさで〝ベストセラーコーナー”に手が出た。
『住んでみたヨーロッパ 9勝1敗で日本の勝ち』川口マーン恵美、



語り口が一刀両断的、すっきり☆ いちいち納得する☆ マルガリータとは相性良し! 気が合うかも(笑)
30年間のドイツ暮らしから、かの地と、EU,ヨーロッパ事情と、日本との比較対照。
マルガリータの体験も少々織り込むと、
第6章から; 馬肉スキャンダルとは何か
イギリス冷凍ラザニアに牛の代わりに馬のひき肉、ドイツでも、
ルーマニアの野良馬が肉やに持ち込まれ、馬肉の供給が増えた。~先日のルーマニアで昼食のミートボールがもたれて仕方なかった、
第10章から;知らない土地では劇場か動物園に
知らない土地で、その町の豊かさは「劇場と動物園」にまでお金を描けているかどうか、
マルガリータもいつも言っている、「ミュンヘンのオペラ座、ガスタイク、ミュンヘン動物園がある限り…」
ボルドーのオペラ座、リガのオペラ座、も良かった。
やる気が失せるオーケストラ
お客の質で本当にコンサートは左右される。 パリ・サル・プレイエルはいつも安心して聴ける。
第12章から;ロマの物乞いの背景に犯罪組織が
パリのオペラ座付近の日本人は格好の餌食、白昼堂々、少女の群れに囲まれてあっというまに携帯電話、財布を持って行かれる。
シャンゼリゼ最寄りの警察署で、10歳くらいの少女満載ワゴン車を目撃した。居合わせた仏人女性弁護士も、
「未成年は即釈放で警察もいたちごっこでなすすべがない」とあきらめ顔。それを承知で上部も繰っているのだ。
(書きかけ~
『住んでみたヨーロッパ 9勝1敗で日本の勝ち』川口マーン恵美、



語り口が一刀両断的、すっきり☆ いちいち納得する☆ マルガリータとは相性良し! 気が合うかも(笑)
30年間のドイツ暮らしから、かの地と、EU,ヨーロッパ事情と、日本との比較対照。
マルガリータの体験も少々織り込むと、
第6章から; 馬肉スキャンダルとは何か
イギリス冷凍ラザニアに牛の代わりに馬のひき肉、ドイツでも、
ルーマニアの野良馬が肉やに持ち込まれ、馬肉の供給が増えた。~先日のルーマニアで昼食のミートボールがもたれて仕方なかった、
第10章から;知らない土地では劇場か動物園に
知らない土地で、その町の豊かさは「劇場と動物園」にまでお金を描けているかどうか、
マルガリータもいつも言っている、「ミュンヘンのオペラ座、ガスタイク、ミュンヘン動物園がある限り…」
ボルドーのオペラ座、リガのオペラ座、も良かった。
やる気が失せるオーケストラ
お客の質で本当にコンサートは左右される。 パリ・サル・プレイエルはいつも安心して聴ける。
第12章から;ロマの物乞いの背景に犯罪組織が
パリのオペラ座付近の日本人は格好の餌食、白昼堂々、少女の群れに囲まれてあっというまに携帯電話、財布を持って行かれる。
シャンゼリゼ最寄りの警察署で、10歳くらいの少女満載ワゴン車を目撃した。居合わせた仏人女性弁護士も、
「未成年は即釈放で警察もいたちごっこでなすすべがない」とあきらめ顔。それを承知で上部も繰っているのだ。
(書きかけ~

























 ←トランシルヴァニアを旅するアメリカ人
←トランシルヴァニアを旅するアメリカ人