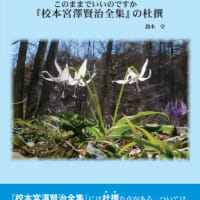そもそも、なぜ私はここまで松田甚次郎の下根子桜の訪問回数とその日がいつかを調べてきたのかというと、甚次郎が賢治から〝どやされた〟と千葉恭の目からは見えた日がいつかを確定したかったからだ。
というのは、千葉恭は追想の「宮澤先生を追つて(三)」において、
ところで、当然のことながら、甚次郎が賢治から〝どやされた〟のは賢治の許を訪ねた日でしかあり得ない。しかもそれは、『松田甚次郎の日記』を調べた結果、
さてこの両日のそれぞれについて、昭和2年3月8日の訪問に関して甚次郎は、
一方、昭和2年8月8日の訪問に関しては、
前掲の甚次郎の証言から、賢治から甚次郎が〝どやされた〟のはどちらの日がふさわしいかというと、もちろん後者8月8日はあり得ず、前者3月8日であろう。
なぜならば、昭和2年2月1日付岩手日報の記事に、取材を受けた賢治が、
もちろん、この〝どやされた〟日は甚次郎が盛岡高等農林在学中であろうことは私も以前からほぼ確信していた。しかも、それはあの昭和2年3月8日の日のことであろうともまたである。しかし一抹の不安があった。というのは甚次郎は高等農林に在学中にかなりの回数下根子桜に賢治を訪ねていたと受け止められるような表現をしているある資料が、2つほどあったからである。そこで、甚次郎が〝どやされた〟と千葉恭が受け止めたような場面を他の日に千葉恭は目の当たりにしていたかも知れない、という一抹の不安があった。もしそのようなことがあれば〝どやされた〟日はあの昭和2年3月8日とは言い切れなくなってしまうからである。
しかし今回の新庄行で『松田甚次郎日記』を見ることが出来たので、甚次郎が盛岡高等農林在学中に賢治を訪ねたのはたった1回だけであったということが分かった。この〝たった1回だけ〟であったということは、彼が学生時代にかなりの回数そこを訪ねたわけではなくてたった一度しか訪ねていないということを担保する重要な役割を持つ。
したがって、千葉恭の目から甚次郎が賢治から〝どやされた〟と見えた日は昭和2年3月8日でしかあり得ないことになる。これが〝たった1回だけ〟の持つもう一つの重要な意味であり、役割である。逆の言い方をすれば、このようなことなどが導けるのではなかろうかとだろうと思ったので、私はここまで甚次郎の下根子桜の訪問回数とその日がいつかを調べてきたのだった。
というわけで、現時点での私の判断は、
さあそうすると、残された次の大きな課題は何か。それは、いつ頃から恭は賢治と一緒に暮らし始めたのか、その時期を明らかにすることだ。そしてその時期は彼が穀物検査所を辞めた時期とほぼ重なるだろうから、役所をいつ辞めたかを知るということでもある。
<*1:投稿者註> 一般に、賢治はシャイで心優しい人と思われているようだが、実は案外そうでもなかったらしい。それは、羅須地人協会員であった伊藤忠一も高橋慶吾も、そして伊藤克己も、「とても気持ちの変化がはげしい人だった」というようなことを語っていたと、菊池忠二氏が『私の賢治散歩 下巻』の36pで「意外に思った」こととして紹介しているからである。このことを知るともはや、あの「春と修羅」の中に、有名な次の連、
 続きへ。
続きへ。
前へ 。
。
 〝『非才の私でも賢治研究は出来る』の目次〟へ
〝『非才の私でも賢治研究は出来る』の目次〟へ
”みちのくの山野草”のトップに戻る。
〈新刊案内〉
この度、拙著『このままでいいのですか 『校本宮澤賢治全集』の杜撰』

を出版した。その最大の切っ掛けは、今から約半世紀以上も前に私の恩師でもあり、賢治の甥(妹シゲの長男)である岩田純蔵先生が目の前で、
延いては、
しかしながら、数多おられる才気煥発・博覧強記の宮澤賢治研究者の方々の論考等を何度も目にしてきているので、非才な私にはなおさらにその追究は無謀なことだから諦めようかなという考えが何度か過った。……のだが、方法論としては次のようなことを心掛ければ非才な私でもなんとかなりそうだと直感、しかも根拠も無いままに確信もした。
周知のようにデカルトは『方法序説』の中で、
すると、非才な私でもなんと賢治研究が出来た。その結果、辿り着けた事柄を述べたのが、拙著『このままでいいのですか 『校本宮澤賢治全集』の杜撰』(鈴木 守著、録繙堂出版、1,000円(税込み))であり、その目次は下掲のとおりである。

現在、岩手県内の書店で販売されております。
なお、岩手県外にお住まいの方も含め、本書の購入をご希望の場合は葉書か電話にて、入手したい旨のお申し込みを下記宛にしていただければ、まず本書を郵送いたします。到着後、その代金として1,000円分(送料無料)の切手を送って下さい。
〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木守 ☎ 0198-24-9813
というのは、千葉恭は追想の「宮澤先生を追つて(三)」において、
詩人と云ふので思ひ出しましたが、山形の松田さんを私がとうとう知らずじまひでした。その后有名になつてから「あの時來た優しさうな靑年が松田さんであつたのかしら」と、思ひ出されるものがありました。<『四次元7号』(宮澤賢治友の会)>
と、また追想の「羅須地人協会時代の賢治」において、 一旦弟子入りしたということになると賢治はほんとうに指導という立場であつた。鍛冶屋の気持ちで指導を受けました。これは自分の考えや気持ちを社会の人々に植え付けていきたい、世の中を良くしていきたいと考えていたからと思われます。そんな関係から自分も徹底的にいじめられた。
松田甚次郎も大きな声でどやされたものであつた<*1>。<『イーハトーヴォ復刊2号』(宮澤賢治の会)>
と述べているからだ。意外なことに、「自分も徹底的にいじめられた」と千葉恭は証言しているのである。そしてまた注目すべきことは、賢治の許を訪れた甚次郎が賢治から〝どやされ〟ていると千葉恭からは見えたその場面を、千葉恭は目の当たりにしていたに違いない、ということが導かれる。松田甚次郎も大きな声でどやされたものであつた<*1>。<『イーハトーヴォ復刊2号』(宮澤賢治の会)>
ところで、当然のことながら、甚次郎が賢治から〝どやされた〟のは賢治の許を訪ねた日でしかあり得ない。しかもそれは、『松田甚次郎の日記』を調べた結果、
〝松田甚次郎が下根子桜に賢治を訪ねたのは昭和2年3月8日と同年8月8日の2回だけであり、その2回しかない〟
ということが先に判明出来ているから、この両日のどちらかでしかあり得ない。さてこの両日のそれぞれについて、昭和2年3月8日の訪問に関して甚次郎は、
先生は足下に「そんなことでは私の同志ではない。これからの世の中は、君達を学校卒業だからとか、地主の息子だからとかで、優待してはくれなくなるし、又優待される者は大馬鹿だ。煎じ詰めて君達に贈る言葉はこの二つだ――
小作人たれ
農村劇をやれ」
と、力強く言はれたのである。
とか、 小作人たれ
農村劇をやれ」
と、力強く言はれたのである。
黙って十年間、誰が何と言はうと、実行し続けてくれ。そして十年後に、宮澤が言った事が真理かどうかを批判してくれ。今はこの宮澤を信じて、実行してくれ」と、懇々と説諭して下さつた。私共は先覚の師、宮澤先生をたゞたゞ信じ切つた。
ということを述べている。一方、昭和2年8月8日の訪問に関しては、
それから一ヶ月間余暇をぬすんで、初体験の水掛と村の夜の事を脚本として書いて見た。そして倶楽部員の訂正を仰いで、ほゞ筋が出来たが、何だか脚本として物足りなくて仕様がないので困つてしまつた。「かういふ時こそ宮澤先生を訪ねて教えを受くべきだ」と、僅かの金を持つて先生の許に走つた。先生は喜んで迎へて下さつて、色々とおさとしを受け、その題も『水涸れ』と命名して頂き、最高潮の処には篝火を加へて下さつた。この時こそ、私と先生の最後の別離の一日であつたのだ。余りに有り難い一日であつた。やがて『水涸れ』の脚本が出来上がり、毎夜練習の日々が続いた。<共に『土に叫ぶ』(松田甚次郎著、羽田書店)>
と述べている。そこで、このそれぞれの訪問日に関する甚次郎の証言を基に〝どやされた〟日について次に考えてみたい。前掲の甚次郎の証言から、賢治から甚次郎が〝どやされた〟のはどちらの日がふさわしいかというと、もちろん後者8月8日はあり得ず、前者3月8日であろう。
なぜならば、昭和2年2月1日付岩手日報の記事に、取材を受けた賢治が、
「目下農民劇第一回の試演として今秋『ポランの廣場』六幕物を上演すべく夫々準備を進めてゐるが、…」
と答えたという報道がなされたのだが、賢治自身はその後農民劇の準備を進めていった気配はない。一方の、8月8日に下根子桜を訪れた松田甚次郎の方は着々と農村(民)劇の準備をしており、脚本さえ出来上がりつつある。8月8日に訪れた松田甚次郎が賢治から褒められることはあっても〝どやされる〟筋合いにはなかったはず。よって、「そんなことでは私の同志ではない。…地主の息子だからとかで、優待してはくれなくなるし、又優待される者は大馬鹿だ。…小作人たれ 農村劇をやれ」と、力強く言はれた」
のは3月8日の方でしかあり得ないはずだからである。そしてこの時の賢治の諭し方は他人から見れば〝どやされた〟と見えないこともなかろう。もちろん、この〝どやされた〟日は甚次郎が盛岡高等農林在学中であろうことは私も以前からほぼ確信していた。しかも、それはあの昭和2年3月8日の日のことであろうともまたである。しかし一抹の不安があった。というのは甚次郎は高等農林に在学中にかなりの回数下根子桜に賢治を訪ねていたと受け止められるような表現をしているある資料が、2つほどあったからである。そこで、甚次郎が〝どやされた〟と千葉恭が受け止めたような場面を他の日に千葉恭は目の当たりにしていたかも知れない、という一抹の不安があった。もしそのようなことがあれば〝どやされた〟日はあの昭和2年3月8日とは言い切れなくなってしまうからである。
しかし今回の新庄行で『松田甚次郎日記』を見ることが出来たので、甚次郎が盛岡高等農林在学中に賢治を訪ねたのはたった1回だけであったということが分かった。この〝たった1回だけ〟であったということは、彼が学生時代にかなりの回数そこを訪ねたわけではなくてたった一度しか訪ねていないということを担保する重要な役割を持つ。
したがって、千葉恭の目から甚次郎が賢治から〝どやされた〟と見えた日は昭和2年3月8日でしかあり得ないことになる。これが〝たった1回だけ〟の持つもう一つの重要な意味であり、役割である。逆の言い方をすれば、このようなことなどが導けるのではなかろうかとだろうと思ったので、私はここまで甚次郎の下根子桜の訪問回数とその日がいつかを調べてきたのだった。
というわけで、現時点での私の判断は、
恭は昭和2年3月8日に下根子桜を訪ねてきた甚次郎本人を直に見ている。そして賢治から甚次郎が「小作人たれ 農村劇をやれ」と〝訓へ〟られている場面を恭は〝どやされた〟と受け止めていた。
というものである。またこのことにより、恭はその現場にいたということになるから、 ☆千葉恭は昭和2年3月8日頃までは少なくとも下根子桜で賢治と一緒に暮らしていたということが充分に考えられる。
である。なお、この3月8日前後だけたまたま千葉恭は下根子桜櫻の別宅に泊まっていたとも考えられる。それゆえ、現時点では〝ということが充分に考えられる〟としてある。このことに関しては今後注意深く扱い、さらなる検証を試みたい。さあそうすると、残された次の大きな課題は何か。それは、いつ頃から恭は賢治と一緒に暮らし始めたのか、その時期を明らかにすることだ。そしてその時期は彼が穀物検査所を辞めた時期とほぼ重なるだろうから、役所をいつ辞めたかを知るということでもある。
<*1:投稿者註> 一般に、賢治はシャイで心優しい人と思われているようだが、実は案外そうでもなかったらしい。それは、羅須地人協会員であった伊藤忠一も高橋慶吾も、そして伊藤克己も、「とても気持ちの変化がはげしい人だった」というようなことを語っていたと、菊池忠二氏が『私の賢治散歩 下巻』の36pで「意外に思った」こととして紹介しているからである。このことを知るともはや、あの「春と修羅」の中に、有名な次の連、
いかりのにがさまた青さ
四月の気層のひかりの底を
唾しはぎしりゆききする
おれはひとりの修羅なのだ
が登場しているのも宜なるかなと私は思ってしまう。賢治は自分のことを「おれはひとりの修羅」と見立て、その心情を包み隠さずに吐露していたのだ、と。四月の気層のひかりの底を
唾しはぎしりゆききする
おれはひとりの修羅なのだ
 続きへ。
続きへ。前へ
 。
。 〝『非才の私でも賢治研究は出来る』の目次〟へ
〝『非才の私でも賢治研究は出来る』の目次〟へ”みちのくの山野草”のトップに戻る。

〈新刊案内〉
この度、拙著『このままでいいのですか 『校本宮澤賢治全集』の杜撰』

を出版した。その最大の切っ掛けは、今から約半世紀以上も前に私の恩師でもあり、賢治の甥(妹シゲの長男)である岩田純蔵先生が目の前で、
賢治はあまりにも聖人・君子化され過ぎてしまって、実は私はいろいろなことを知っているのだが、そのようなことはおいそれとは喋れなくなってしまった。
と嘆いたことである。そして、私は定年後ここまでの16年間ほどそのことに関して追究してきた結果、それに対する私なりの答が出た。延いては、
小学校の国語教科書で、嘘かも知れない賢治終焉前日の面談をあたかも事実であるかの如くに教えている現実が今でもあるが、純真な子どもたちを騙している虞れのあるこのようなことをこのまま続けていていいのですか。もう止めていただきたい。
という課題があることを知ったので、 『校本宮澤賢治全集』には幾つかの杜撰な点があるから、とりわけ未来の子どもたちのために検証をし直し、どうかそれらの解消をしていただきたい。
と世に訴えたいという想いがふつふつと沸き起こってきたことが、今回の拙著出版の最大の理由である。しかしながら、数多おられる才気煥発・博覧強記の宮澤賢治研究者の方々の論考等を何度も目にしてきているので、非才な私にはなおさらにその追究は無謀なことだから諦めようかなという考えが何度か過った。……のだが、方法論としては次のようなことを心掛ければ非才な私でもなんとかなりそうだと直感、しかも根拠も無いままに確信もした。
周知のようにデカルトは『方法序説』の中で、
きわめてゆっくりと歩む人でも、つねにまっすぐな道をたどるなら、走りながらも道をそれてしまう人よりも、はるかに前進することができる。
と述べていることを私は思い出した。同時に、石井洋二郎氏が、 あらゆることを疑い、あらゆる情報の真偽を自分の目で確認してみること、必ず一次情報に立ち返って自分の頭と足で検証してみること
という研究における基本姿勢を教えてくれているから、具体的にはこの姿勢を心掛けて粘り強く取り組めばなんとかなるだろう、と意を決して歩き出すことにした。すると、非才な私でもなんと賢治研究が出来た。その結果、辿り着けた事柄を述べたのが、拙著『このままでいいのですか 『校本宮澤賢治全集』の杜撰』(鈴木 守著、録繙堂出版、1,000円(税込み))であり、その目次は下掲のとおりである。

現在、岩手県内の書店で販売されております。
なお、岩手県外にお住まいの方も含め、本書の購入をご希望の場合は葉書か電話にて、入手したい旨のお申し込みを下記宛にしていただければ、まず本書を郵送いたします。到着後、その代金として1,000円分(送料無料)の切手を送って下さい。
〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木守 ☎ 0198-24-9813