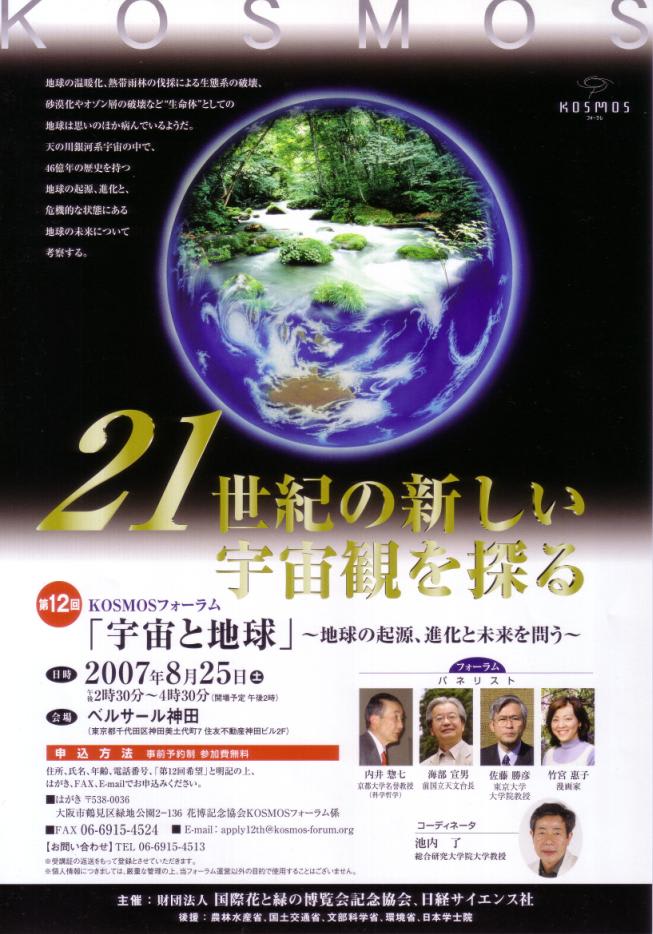聖徳太子「十七条憲法」は、604年に発布された日本の最初の憲法です。
そもそも「憲法」という言葉自体、「十七条憲法」に由来するものです。
ところが、戦後、かつてお話したような事情で、日本人が自分の原点を忘れてしまうような教育制度が出来上がってしまいました
*。
日本史や倫理の時間にほんの少し仏教の話、聖徳太子の話が出てはきますが、「十七条憲法」の全文を高校までの授業でちゃんと読む機会を与えられた人は、ほとんどいないでしょう。
私も、読んだ記憶がありません。授業時に聞き取り調査をしていますが、私の学生の中でもこれまでのところ1人もいないようです。
しかし、良かれ悪しかれ、これは日本という国の出発点・原点です。
価値判断の前に、ともかく私たちは読んでみる必要があるのではないでしょうか。
読みもしないで、進歩主義的偏見で「古い」とか「右よりだ」とか「保守反動だ」と言ってしまうのは、おなじくちゃんと読まないで信奉する保守主義的偏見とおなじくらい不毛でフェアでない態度だと思います。
そこで、これからしばらくみなさんに原文(の書き下し)と私の現代語訳をご紹介し、短いコメントを加えて、判断の材料にしていただこうと思います。
一に曰く、和をもって貴しとなし、忤(さから)うことなきを宗(むね)とせよ。人みな黨(とう)あり。また達(さと)れる者少なし。ここをもって、あるいは君父(くんぷ)に順(したが)わず。また隣里(りんり)に違(たが)う。しかれども、上(かみ)和(やわら)ぎ、下(しも)睦(むつ)びて、論(あげつら)うに諧(かな)うときは、事理(じり)おのずから通ず。何事か成らざらん。
第一条 平和をもっとも大切にし、抗争しないことを規範とせよ。人間にはみな無明から出る党派心というものがあり、また覚っている者は少ない。そのために、リーダーや親に従わず、近隣同士で争いを起こすことになってしまうのだ。だが、上も下も和らいで睦まじく、問題を話し合えるなら、自然に事実と真理が一致する。そうすれば、実現できないことは何もない。
ここには、日本という国がもっとも優先的に追求すべき国家理想は人間と人間との平和――そして後でお話しすることで明らかになるように人間と自然との調和も含まれています――であることが高らかに謳われています。
しかもそれだけでなく、争い・戦争というものは無明
*から出てくる自分たちさえよければいいという党派心から生まれるという深い人間洞察が、短い言葉のなかでみごとに表現されています。
無明がなくならないかぎり、戦争はなくならない、平和は実現しない、人間と自然との調和も実現しないのです。
しかし、たとえまだ無明を克服し覚ることのできていない人間であっても、心を開いて親しみの心をもって、事柄とコスモスの真理が一致するところまで徹底的に話し合うなら、たとえどんなに困難なことでも実現できないことはない、というのです。
近代的な民主主義のまったくない時代に、私利私欲ではなく理想を目指して徹底的に議論すること、話し合いによる政治を提唱し、「和の国日本」の建設という当時の状況からすればほとんど不可能に見える大国家プロジェクトをみんなで立ち上げよう、と太子は呼びかけています。
この理想、このプロジェクトは1400年経っても、残念ながら実現されていないのではないでしょうか。
これは、私たち日本人の立ち帰ることのできる原点、立ち帰るに値する原点、立ち帰らなければならない原点だ、と私は思うのです。
*ところで、ここで念のために言わせていただきますが、私は右でも左でもありません。右の妥当な面と左の妥当な面を統合したいと思っているのです。
↓ご参考になりそうでしたら、お手数ですが、是非、2つともクリックしてメッセージの伝達にご協力ください。
人気blogランキングへ