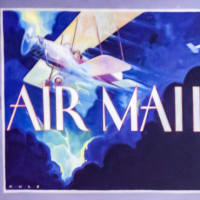しかし行ってみて驚いたのが防衛大学開校記念祭の盛りだくさんなこと。
さすがはわが国唯一の国立士官学校です。
ほかの大学では決して見ることのできない儀仗隊の演技や棒倒し、
なんといっても次々と一瞬だけ上空を通過するのは本物の自衛隊機。
大学祭に学生の家族が大挙して参加する大学、というのも他に例を見ませんが、
全くその大学に縁もゆかりもない観客が、そこで行われる出し物?を一目見ようと
詰めかける大学祭もまたおそらくここだけでしょう。
さて、そんな、ほかにはない大学祭の出し物、その一つが「落下傘降下」。
なにしろ本物の空挺団が空から降りてくるのです。あたりまえだけど。

降下する空挺隊員は三人。
飛行機から間をおかずに降下します。
空挺団、落下傘部隊は旧軍時代は陸海共に保持していましたが、
現在は陸自の第一空挺団だけが落下傘降下を行う部隊です。
以前、「空の神兵」という、陸軍空挺団の映画について書いたことがありますが、
この第一空挺団は、まさにこの映画に描かれた部隊が前身となっています。
1954年に、元帝国陸軍空挺団の元隊員を集めて構成されました。
文字通りの「空の神兵」の末裔です。

なんの危なげもなく、正確にグラウンド真ん中に着地。
あたりまえのようですが、これが精強の部隊空挺団の実力だと分かったのは、
このあとの「防大パラシュート部」の降下を見たときでした。
その話はまた後ですることにして。
二本の足で軽々と着地した瞬間、
ものすごいスピードで傘をたたみます。
これを、全くの一人でやってしまう、ということですら、
どうやら自衛隊唯一の精強空挺団ならではであったことが、
しつこいですが、防大パラシュート部の降下を見たときに納得しました。
ちなみに、部隊の標語は「精強無比」。
二人目が降下してきました。
先日入間の航空祭で見たパラシュートとは色も形状も違います。
たたんでいるところを見ると分かりやすいですが、
やはり視認性を低くするためにグレーの傘となっています。
このパラシュートはラムエアFS-300という形のようですが、
入間の時の茶色い(ゴールド?)落下傘は「60式空挺用」というそうです。
フランスの会社のものを、日本の藤倉航装という会社がライセンス生産しています。
入間の航空祭の観覧記で、「空の神兵」の、
「真白き薔薇の花模様」
というような形状のパラシュートはもう二度と自衛隊では使われないのでしょうか、
と嘆いてみたわけですが、このHPによると、空挺用の696MIという形のパラシュートが、
どうやら「真白き薔薇」状である模様。
いや、よかったよかった。
入間の時は足をまっすぐに、体を棒のようにして降下していましたが、
この日の降下隊員はラフな?態度に思われました。
降下の仕方も、傘の形状や、編成によって変わったりするのでしょうか。
このころから、なぜかわかりませんがグラウンドに向かってスモークが焚かれ、
ただでさえ曇っているのにあたりは真っ白になってしまいました。
もしかしたら、降下後の行動を援護する意味で張られる煙幕でしょうか。
空挺団は、ただ落下傘で降りてくればそれで仕事が終わるわけではありません。
「空の神兵」でもそうであったように、降下後の作戦行動、それがメインです。
みなさんは「軽歩兵」という言葉をご存知ですか?
軽歩兵というのは、最小の装備で柔軟な戦闘、つまりゲリラ的な戦闘を行う兵を指します。
つまり、散兵戦でもって特殊な任務にあたることが目的とされるわけです。
大東亜戦争の典型的な空挺部隊の作戦が、これも一度集中的に記事にした
「義烈空挺隊の敵中強行着陸」です。
陸自第一空挺団は、正規軍との防衛作戦はもちろん、ゲリラに対して即応できる
「精強軽歩兵」という位置づけがされているのです。
またもや軽々と着地。
前にも書きましたが、この空挺団は「陸自最強」と言われています。
訓練生になるのも条件があり、知力体力ともに重要ですが、
体力のハードルは非常に高いと思われます。
握力30キロ以上、肺活量3200立方cm以上、呼吸停止50秒以上。
わたしは握力でまず駄目だな。
しかし、面白いのが血圧。
140mmHg~100mmHg、90mmHg以下、ということになっています。
低いのはいくら低くてもいいけど、高いとダメ、ってことでしょうか。
なんでも自分の話をして申し訳ありませんが、
エリス中尉、実は異常なくらいの低血圧で、上が100を超えたことがない、下は底なし、
という人間なので、この点だけは合格できそうです。
血圧が高いと降下中さらに血圧が上がってまずいんでしょうか。
いつ傘を体から取り外したのかわからないくらいの早業でした。
こんな隊員がそろっているのですから、当然スポーツ競技会は、
自衛隊内でも外でも、大変な活躍をするのだそうです。
かれらのモットーは「風林火山」。
「風」=速きこと風のごとく、持続走(富士駅伝など)を走る。
「林」=徐かなること林の如く、射撃競技会で撃つ。
「火」=侵掠すること火の如く、ラグビーで燃える。
「山」=動かざること山のごとく、武道競技で相手を圧する。
いったいなんなんだよこの集団は・・・・・。
なんか、凄くないですか?紐。
よくこんな超早回しでやっているのに紐が絡まないものです。
全力で傘から空気を抜くために押さえつけてますね。
背中に背負ったパックの空き方が面白い。
「空の神兵」では、バックパックの表面に落下傘の傘をきっちりたたんで、
決して絡まないように慎重に紐をセットしている様子が描かれていました。
降りた順番に正面に走っていき、そこで座って待機。
三人がそろったので立ち上がり・・・・、
観閲官の前に進み出ます。
起立、礼。
パラシュートを抱えて退場。
おーい、真ん中の隊員~!
もう少し短く持たないと踏んじゃうよ~。
と思っていたら、ちゃんとたくし上げて持っていました。
しかし、こんなことをいちいち点検するやつもあまりいないであろう。
一番後ろの隊員
「一番先に降下したから小さくたためたんじゃないもんね!実力だもんね!」
真ん中
「わーん、ちゃんとたためなかったよ~」
先頭の隊員
「あ、なんか落ちてる」
大アップ。
ヘルメットがかっこよろしおすなあ。
空挺団について書かれたものを見ると、この部隊の強そうなことと言ったら、
やたらたくさんある部隊モットーに、
「いかなる犠牲があろうとも」とか「たとえ最後の一員となっても」などという、
悲壮な文言が織り込まれていることにも表れています。
実際に空挺団はイラク復興支援群に警備部隊として派遣されていますし、
海外において万が一有事になった際、
邦人保護のために出動するのが目的の隊もすでに編成されています。
あの上九一色村のオウム真理教の強制捜査の際には、
最悪の事態に備えて空挺団は出動できるような態勢で待機をしていたそうです。
生身の体で上空から地上に降り立ち、すぐさま戦闘行動に移る、という、
大変な身体能力と精神力、加えて強靭な意志と大胆かつ細心の判断力。
まるで現代のスーパーマンのような彼らの降下に、
満場の観客は思わず息をのんだのでした。
そんな彼らの「空挺精神」とは。
空挺精神 精鋭無比
空挺隊員は、強靭な意志と追随を許さない創意と挺身不難の気概とを堅持し、
剛胆にして沈着、機に応じ自主積極的に行動し、
たとえ最後の一員となっても任務の達成に邁進(まいしん)しなければならない。
というわけで、この精強の部隊に配属されることを(おそらく)願っている、
防大のパラシュート部について次回はお話します。