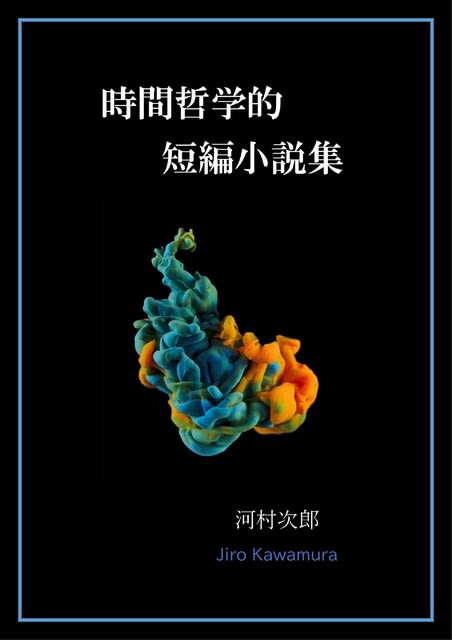これで私が書いた哲学的短編小説集は五冊目となるが、今回は時間哲学に焦点を当てて、七編の哲学的短編小説を書き上げた。時間の問題は古代ギリシャ以来、西洋哲学の根本問題の一つである。
今回の本には七編の短編小説が収録されているが、そのタイトルとその主題と趣旨は次のようなものである。
1 夭折の美学の時間性 (三島由紀夫の生涯と文学ないし芸術をヒントにして夭折の美学の時間性を短編小説によって象徴的に表現しようとしたもの)
2 腫瘍と時間 (「腫瘍と時間」という極めて書きづらいタイトルをあらかじめ決めておいて、とにかく書き上げようとして、実際書き上げた作品。「がん」ではなくて「腫瘍」と時間の関係を哲学的かつ文学的に表現しているところが面白い)
3 「未来は決定されている」と思い込む自由意志否定論者の根本的誤謬 (「決定論と自由」という問題は古代以来の哲学の根本問題であるが、ここではそれを時間論との関係で取り上げ、短編小説化した。決定論論者の自己撞着と時間理解の浅さが浮き彫りにされる)
4 鬱と不眠の時間性 (職場と仕事のストレスからうつ病になったサラリーマンの意識と心身状態を、時間性に焦点を当てて、短編小説によってその意味を象徴的に表現したもの。鬱と不眠は密接に関係しているが、この関係の時間性を哲学的心身問題と臨床時間生物学と精神医学の三つの観点を融合し書き上げた秀作である)
5 運命と時間/あるいは幸福と不幸の時間性 (運命という意味深い現象を時間性の観点から解き明かした短編小説。運命と幸・不幸の関係も論じられ、幸福と不幸それぞれの時間的性質が明らかにされる。身につまされる話である)
6 未来のことは未来の私にまかせてようのか (『未来のことは未来の私にまかせよう』という希望に満ちた闘病記を出版した翌年、三二歳の若さで、スキルス胃がんで死んだ女性キャスターの例をばねにして、本当は「未来のことは未来自体にまかせよう」ということが重要だと説いた短編小説。生命と時間の関係を未来という現象の理解に焦点を当てて象徴的に論じた短編小説)
7 失われた時を求めないでいたら (「昔はよかったなー」という懐古意識を極端に毛嫌いする政治家志望の男の転落劇。過去を振り切りつつ、常に前向きに活動したがるバイタリティーの塊が、「昔はよかったなー」という意識の本当の意味と「失われた時を求める」心性の重要さを死の床で次第に理解していく話。「昔はよかったなー」と失われた時を求めていく心性は、消極的な懐古趣味ないし後退主義ではなくて、実は堅実な積み重ね主義だったのである。悩みのない馬鹿的なリア充は死に瀕して初めてその意味を知るという話)
今回も医学的話題に満ちた哲学的短編小説集になっている。いちおう時間という哲学の根本問題を短編小説によって象徴的に表現しようという趣旨で書いたが、あまり時間論という観点に拘らずに、短い物語の中に時間の深い意味を織り込む、という手法を取った。その方が理屈っぽくなくて、読者も親しみやすいと思ったからである。
むしろ、こうした書き方の方が、時間を表立って主題とするよりも、時間の深い意味の文学的象徴化を成功させているかもしれない。いずれしても、読者は先入見を排して、この七編の短編小説を思う存分楽しんでほしい。