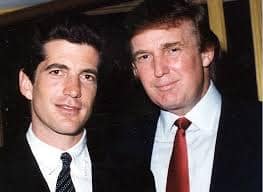CIAに睨まれ「罠」にハマった菅総理大臣の去就は、大海の木の葉、「東北新社」は「電通」の配下であり、「CIA」の企業グループである!!

中國に近づき過ぎてCIAの簡単な「罠」にハマってしまった菅総理大臣の去就は、CIAに握られてしまった!!
あわれ菅総理の命運は、就任まもなく尽きてしまった!!

菅首相、長男の「東北新社」中途入社で便宜図る…創業者に口利き、元総務相の立場を利用か
首相官邸のHPより
菅義偉首相の長男で東北新社社員の菅正剛氏から総務省幹部が接待を受けていた問題で、同省は24日、谷脇康彦総務審議官ら9人を懲戒、2人を戒告とする処分を発表した。
総務審議官時代の2019年に接待を受けていた山田真貴子内閣広報官は25日、衆院予算委員会に参考人として出席。
山田氏は「(首相の長男との会食は)私にとって大きな事実ではない」「放送業界全体の実情に関する話はあったかもしれないが、全体としては一般的な懇談だった」などと語り、内閣広報官を続投する意向を示している。
総務省はBS・CSなどの衛星放送事業の許認可権を有しているが、東北新社は子会社を通じて現在、計8つの衛星チャンネルを運営。
総務省幹部が同社から接待を受けていた時期にあたる18年には総務省は同社子会社の「囲碁将棋チャンネル」(CS放送)、20年には「スター・チャンネル」(BS放送)の継続・更新を認可している。
そして菅正剛氏は東北新社のメディア事業部趣味・エンタメコミュニティ統括部長というポストに就くほか、同社子会社で総務省認定の衛星基幹放送事業者である囲碁将棋チャンネルの取締役も務めている。
「正剛氏は現在40歳ということですが、その年で東北新社クラスの老舗大手メディア企業の部長職、さらには子会社取締役というのは、異例中の異例というか、ちょっとあり得ない人事です。
さらに、40歳そこそこの部長クラスが、総務省幹部と会食をするというのも、通常では、あり得ません。
本来なら東北新社本体の役員クラスが相手をする話ですから。まさに“菅さんの息子”ゆえの特別待遇ですよ」(大手広告代理店社員)
菅首相と東北新社の関係
東北新社といえば、前述の衛星放送関連事業のほか、テレビ番組・映画・CM制作、映画配給、各種映像コンテンツの輸入・仕入・販売・編集・版権ビジネスなど、映像関連ビジネス全般を幅広く手掛ける名門企業として知られている。
その同社に正剛氏は2008年に中途入社しているが、06年に当時総務相だった父・菅氏の秘書官に就くまではバンド活動をしていたと報じられており、東北新社が手掛けるビジネスでの経験は特に見当たらない。
一方、菅首相と東北新社の関係は深い。菅首相と同社創業者(故人)はともに秋田県出身で、創業者とその息子の元社長から12~18年に計500万円の個人献金を受けている。
さらに22日の衆院予算委員会で菅首相は、創業者と自身の長男を引き合わせたことを認める一方、「(長男の正剛氏と創業者の)2人で(就職の)話を決めた」と答弁した。
「なんの実績もない20代の若者が、大手メディアの創業者と“2人で話して就職が決まる”なんて、これを聞いて“コネ入社”だと思わない人はいないですよね。
総務相を経験した大物政治家が息子と創業者を“引き合わせた”となれば、結果として世間的には“口利き”と見なされても仕方ないでしょう。
大手広告代理店はコネ入社が多いと誤解されがちですが、たとえば電通の場合、毎年百数十人の新卒社員のうち、純粋なコネ入社というのは、そのうちの数人、一桁台くらいじゃないでしょうか。
もちろん業種にもよりますが、今は一部上場企業だと、大口取引先企業の部長クラスの子息くらいでは難しく、役員クラスにならないとコネ入社の対象に入ってこないのではないでしょうか。
もっとも、大手メディアには“政治家枠”があるので、有力議員の子息などは結構多いですが、今回の東北新社のケースのように、自社の事業にダイレクトに権限を持つ省庁の大臣経験者の子息となれば、採用しないわけにはいかないでしょうし、むしろ“入社させて利用しよう”と考えるのは企業としては当然でしょう」(大手広告代理店社員)
そして、過去に総務相・官房長官を歴任した菅首相といえば、総務省のみならず省庁全体に絶大な力を持つ政治家として知られている。
「強引に総務省でふるさと納税を推し進めた菅氏は首相就任後、政権の浮揚策の目玉として、総務省が管轄する通信業界に携帯電話料金の値下げを飲ませた。
その菅首相の側近だった谷脇総務審議官、吉田真人総務審議官、秋本芳徳前情報流通行政局長の3人組が、あろうことか総務省のダイレクトな利害関係者である東北新社社員で、菅首相の息子である正剛氏から接待を受けていた。
さらに同省出身で菅首相が内閣報道官に抜擢した山田氏まで同罪だったわけで、まさに“菅首相の身内が全員ズブズブ”な実態が露呈した格好となりました」(全国紙記者)
「わいろ」に当たる?
自身の政治的立場を利用して、息子の就職に便宜を図っていたのだとすれば、倫理的に許されることではないが、法的に問題はないのだろうか。
山岸純法律事務所の山岸純弁護士は、次のように解説する。
「実は、収賄罪や贈賄罪で問題となる『わいろ』は、金銭に限られず、『人の需要もしくは欲望を充たすべき一切の利益』とされているので、代わりに借金を返済してくれた、豪華な食事をおごった、というのも『わいろ』になる場合があります。
『親族を入社させる』というのも、入社倍率が高く給与も良い会社への紹介などであれば、人が羨む職に就かせたという点で『わいろ』にあたるかもしれませんね。
もっとも、収賄罪などは、単に『わいろ』をもらっただけでは成立せず、『職務に関して』という要件が必要となります。
菅首相の息子が就職したのが2008年、菅首相が総務相を退任したのは07年なので、いくら就職先が総務省が管轄する放送事業を行っていたとしても、『職務に関して』とするのはムリでしょう。
また、『コネ入社』自体も、いわゆる政治家の“口利き”のレベルでしょうから、法律問題とすることは難しいでしょう。
ただ、一時期のスポーツ推薦で偏差値の高い大学に入ったスポーツが得意な高校生のほとんどがスポーツ以外の大学の授業についていけなくなった例と同様に、実力で入社してないなら、たいしたことはないんでしょうね(スポーツ推薦を否定する考えではありません)」
盤石とみられた菅政権だが、早くも綻びが見え始めている。
(文=編集部、協力=山岸純/山岸純法律事務所・弁護士)
「フジと日テレ」の外資比率が、東北新社を超えても許される理由

武田良太総務相は3月26日の閣議後の記者会見で、放送事業会社「東北新社」の衛星放送事業の一部の認定を5月1日付で取り消すことを明らかにした。
放送法で定める外資規制により、外国人等議決権割合が20%を超えていたにもかかわらず、事実と異なる申請を行っていたことが理由だ。
だが、外国人による株の保有比率を見ると、東北新社よりも高いのがフジ・メディア・ホールディングスと日本テレビホールディングスの2社である。
東北新社の問題をきっかけに、今後、放送業界の外資規制に注目が集まりそうだ。(株式会社アシスト社長 平井宏治)
各国で放送事業者に
外資規制が設けられている理由
2021年3月23日に行われた武田良太総務相の定例会見で、記者からは次のような質問が上がった。
「東北新社は免許を取り消され、他方、(外国人等議決権比率が外資規制を超えている)フジテレビと日本テレビが見逃されているのはどういうわけでしょうか。
法の下の平等や公平性、公正性に反するように思われます。理由をお聞かせください」
だが、これに対し、武田大臣は「事実関係をよく確認した上で、適切に対処してまいりたい」とだけ述べ、具体的な対応については言及しなかった。
わが国では、電波法や放送法により放送会社の外国人等議決権割合は5分の1(20%)を超えてはならないと定められている。
放送業者に対する外資規制が行われている理由は、放送が世論に及ぼす影響を考慮した安全保障上の理由による。
放送業者に対する外資規制は、わが国だけでなく、アメリカ合衆国でも欧州でも類似の制限が設けられている。
電波法第5条3項は、認定放送持株会社の欠格事由として、放送法5条1項に定める外国人等の議決権割合が全ての議決権の5分の1を超えないこととしている。
だが、外国人直接保有比率が、5分の1を超えている企業は、東北新社だけではない。
2021年3月26日において、フジ・メディア・ホールディングス、日本テレビホールディングスの外国人直接保有比率はそれぞれ、32.12%、23.77%と、発行済株式総数の5分の1を超えている。
とはいえ、発行済株式総数は議決権の数とは一致しない。
定款で単元株式数を定めている場合は、1単元の株式につき1個の議決権となるが、単元株式数未満の株式(端株)には議決権はない。
そして、放送免許の欠格事由では議決権の個数が問題になる。
総務省の通達で変更された
外国人等議決権の計算方法
だれでも証券会社を通じて上場会社の株式を購入することができる。多くの外国人が上場放送会社の株式を買えば、単元株に付いている議決権も総議決権個数の5分の1を超えてしまい、上場放送会社は何もできない。
そこで、放送法116条では、外国人等の議決権割合が、全ての議決権の5分の1を超え、欠格事由に該当した場合は、その氏名および住所を株主名簿に記載し、または記録することを拒むことができるとしている。
なお、外国人等の議決権割合の計算方法は、総務省が2017年9月25日に上場する放送事業会社に出した通達文書により、計算方法が変更されている。
筆者が総務省と上場放送会社に確認したところ、通達前は、総議決権個数に19.99%を掛けた個数が、外国人等の議決権割合とされていた。
例えば、総議決権個数が1万個の場合、1999個(1万×19.99%)が外国人等の議決権割合とされていた。
しかし、この計算方法では、実際に株主総会で外国人等が行使できる議決権個数が5分の1を超えてしまう。どういうことか、順を追って説明したい。
放送事業者A社について、総議決権個数が1万個、外国人等が保有する議決権の個数が3000個だったと仮定する。
日本人の保有する議決権個数は、7000個(1万-3000)になる。一方、外国人等が保有する議決権3000個のうち、1999個は議決権行使ができるが、残る1001個は上場する放送会社が名義書き換え拒否をする。
この1001個の議決権を持つ外国人等の株主は株主名簿に記載されないので、株主総会の招集通知は送付されない。
その結果、株主総会は、1999個の議決権を持つ外国人等株主と7000個の議決権を持つ日本人株主で行われる。
外国人等が行使できる議決権割合は、1999÷8999=22.21%になり、全議決権個数の5分の1を超えてしまうのだ。
筆者は、2011年頃からこの問題に気づき、総務省に外国人等が行使できる議決権個数の計算方法を変えるように陳情を行った。
筆者以外にこの問題に気づいた人たちからも指摘があり、2017年9月25日、総務省は外国人等が行使できる議決権の計算方法を変更する通達を対象となる放送事業者へ出した。
では、一体どのような通達なのか。
通達内容は非公開だが、筆者が総務省と上場する放送会社に確認した内容を基に、先述のA社の例を使い説明する。少し難しいことはご容赦いただきたい。
日本人の持つ議決権は7000個だ。この日本人の議決権を総議決権個数の80%とするため、まずは7000÷0.8を計算(8750個)。
さらに外資規制では外国人等議決権割合が20%を下回る必要があるため、8750個から議決権1個を引いた8749個を総議決権個数とする。
総議決権個数が8749個なので、外国人等が行使できる議決権個数は、8749-7000=1749個になる。
その結果、外国人等が保有する議決権総数のうち、1251個(3000-1749)が名義書き換え拒否の対象になるのだ。
なお、実際の計算は、自己株式の議決権を除いたりするので、これらを加味した計算結果が公表される。
実際に日本テレビホールディングスの状況はどうなっているのか。
同社のプレスリリース(2020年4月17日)によれば、2020年3月31日の算定となる総議決権個数は、242万9423個。
そのうち、外国人等が行使できる議決権個数は48万5884個と、外国人等議決権割合は19.99%(正確には、19.99998%)となり、欠格事由を回避している。
また、同社の有価証券報告書には、名義書き換え拒否をした議決権個数は10万8693個だったことなどが記載されている。
ところが、東北新社は外国人等が行使できる議決権個数の割合が全議決権個数の5分の1を超えていたにもかかわらず名義書き換え拒否の処理を行わなかったため、欠格事由に該当することになった。
初歩的なミスだが、法律は法律だ。衛星放送の認可が取り消しになるのは当然であり、東北新社の衛星放送認可取り消しの理由は、これ以上でもこれ以下でもない。
保守系メディアの
外国人直接保有比率は高い傾向
有価証券報告書を使い、在京5局の外国人等が行使できる議決権個数比率をグラフにまとめた。
このグラフは、分子は「外国法人等+外国人持株調整株式の単元数」、分母は「全単元株数-自己株式の単元数」とし、それ以外の調整は行っていない。
テレビ番組が国民世論に及ぼす影響が大きいことを考慮すると、電波法や放送法により放送会社の株主総会で行使できる議決権を制限すれば事足りることだろうか。
確かに議決権行使は19.99%に調整される。しかし、実際に外国人等が放送会社の株式を大量に保有することが、放送会社の運営に影響を与えないと断言はできない。
外国人直接保有比率が高ければ、外国による影響が高くなるし、外国人直接保有比率が低ければ、外国による影響が低くなるだろう。
グラフからも明らかだが、放送業界全体の外国人直接保有比率が高いのではない。日本テレビ(読売系)、フジテレビ(産経系)のいわゆる「保守系」メディアの外国人直接保有比率が高い一方で、TBSやテレビ朝日(朝日系)といったいわゆる「リベラル系」メディアの外国人直接保有比率は低い。
外国人直接保有比率の高低には配当性向や配当利回りの違いがあるとする意見もあるが、こうしたメディアとしてのスタンスが影響している可能性はないのだろうか。
国際情勢や安全保障問題などを取り上げる番組の多くが地上波放送から姿を消し、グルメ番組、お笑い番組、スポーツ中継、ワイドショーばかりが放送されている。
核兵器保有国の谷間にあるわが国の状況や尖閣諸島への領土・領海侵入危機など、国民が知るべき報道が不十分であることを憂慮すべきだ。
インターネットなどさまざまな方法で情報を集め分析し判断する人たちがいる一方で、情報端末操作ができず地上波だけが唯一の情報収集手段の人たちもいる。
地上波だけが情報収集手段の有権者に対し、外国の意向を反映した報道が流れ、外国の思惑通りに世論形成され誘導されるリスクを踏まえて、外国人直接保有比率の是非を改めて議論すべきだろう。
また、外国人直接保有比率については、国別の情報が開示されないことは問題だ。
放送会社の株主名簿を見ると、主要株主にカストディアン(投資家に代わって有価証券の保管・管理を行う金融機関)の名前が並んでいる。
また、日本に帰化した外国人が保有する株式は、日本人保有株式にカウントされることも留意する必要がある。

放送事業が国民世論に及ぼす影響を考えれば、最低限でも国別の開示は必要であるし、タックスヘイブンやファンドなど真の持ち主の正体を隠す投資家による放送業界の株式取得は規制されてもよいのではないか。
放送業界と安全保障との関係を考えると、非上場化を行い、非上場化の際に外国人株主をスクイーズアウト(少数株主の排除)する選択肢もある。
外国の影響を排除するならば、官民ファンドを設け、MBO(経営陣が参加する買収)を行い、外国人投資家を株主から一掃することは可能だ。
とはいえ、非上場化しても、放送番組の政治的公平性などを定めた放送法4条が守られるとは限らないとの指摘もある。
放送番組の制作に外国の影響を受けないための制度設計が必要なことは言うまでもない。
東北新社の認可取り消しで放送業界の外資規制に注目が集まった。このことをきっかけに放送と安全保障の議論が盛り上がることを期待したい。
保守系メディアの株式を買い、大株主となった外国の思惑が放送会社へ及び、外国の意向を忖度(そんたく)した放送を流しているという意見がある一方で、放送局は外国人直接保有比率に関係なく、日本の国益に資する放送を流しているという意見もある。
いずれにせよ、外資規制導入の趣旨を考えると、外国人直接保有比率が高いことは、好ましい状況ではない。
以上
ルールを破った「人食い」は、処刑できるがルールを破らない「人食い」は処刑できない!!

こんなバカな約束があるという・・・。
機密開示【世界同時緊急放送システム】
膨大な機密情報が開示されるが、人類が一番衝撃を受けるのは【レプテリアン】です。
銀河連合も衝撃だろうが、人類誕生の初めからレプテリアンに地球が支配されていたなぞ放送を聞いて見ても信じられないのではないか。
レプテリアン→悪魔崇拝・人身売買・小児性愛者・レイプ虐待・アドレナクロム・殺害・人食い→バチカン→ディープステート→グローバリスト・中国共産党・明治維新の真実→偽天皇→詐欺政界・財界・医療・金融・国の偽借金・詐欺税金制度・国民洗脳メディア→人類ゴイム化→気象兵器→人工地震→人口削減→偽ウイルスコロナ→殺人ワクチン。
そのために数日間繰り返し繰り返し見せる聞かせる。
特にテレビ人間の方々の衝撃は計り知れないだろう。
地球が生まれ変わるのだから子供も大人もない。
1人の人間(知的生命体)として扱う。
世界人類の救世主!!
自警団を各地に設立して、家族を守れ!!
日本テンプル騎士団が支援します!
日本国自立なくして、子供たちの輝かしい将来はない!!
TEL042-365-2728 FAX042-361-9202
住所、氏名。 電話番号を明記の上でFAXでお問い合わせください!!
多くの方たちから「行方不明の子供」の情報が送られてきます!!
敵わぬ敵ではあるが、身を挺して子供たちを守らなくてはならない!!
限りなく美しい国のために、そして民族のために屍と成りても闘わん!!
有志達392名が、参加したいとの希望がありましたが危険が伴いますので一部の方を除いて「声援」だけをお願いしました・・・感謝します!!
この「人食い問題」を、解決しない限り、私たちに安住の地はない!!
犬、猫にも、効果絶大です!!