
-
経済成長の鈍化:以前のような高度経済成長は期待できず、不動産バブルの崩壊や消費の低迷など、様々な要因で経済成長が鈍化しています。
-
不動産市場の過熱は、地方政府の財政問題や金融システム不安を引き起こし、経済全体に悪影響を及ぼしています。
-
一党独裁体制:民主的なプロセスを経ない意思決定や、情報統制、人権問題などが、国際社会からの批判を招き、経済活動にも制約をもたらしています。
-
貿易摩擦や技術覇権争い、地政学的な対立など、米中関係の悪化は、中国経済に大きな影響を与えています。
-
人口減少と高齢化は、労働力不足や社会保障費の増大など、中長期的な経済成長の足かせとなっています。
また、国内の不満を抑え込み、国際社会からの信頼を取り戻すためには、より透明性の高いガバナンスや人権尊重が不可欠です。
中国が「迷走」から脱却し、持続可能な発展を遂げるためには、国内改革と国際協調の両輪をバランスよく進めることが求められます。
2025年7月統計:中国景気は「迷走」を継続、大規模な景気刺激策は?
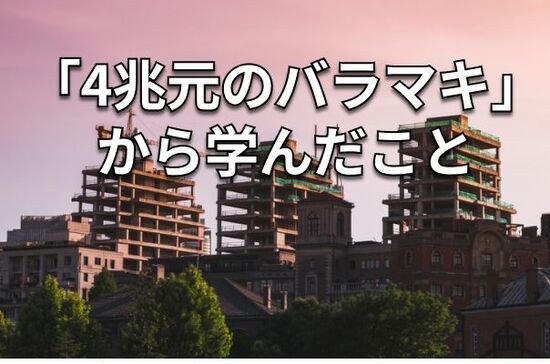
中国政府が7月の主要経済統計を発表しました。生産、小売売上、投資は軒並み低迷し、不動産不況やデフレスパイラルも続いています。
そんな中、習近平氏率いる中国共産党指導部は景気の現状をどう認識しているのか?
大規模な景気刺激策は打ち出されるのか?
最新の統計と政策動向に基づいて分析します。
貿易は7月、5.9%増(輸出7.2%、輸入4.1%)となり、1~6月の2.9%増(輸出7.2%増、輸入2.7%減)と比べると改善が見られますが、関税協議を続ける米国との貿易統計を単独で見てみると、7月、中国の対米輸出が12.6%減、輸入は10.3%減と依然低迷しています。
先週のレポートで扱ったように、米中両国政府は、8月12日に期限を迎えていた24%の関税適用の停止措置を、さらに90日間延長することで合意しました。協議が破綻する局面は逃れましたが、次なる期限の11月10日に向けて、不透明で不安定な状況が続くものと思われます。
中国共産党指導部の現状認識
本連載でも適宜扱ってきたように、習近平氏率いる中国共産党指導部は、「トランプ関税」、およびそこから生じ得る米中貿易摩擦を、2025年の中国経済にとっての最大の不安要素と認識している、というのが私の理解です。
故に、米中関税協議のもようや進展を密にフォローすることが、中国経済の推移を分析する上で極めて重要です。
共産党指導部の経済情勢を巡る認識や、これから打ち出される可能性のある政策を理解する上で、私が重視しているのが、7月30日に行われた中央政治局の会議です。
中央政治局というのは、中国共産党における最高意思決定機関であり、基本的に毎月末に開催されます。
習近平氏を含めた中国共産党中央政治局常務委員(チャイナセブン)も原則として全員参加します。
毎年7月の中央政治局の会議では経済情勢が審議されるのが恒例です。上半期の経済情勢を振り返り、夏以降の経済政策を審議し、方向性を定めることが目的です。
●昨今、中国の経済運営は少なくないリスクと課題に直面している。情勢を正確に把握し、危機意識を高め、ボトムラインを堅持し、発展のチャンスと潜在力、アドバンテージをしっかり発揮することで、景気回復をさらに良い方向に押し上げる
●従来以上に積極的な財政政策と、適度に緩和的な金融政策をより着実に、きめ細かく実践し、政策の効果を十分に放出する
●内需の潜在力を放出する。商品消費を拡大すると同時に、サービス消費の新たな成長分野を育成する。
国民生活を保障する中で消費のニーズを拡大する。民間の投資活力を促し、有効な投資を拡大する
●対外貿易で影響の大きい輸出企業を、融資強化などを通じて支援する
●国内の資本市場の吸引力と包容性を高め、資本市場の回復と成長を促す
●雇用優先の政策を突出させる。大学卒業生、退役軍人、農民工といった集団の雇用を重点的に促進していく
財政政策や金融政策を含めたマクロ政策を徹底的に実践していくこと、複数の角度から消費を促していくこと、トランプ関税が中国経済へもたらすショックにピンポイントで対応すること、低迷してきた資本市場を活性化させること、何より雇用優先の経済政策を打ち出すこと、などが掲げられています。
大学卒業生、退役軍人、農民工(農村から都市部への出稼ぎ労働者)という三つのグループを具体的に取り上げているのは興味深いです。
大学卒業生は毎年約1,000万人、退役軍人は約5,700万人、農民工は約2億人以上います。
これらの人々が職に就けなかったり、路頭に迷ったり、社会保障を受けられなかったりすれば、単なる経済問題ではなく、社会不安や政治リスクをも誘発し得るという危機感を有していることが分かります。
習近平氏を含め、経済情勢の現状を決して楽観視せず、とにかく危機意識と警戒心を持って、できることは全部やる、可能な限り合理的で、照準を絞った形でやる、そうすることで、2025年の成長率目標(5.0%前後)は達成され、経済社会は初めて安定し得るという認識を抱いているのだと分析しています。
大規模な景気刺激策の可能性は?
それだけの危機感を党指導部として持っているからには、景気を上向かせるべく、マーケット側が期待するような、大規模な景気刺激・支援策を打ち出すのではないか、という期待値が高まりそうですが、その点に関して、私は懐疑的な姿勢を崩していません。
理由は大きく分けて二つあります。
一つ目が、党指導部として、リーマンショック後に打ち出した景気刺激策4兆元のトラウマに駆られているからです。
あの時になりふり構わず打ち出した「4兆元の罠」が、今日まで続く過剰生産能力や地方債務といったジレンマを引き起こし、いまだに解決できない構造的問題になっている、故に、大規模な景気刺激策を安易に出すことはできない、というのが党指導部が有する教訓であり、総括です。
二つ目が、前述したように、確かに習近平氏を含め、党指導部は経済情勢に対して危機感と警戒心を崩していませんが、一方で、2025年の上半期の国内総生産(GDP)実質成長率は5.3%増と年間目標を上回っています。
また、懸念されてきたトランプ関税に関しても、最終合意には至っていないものの、継続的に協議は行われており、追加関税適用も90日間再延長されました。
このあたりの状況を受けて、「経済情勢や景気動向を巡る指標や要素は、一定程度コントロールできている」「既存のマクロ政策に加えて、刺激策や支援策を、小刻みにピンポイントで打ち出していくことで、目標達成は可能だ」という認識を党指導部が有している、というのが私の仮説であり、分析です。
従って、中国政府がこれから年末にかけて、大規模な景気刺激策を打ち出すことに対して、過度な期待を抱かずに、情勢や政策を注視していくのが現実的な路線だと思います。
自警団を各地に設立して、家族を守れ!!
日本国自立なくして、子供たちの輝かしい将来はない!!
TEL042-365-2728 FAX042-361-9202
住所、氏名。 電話番号を明記の上でFAXでお問い合わせください!!
多くの方たちから「行方不明の子供」の情報が送られてきます!!
敵わぬ敵ではあるが、身を挺して子供たちを守らなくてはならない!!
限りなく美しい国のために、そして民族のために屍と成りても闘わん!!
有志達392名が、参加したいとの希望がありましたが危険が伴いますので一部の方を除いて「声援」だけをお願いしました・・・感謝します!!
この「人食い問題」を、解決しない限り、私たちに安住の地はない!!













 <iframe id="google_ads_iframe_/6974/SankeiNews/Mobile_TextAd_1st_0" style="border: 0px; vertical-align: bottom; min-width: 100%;" tabindex="0" title="3rd party ad content" src="https://ec4bab256a97f97fef9ed705f5f17b3f.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-44/html/container.html" name="" width="0" height="36" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" data-is-safeframe="true" aria-label="Advertisement" data-google-container-id="5" data-load-complete="true"></iframe>
<iframe id="google_ads_iframe_/6974/SankeiNews/Mobile_TextAd_1st_0" style="border: 0px; vertical-align: bottom; min-width: 100%;" tabindex="0" title="3rd party ad content" src="https://ec4bab256a97f97fef9ed705f5f17b3f.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-44/html/container.html" name="" width="0" height="36" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" data-is-safeframe="true" aria-label="Advertisement" data-google-container-id="5" data-load-complete="true"></iframe>










/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/VJLYF4U3PRJHLC7K2YFGMHDZLI.jpg)








