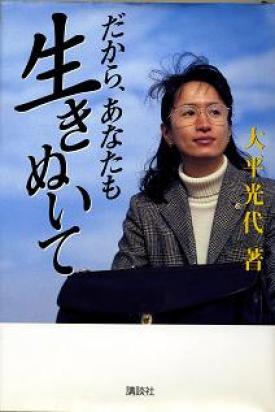日本の将来を担う若者たちの自殺が増えています!
以下転載
20代死因の半数が自殺。私たちに何ができるか?
小倉 広 | 作家、組織人事コンサルタント、心理カウンセラー
■ 20代、30代の死因の第一位は自殺
平成25年版の自殺対策白書によると、20代の死因の半数近くが自殺であることがわかりました。政府はこれを「深刻な状況」と指摘。「特に若年層に重点を置いた取り組みが急務」と強調しています。
若い世代の自殺問題は20代のみにとどまりません。20~39歳の各年代における死因の第一位も同じく自殺、となっています。(厚生労働省2011年「人口動態統計」より)。20代、30代ともに死因の第一が自殺、であることは尋常なことではありません。
この数字は、国際的に見ても突出しているようです。15~34歳の世代で死因の第一位が自殺となっているのは先進七カ国で唯一日本だけとのこと。政府が対策を急ぐのも無理はありません。
若い世代の自殺の原因を見てみると、「健康問題」が一位ではあるものの、その原因と推測される「就職の失敗」や「進路の悩み」「勤務問題」などが増加傾向にある、といいます。組織人事コンサルタントであり、心理カウンセラーでもある私としては、とても他人事とは思えません。では、私たちにいったい何ができるのでしょうか?
■ 失敗を過度に悲観してしまう20代、30代
人生に失敗はつきものです。失敗のない完璧な人間など一人もいません。しかし、就職の失敗や職場の人間関係の失敗など、渦中にいるとそれがわからなくなってしまうものです。特に20代、30代の若い世代では、人生経験が短い分、余計にその傾向が顕著のようです。「みんなはうまくやっているのに、自分だけが、なぜこんな目に……」と、過度に状況を悲観してしまうものです。
しかし、実際はそうではありません。順風満帆に見える人、悩みなどなさそうな人も皆、何かしらの問題を抱えているものです。そして、それがなくなることはありません。「問題をなくそうとする」のではなく、「問題といかに上手につきあっていく」か。それが「生きること」だと気づいたのは、私自身の場合、40歳を越えてからのことだったように思います。
しかし、それまでの間の20代、30代を通じて私はずっと生きることに辛さを感じ悩んでいたものです。
「なぜ自分ばかりにこんなに苦しみが訪れるのか……」と。そして、これらの問題をなくそう、と躍起になり、余計に苦しみを増大させていったのです。
■ 本当の意味で強い人間になる
そんな私が悩みや苦しみから抜け出す大きなターニングポイントになったのが、今も座右の銘にしている、ある言葉との出逢いです。私が敬愛する高名な心理学者であり元文化庁長官でもある故・河合隼雄氏の以下のような言葉です。
出典:「魂にメスはいらないーユング心理学講義ー」講談社+α文庫「自分をラッキョウの皮をむくみたいにむいていって見えてくるもののほうが、成熟という言葉には近いんじゃないかと思う」
自分を隠してコートを着込むのではなく、ラッキョウの皮をむくように自分をさらけ出して生きる。それこそが「成熟」である。そのメッセージは、格好悪いことや自らの失敗を隠して、コートを着込んでいた私にとって衝撃をもたらしました。以降、私は「ダメな自分」を隠すのはやめよう。「ダメな自分だってかわいいじゃないか。人間的じゃないか」と、少しずつ自分を許すことができるようになっていったのです。
■ 不完全を認める勇気を持ち、自己受容をする
心理学の世界において、これはまさに「自己受容」そのものです。
「ありのままの自分をすべて受け容れる」。
本当の意味で強い人間は、「ダメな自分」「カッコ悪い自分」「失敗だらけの自分」をすべて受け容れます。決して、それを隠したり、無理になくそうとしたりはしないもの。まずは、完璧ではない自分を認めて、その上でそれを克服するよう努力を始めるのです。
心理学者のアルフレッド・アドラーをこれを以下のように適切な言葉で表現しました。
「自分が不完全であることを認める勇気が必要だ」と。
そうです。本当に強い人間とは、自らを「完全であると装う」人間ではなく、自らが「不完全であることを認める」人間です。
「人間は不完全だからこそ努力するのである」同じくアルフレッド・アドラーの言葉です。
■ では、私たちに何ができるのか?
若年層の自殺問題に対して政府は早急に手を打つ、と宣言しました。では、私たちにいったい何ができるのでしょうか? 政府の対策を待っていればいいのでしょうか? 動きの遅い政府を批判すればいいのでしょうか? 国を動かせないもどかしさから、無力感を嘆いていればいいのでしょうか?
私はこう思います。私たち大人の一人ひとりが、自らのできる小さな範囲で若者たちに良い影響を与えるよう努力を続けることではないか、と。
組織人事コンサルタントであり、心理カウンセラーである私の仕事を例に取るならば、執筆講演活動を通じて良い影響を与えるよう努力する。若年層に対して「過度に悲観しないよう」「自分が不完全であることを認める勇気を持とう」と呼びかける。さらには、私自身が自らの失敗体験をさらけ出しつつ「自分が不完全であることを認める」見本を示し続ける。それこそが、私にできることではないか、と思うのです。
■ 小さな灯りを照らし続ける
一灯照隅、万灯照国(いっとうしょうぐうばんとうしょうこく)
比叡山延暦寺を開いた最澄の言葉です。一つの灯火は小さな一隅しか照らせないが、それに共鳴した人たちが現れ、一万の灯りになれば国全体を明るく照らすことができる、という意味です。
私たち大人が、20代、30代の若者に対してできること。それは小さな一灯を掲げることでしかないかもしれません。しかし、万灯を掲げることができないから、と言ってあきらめるのではなく、一灯を掲げ続けること。小さな自分の周囲の若者に良き影響を与えようと努力すること。
自分自身が「不完全であることを認める勇気」を持ち、失敗体験を語りながら見本となる努力をすること。それこそが、一灯照隅、万灯照国になるのではないでしょうか。
若年層の自殺問題に対して私たちができるささやかなことについて考えてみました。
作家、組織人事コンサルタント、心理カウンセラー
大学卒業後リクルート入社。組織人事コンサル室課長からベンチャー役員へ転身。コンサル会社社長を経て現職。あらゆる立場で組織を牽引。しかしリーダーシップ不足から組織を束ねることに失敗し二度のうつ病に。一連の経験を通じて「リーダーシップとは生き様そのものだ」との考えに至る。30代を救うメンターとしても知られる。著書『任せる技術』(日本経済新聞出版)『自分でやった方が早い病』(星海社新書)など約30冊。
以上。
夢も希望もない現在社会に、愛想をつかした若者たちは自ら自らの命を絶ちます!
これ以上の親不孝はありません!
自殺というのは、思ったよりも勇気が必要で大変なことなのですが、若者たちは自殺という道を選んでしまいます!
愚かなることこの上ありませんが、大人の責任は重大です・・・・・・!
死ぬ勇気があるのなら、自殺する前に042-361-9202にFAXして貰いたい!
まさか死ぬ勇気があって、FAXする勇気がないなんて言わせませんぞ!
諸君に、新天地を与えて、夢と希望を与えよう!
世界人類の平和と繁栄のために、命をささげればいい!