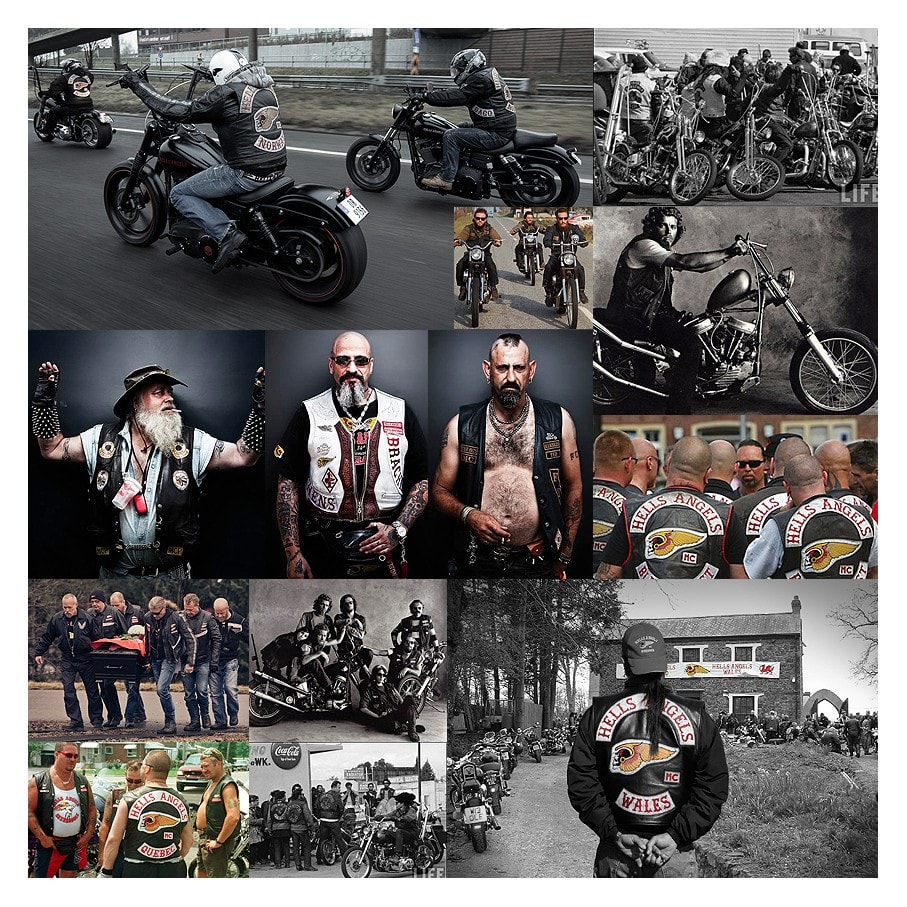これは全てユーザー側の「勝手なイメージ」です。(笑)
実は大した根拠なく、イメージでカワサキのバイクを「男カワサキ」と言ってるだけなんですよね。
ただし、70年代までさかのぼり「昔話」を掘り起こせば多少は理由があって、
カワサキと言えば無骨でデカく、とにかく「Z」シリーズを中心に大型バイクが主流だったことや、
国産の割に壊れるという伝説がそう言わせてると考えられます。
また、作れば売れると分かっていても、
あえて「スクーターを作らない」という姿勢もそのイメージを誘発してるとも言えます。
実際のカワサキ・バイクは80年代以降そのイメージを残してはいたものの、
他社と比べ圧倒的な「男らしさ」は無くなっています。
結局は「噂だけ」で実際は高性能で壊れにくくなっており、乗りやすいバイクも多く排出していましたからね。
カワサキ乗りの有名な話で「オイルが漏れてるのはオイルが入っている証拠だ!」という名言があります。(笑)
これは昔、カワサキ・エルミネーターに乗った誰かさんが言った言葉で、
この名言が「壊れる」=「カワサキ」=「男」という印象を世間に強く植え付けました。
しかし、オイル漏れはカワサキに限ったことではなく、
どのバイクでもそれなりに乗ってれば起こりうることです。
イメージが先行してるカワサキだったので「やっぱりカワサキかぁ」ってなってるだけなんですよね。
確かに「造りが雑」とか「新車でも当たり外れがある」とか言われてきました。
でもそれは大昔の話です。(笑)
例えば現在売られているカワサキのバイクを見て、
「男カワサキ」と感じられるバイクはごく少数です。
だってヤマハ「VMX1700」や、スズキ「GSX-R隼」だって十分「男らしい」ですからね。
結局、70年代にあった大型バイクに由縁の発端がある訳ですが、
もうそれ自体、伝説と言ってもいいほど昔の話です。
今のカワサキを「男カワサキ」と考える人は、大昔のイメージをいつまでも引きずってると言えます。
今は万人向けの高性能なバイクを作る「老若男女カワサキ」なんですよね!(笑)