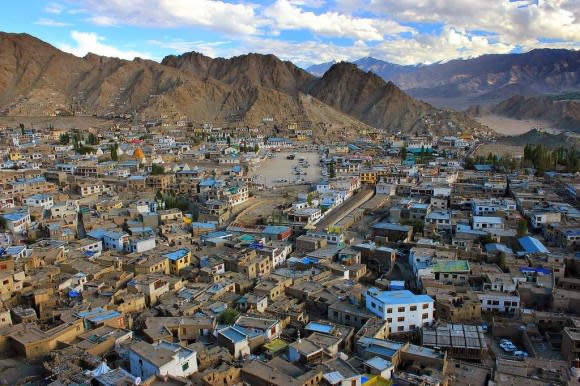おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

日本で言うところの神道とは、山や川などの自然や自然現象を敬い、それらに八百万の神を見いだす多神教を意味する。一神教が主である海外の人々にとっては、日本の神道は神秘と謎に満ち溢れているらしく、それ故に、こんな考察記事が特集されていた。
我々にとって、正月には神社に行って初詣するのはあたりまえの行事となっているが、そもそも神道に関してあまり深く考えたことはないのではないだろうか?日本を知りたいと思う外国人の向学心には頭が下がる思いである
以下は海外サイトが特集していた、外国人による「神道」に関する10の考察である。巫女に関しての記述とか、いったい何の文献を参考にしたのかも気になるところだ。
”神道とは、日本のおもな宗教のひとつ。だが多くの点で、単なる宗教以上の意味があり、日本文化の基盤となっている。古代日本人の自然を崇める慣わしから生まれ、礼拝も、聖典も、創造主もない。自然全体を受け入れるためか、どんな宗教の信者でも参加できる、ほかの宗教とは一線を画す独特な信仰である。”
10.神

神道における神は、やおよろずの神と言われ、漢字で八百万の神と書き、あらゆるものに神が宿り、たくさんの神が存在するという意味である。日本人は昔から、風や火などの自然の力、動物、山、滝などの風景に霊性を感じ、畏敬の念をこめてこれを擬人化した。
人間でさえ、立派で高潔な生き方をした徳のある者は死後、神として崇められる。ほかの宗教の神との大きな違いは、神道の神は完璧で絶対的な存在ではないということだ。優しく寛大かと思うと、破壊的で暴力的な面もあり、自然の恵みと猛威という二面性によく似ている。
9.太陽神、天照大神(アマテラスオオミカミ)

神道の神の中でも特に重要なのが天照大神だ。父イザナギがイザナミを探して黄泉の国を訪ね、戻ってきて身を清め、左目を洗ったときに生まれたという。イザナギは天照の温かく眩いばかりの光を見て、彼女に天上の世界、高天原を治めさせた。天照はきょうだいたちと一緒に古代日本を創造し、孫のニニギを地上に送って使者とした。天照はニニギを通して天皇家に剣、玉、鏡を贈り、以来、これらは日本の皇室の証である三種の神器となった。
8.稲荷

天照が世界を照らし、稲荷がその恩恵を与える。米、酒、繁栄、狐、刀鍛冶、商売の神さまで、日本全国75000の神社のうち32000以上に稲荷の名前がついている。近頃はその神秘性から狐の形として表されることが多く、稲荷神社の入り口には二体の狐の像が鎮座し、神社を守っている。総本社は京都の伏見稲荷で、奥社へと導かれる参道には、おびただしい数の朱の鳥居が赤いトンネルをつくっているのが特徴的だ。
7.伊勢神宮

天照大神に捧げられた社で、日本の神道の神社の中でもっとも神聖な場所。約120の社や建物でできていて、内宮、外宮という重要な社がある。建立は5世紀だが、20年ごとに新しい材料を使って、昔ながらの建築方法で、古い社の隣に新しく建て直す式年遷宮という儀式が行われる。新しいものが完成すると、古い社は壊され、その場所には大きな白い玉砂利が敷かれ、中心に高い柱が建てられ、まわりを保護して、次の式年遷宮が
始まる20年間、その区画を不可侵なものにしておく。
6.清らかさ

神道の考え方の中心は、心、体、精神の清らかさだ。神道全般の根幹をなすもので、玄関で靴を脱ぐことから、死者の臓器を提供するのを嫌がることまで、日本人の日々の生活の中でも見ることができる。罪という言葉は、英語でsinと訳すが、日本語の定義では、精神的な罪だけでなく、実際に不潔だったり、病気や死などで体が汚染されていることまで、もっと広い意味をもつ。
これらの理由から、清めの儀式は体や精神を清浄にすることへ発展した。一番簡単で一般的な方法は手水(ちょうず)といって、神社にお参りする前に手や顔を洗うことだ。ほかには、体だけでなく、地面に塩をふりかけて、穢れを祓う修祓(しゅばつ)という清めがある。相撲の力士が取り組み前に塩で土俵を清めるのもこれである。
5.神主と巫女

毎週、礼拝がないといっても、神道の神主はとても忙しい。参拝者に対応し、儀式を執り行い、地元の祭りや祝日に駆り出され、神社を保っていかなくてはならない。しかし、ほとんどの神主はパートタイムで、巫女と呼ばれる若い女性が補佐している。今は彼女たちはたいてい高校生のアルバイトか、神主の親戚である。昔から巫女は、神楽と呼ばれる舞を披露して神をもてなしたり、トランス状態になって霊と交信したりとその役割は大きい。
4.おみくじ、お守り、絵馬

神社ではたいていこれらを売っていて、参拝者が買い求める。おみくじは、ランダムに引いて吉凶を占うくじで、引いたくじは近くの木に結びつけるのが習慣だ。
お守りは常に身近に持って、神の加護を受けるための護符や魔除けのこと。悪い運から身を守ってもらい、病気の治癒や幸運を願って求める。ご利益のタイムリミットが過ぎ
ると、受けた神社に戻してお焚きあげしてもらい処分する。絵馬は、願い事を書いて神に見てもらうために吊るしておく木の板のこと。
3.神道と仏教の混在

6世紀、中国や韓国から仏教が日本に伝来した。これを受け入れるかどうか、問題になったが、大量の渡来人たちの流入で、その影響は急速に国中に広がった。だが、日本が完全に仏教に改宗したわけではなく、その教えは神道と微妙にブレンドしていった。神道の神社の隣に仏教寺院が建ち、神が仏陀を守っていると言われた。
明治時代に、神道を国の宗教と定め、神仏を分離しようとしたが、結局は国民が仏教を残すことを要求した。
2.新年

神道のもっとも重要な祝日は、新年の祝いだ。年が明けるまでに家の大掃除をして一年の汚れを落とす。大晦日には、仏教の寺社が人間の煩悩(罪)である108回の鐘を鳴らし、最後の108回目はちょうど午前0時になるようにする。年の始めの三が日は、人々は集まって、飲み食いして新年を寿ぎ、神社に初詣に行く。この時期だけで約9800万人もの人が繰り出し、そのうち300万人が新たな年の幸運を祈って、東京の明治神宮に詣でる。
1.神の系譜

日本の皇室は、太陽神天照大神につながる系統を主張してきた。明治時代、外国の影響を排除する政府の目的の一環として、神道が国家の宗教として定められた。天皇は国の支配者としてだけでなく、神道の長としての立場を確立するために、神との系統を利用したのだ。
第二次大戦中、世論の支持を得るため、神道には国家主義者のプロパガンダが織り込まれた。敗戦後、マッカーサー元帥が出した神道指令(Bunce Directive)によって政教は分離され、天皇は神にあらずと定めた。これにより、神道と国家主義者の政治は切り離され、国民個人個人が自由に信仰する宗教へと戻された。
via:
listverse
☆俺の家は神道だが、知らんことばかりじゃ!勉強せにゃならん!!
おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!