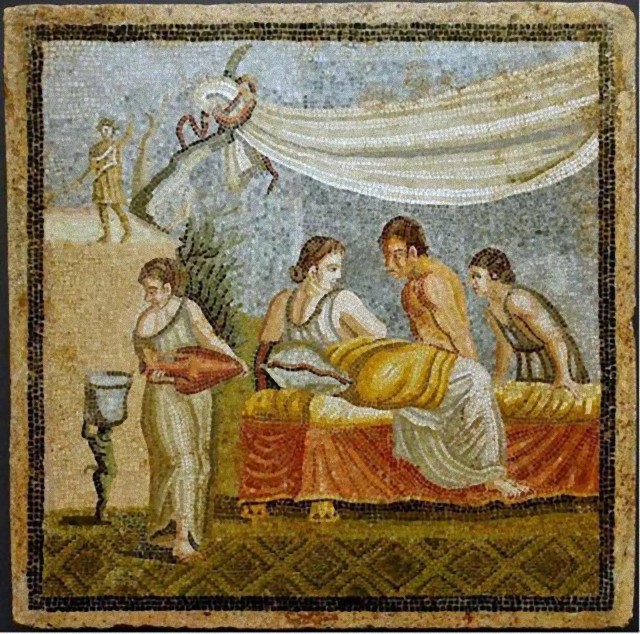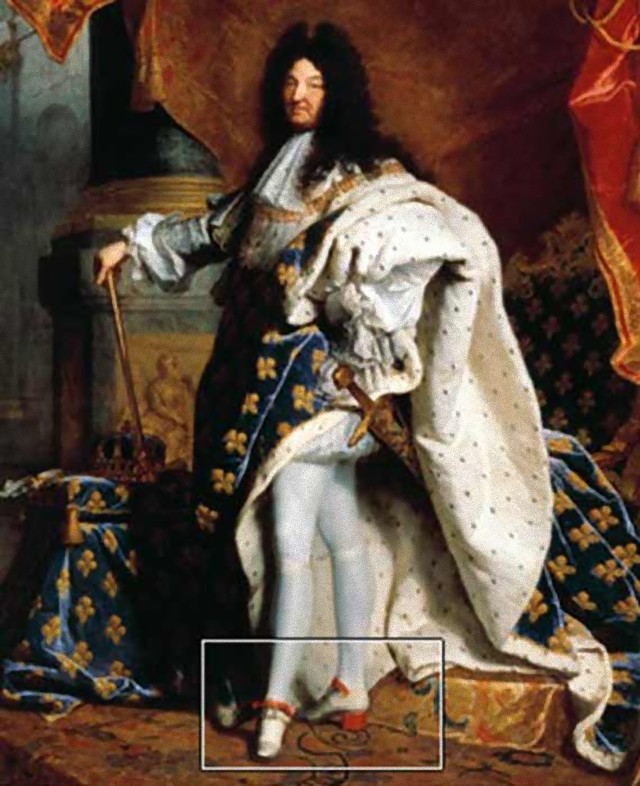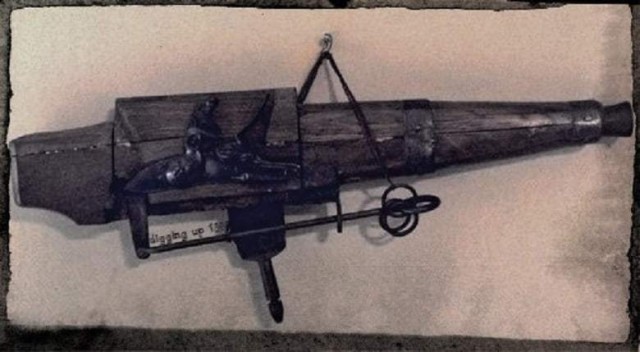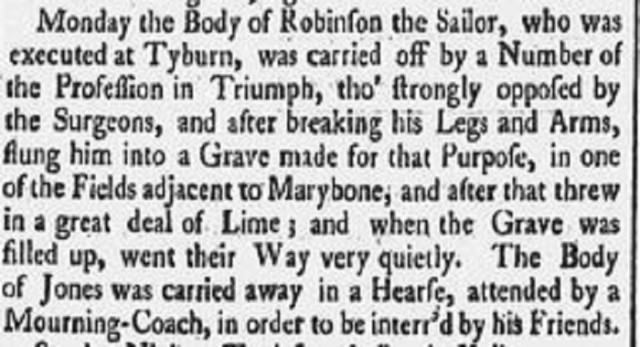雇用大崩壊、大失業時代の前に手軽に始めてみませんか?
MLMではない格安副業です。
100種類以上の豊富な商材を、ワンストップで取り扱えるビジネスパートナーが全国で活躍中。
↑ ↑ ↑
クリックしてね!

動物の世界では強いオスの方がメスにモテるイメージがある。これまでの研究では、家畜として飼われているヒツジの間では、支配的なオスの方がより多くのメスと交尾できると考えられていたが、実際にはそうではなかった。
『AppliedAnimal Behavior Science』に掲載された研究によると、羊のメスにオスを選ぶ選択権を与えたところ、メスが選んだのは、優位を誇る支配的なオスではなく、順位の低い優しいオスであることがわかったという。草食の羊の好みのタイプも、また草食系ということになる。
これまでの研究で、支配的なオスは、その押しの強さでメスにより多くアプローチし、おとなしいオスよりも、荒々しい交尾行動をとる傾向があることがわかっている。
また、あまりに支配力が強すぎるせいか、旺盛な生殖行為が過剰になりすぎて、精子が不足してしまうオスもいることもわかっている。
このように強すぎる支配力は、精子不足のせいでなくても群れを危険にさらすこともあると動物科学者は指摘する。
近親交配が進んで、弱い個体ばかりになってしまう可能性につながるからだ。

メキシコのエスタド・デ・モレロス自治大学(UAEM)とウルグアイのラ・レプブリカ大学の研究チームは、支配的なオスの精子が足りなくなったとき、メスはあまり支配的でない、つまり羊カーストの低いオスのほうになびく傾向があることに気がついた。
それを調べるために、囲いの片側に支配的なオスのヒツジを、反対側に従順なオスのヒツジを一頭づつつないでみた。
そして、発情期のメスのヒツジ7頭を柵の中に入れ、交尾の相手としてどちらのオスを選ぶか観察した。異なるグループのメスを使って、この実験を何度も繰り返してみた。
すると、実験数の4分の1で、メスが支配的なオスをまったく選ばなかったことがわかった。
メスが支配的なオスとを選んだ場合でも、おとなしいオスを相手にする場合に比べて、生殖行為数は少なく、実際の交尾の数も遥かに少なかった。
メスは、おとなしいオスと一緒に過ごすのを楽しんでいるかのように見えたという。支配的なオスと過ごすよりも、おとなしいオスと過ごす時間のほうが平均で3倍も多く、交尾にかける時間も2倍長かったようだ。

進化の過程で、近親交配を防ぐために、メスはあまり支配的でないおとなしいオスを選ぶようプラグラミングされてきたのではないかと研究者は言う。
というかなにより、メスたちは、乱暴なオスではなく、より穏やかに優しくアプローチしてくれるオスのほうを好んでいるようにも見えるという。
References:Female sheep found to prefer less dominant males when mating/
☆草食系でも一応アプローチはすんねんなぁ!
優良出会い系サイトの紹介です!
雇用大崩壊、大失業時代の前に手軽に始めてみませんか?
MLMではない格安副業です。
100種類以上の豊富な商材を、ワンストップで取り扱えるビジネスパートナーが全国で活躍中。
↑ ↑ ↑
クリックしてね!
MLMではない格安副業です。
100種類以上の豊富な商材を、ワンストップで取り扱えるビジネスパートナーが全国で活躍中。
↑ ↑ ↑
クリックしてね!

photo by Pixabay
動物の世界では強いオスの方がメスにモテるイメージがある。これまでの研究では、家畜として飼われているヒツジの間では、支配的なオスの方がより多くのメスと交尾できると考えられていたが、実際にはそうではなかった。
『AppliedAnimal Behavior Science』に掲載された研究によると、羊のメスにオスを選ぶ選択権を与えたところ、メスが選んだのは、優位を誇る支配的なオスではなく、順位の低い優しいオスであることがわかったという。草食の羊の好みのタイプも、また草食系ということになる。
支配力の強いオス羊の交尾行動
これまでの研究で、支配的なオスは、その押しの強さでメスにより多くアプローチし、おとなしいオスよりも、荒々しい交尾行動をとる傾向があることがわかっている。
また、あまりに支配力が強すぎるせいか、旺盛な生殖行為が過剰になりすぎて、精子が不足してしまうオスもいることもわかっている。
このように強すぎる支配力は、精子不足のせいでなくても群れを危険にさらすこともあると動物科学者は指摘する。
近親交配が進んで、弱い個体ばかりになってしまう可能性につながるからだ。

photo by iStock
羊のメスはおとなしいオスを好むことが判明
メキシコのエスタド・デ・モレロス自治大学(UAEM)とウルグアイのラ・レプブリカ大学の研究チームは、支配的なオスの精子が足りなくなったとき、メスはあまり支配的でない、つまり羊カーストの低いオスのほうになびく傾向があることに気がついた。
それを調べるために、囲いの片側に支配的なオスのヒツジを、反対側に従順なオスのヒツジを一頭づつつないでみた。
そして、発情期のメスのヒツジ7頭を柵の中に入れ、交尾の相手としてどちらのオスを選ぶか観察した。異なるグループのメスを使って、この実験を何度も繰り返してみた。
すると、実験数の4分の1で、メスが支配的なオスをまったく選ばなかったことがわかった。
メスが支配的なオスとを選んだ場合でも、おとなしいオスを相手にする場合に比べて、生殖行為数は少なく、実際の交尾の数も遥かに少なかった。
メスは、おとなしいオスと一緒に過ごすのを楽しんでいるかのように見えたという。支配的なオスと過ごすよりも、おとなしいオスと過ごす時間のほうが平均で3倍も多く、交尾にかける時間も2倍長かったようだ。

photo by Pixabay
なぜメス羊は強いオスよりおとなしいオスが好き?
進化の過程で、近親交配を防ぐために、メスはあまり支配的でないおとなしいオスを選ぶようプラグラミングされてきたのではないかと研究者は言う。
というかなにより、メスたちは、乱暴なオスではなく、より穏やかに優しくアプローチしてくれるオスのほうを好んでいるようにも見えるという。
References:Female sheep found to prefer less dominant males when mating/
☆草食系でも一応アプローチはすんねんなぁ!
優良出会い系サイトの紹介です!
雇用大崩壊、大失業時代の前に手軽に始めてみませんか?
MLMではない格安副業です。
100種類以上の豊富な商材を、ワンストップで取り扱えるビジネスパートナーが全国で活躍中。
↑ ↑ ↑
クリックしてね!