テレビ日曜劇場の『御上先生』が終わった。初回は日本の教育に切り込んだドラマの印象だったが、回を重ねると何が主題なのか分からなくなった。私が高校生になったのは1960年、進学校だったので、大学入試に向けた授業が主だった。
なぜ勉強するのか、なぜ教師と生徒の交流は無いのか、なぜ校則があるのか、疑問ばかりだった。教師になって工業高校のデザイン科で教えることになった。この高校は伝統と自由が共存していて、楽しい毎日だった。
それでも日本の教育全体は、詰込みと画一化が主流で、成績を上げるために教師は奔走していると思われた。高校でも違反行為をした生徒に処分が行われたが、家庭謹慎や停学が生徒の教育になるとは思えなかった。
処分が報告される職員会議で、「教育の効果」を問うと、指導部に呼び出された。いくら説教されても、個々の子どもたちが尊重されているとは思えなかった。『御上先生』はクラスの大半が東大を目指すエリート校が舞台だったが、個々の生徒の考える力を育てようとしていた。
考える力とは何か、「それは論理的に思考することだ」と御上先生は言う。論理的思考は正しい結論を導き出すと言う。そこで、戦争はなぜ悪いと問うと、人を殺すから、人の幸せを奪うからと答えが出る。他国から攻撃されたら、どうするのかと問われると答えられなくなってしまう。
戦争を決めるのは政府である。その政府は選んだのは国民である。誰も戦争を望んでいないのに、戦争になってしまう。この仕組みを変えないと、戦争は無くならない。そんな現在、世界が直面する問題にまで進んで行った。
人々が思考を深めるために、情報の提供は極めて大切である。けれど、情報は人を傷つけることもある。それぞれが考えることが重要であると御上先生は言う。彼が文部省のトップになるか、あるいは総理大臣にでもならないと日本の教育は変わらないようだ。















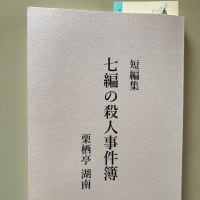








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます