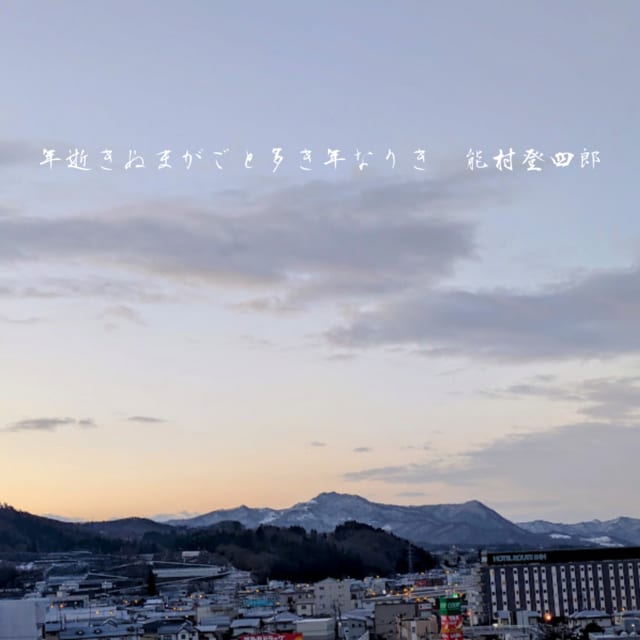今年になって山行は名所への旅という感が強い。新潟県村上市、日本海に面した古い街だ。市役所の近くに、村上城がある。臥牛山という標高135mの山に築城されている。上杉謙信が台頭する戦国時代の城である。山形で言えば千歳山に登るような気楽な散歩登山ができる。町並みは、古い町並みが残され、鮭が遡上してくる川でのサケ漁が行われ、鮭の寒風干しが名産になっている。
1667年に落雷により天守が消失、その後城主が次々と変わり、いまだに天守閣が再建されていない。こ山道はほとんど石畳が敷かれ、登りやすくなっている。道脇にエンレイソウ、カタクリ、シラネアオイなど山の花が咲き乱れ、石垣の上には桜の大木が今を盛りと咲いていた。小雨のなか、本来見えるはずの日本海は雲のような霧にさえぎられている。地形で海を想像してみる。参加者9名、一行は珍しい花を探し、その特定に余念がない。場所を変えて羽黒神社。階段の先の神社も桜が満開。しばらくぶりで、高低を伴った登山を思わせる歩きになった。臥牛山といい、羽黒神社も山形の山や山岳信仰がこの地でも共有されている懐かしがあった。

約2時間の名勝歩きを終えて、昼食は和食「ゆるり」。海の幸と新潟の米を使う海鮮丼。海の近くで食べる海鮮の新鮮さは格別だ。鮭の加工品売り場が食堂の隣にある。お土産に妻が好きな酒のカマ。以前、ここで作られた酒びたしをご馳走になったことがある。村上まで車で2時間、山歩き2時間、帰り道2時間。
gooブログのサービス終了が告知された。今日で開設から4776日、13年が経過したことになる。これを機会にブログの閉鎖が頭をよぎる。だが日々の暮らしで書いておこうと考えることのしばしば。生成AIの登場で書くことの新しいフェイズに入ったことへの興味もある。ここは他のサイトへ引っ越しして、当面継続することにした。サービスの終了は今年の12月、それまでにもっと多くの人から読まれるブログへのレベルアップも目指したい。