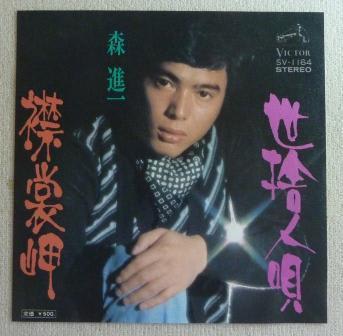これほど怖い思いをした山は記憶がない。何せ私が立っている両脇は鋭く切れ落ちていて、一歩踏み間違えれば奈落の底といった感じである。私はビビりまくりながら、這うようにして山頂を目ざした。
 ※ 黄金山山頂から暑寒別岳など増毛山地を遠望したパノラマ写真です。
※ 黄金山山頂から暑寒別岳など増毛山地を遠望したパノラマ写真です。
「黄金山(こがねやま)」というと、国道231号線からもその特異な山の形が望まれ、いつか登ってみたいなぁ、と思っていた山だった。高さは739mとそれほどでもないのだが、先行者の記録を読むと、かなり怖い山のようだった。
何せ百戦錬磨のsakag氏が「これまでで最も怖かった印象が強かった」とまで記すほどなのだから…。
この山は、その山容から別名「黄金富士」、「浜益富士」とも呼ばれているそうだ。
 ※ 国道231号線から見える「黄金山」です。
※ 国道231号線から見える「黄金山」です。
 ※ 国道から離れ、もう少し近づいたところから見た「黄金山」です。
※ 国道から離れ、もう少し近づいたところから見た「黄金山」です。
今日(5月15日)、早起きをして黄金山がある石狩市浜益地区を目ざした。我が家から片道85km、2時間かけての山行がはたして札幌近郊と言えるかどうかは疑問府つくところだが、まあ敢えて近郊としておこう。
朝5時に自宅を発ち、7時に登山口に着くと、すでに3台の車が駐車していた。
この日は、黄金山の登山開きが予定されていたが、さすがにこの時間にはそうした関係者の姿は見えなかった。
 ※ 黄金山登山口に建つ立派な水洗トイレです。
※ 黄金山登山口に建つ立派な水洗トイレです。
 ※ 黄金山の登山口です。
※ 黄金山の登山口です。
立派なトイレが完備された登山口を7時05分に出発した。上りはじめは沢を経過しながらも穏やかな上りが続く。登山道の脇には春の山らしく、いろいろな山野草が花を付け、目を楽しませてくれる。
私の足で20分後、新道と旧道の分岐点に着いた。私は特に知識もなかったので、上りに新道を、そして下りに旧道を行くことにした。(これが間違いだった…)
 ※ 登り始めは、まあ普通の登山道といった感じでした。
※ 登り始めは、まあ普通の登山道といった感じでした。
 ※ 途中、これから向かう黄金山山頂が木々の間から見え隠れしていました。
※ 途中、これから向かう黄金山山頂が木々の間から見え隠れしていました。
 ※ 新道、旧道の分岐点です。距離的にはほとんど同じくらいのようです。
※ 新道、旧道の分岐点です。距離的にはほとんど同じくらいのようです。
新道もしばらくは穏やかな上りだったが、やがて山容でも分かる急斜面に取り付くと、凄い登りが待っていた。もう見上げるばかりの上りが連続しているのだ。
写真ではイマイチその感じが分からないが、かなりな急登で、脇に張られたロープに掴まり、木の枝や幹に掴まりながら高度を上げていった。
あまりに急斜度のせいか、それとも私が最近自分の体力の衰えを十分自覚してきて無理しなくなったせいか、体力に合った上り方をしたので、それほど辛い思いはせずに上りつづけることができた。
 ※ 徐々に登山道が険しくなってきました。
※ 徐々に登山道が険しくなってきました。
 ※ 写真ではやや平板に見えますが、かなりの斜度で登り続けねばなりませんでした。
※ 写真ではやや平板に見えますが、かなりの斜度で登り続けねばなりませんでした。
 ※ 写真のような梯子を使って登るところも…。
※ 写真のような梯子を使って登るところも…。
 ※ 典型的な岩場です。ロープを掴み、木の枝や幹につかまりながら登り続けました。
※ 典型的な岩場です。ロープを掴み、木の枝や幹につかまりながら登り続けました。
旧道との分岐点から55分後、再び旧道との合流点があった。
この急登部分をこの山を熟知されているらしい若いカップルと前後しながら登ってきたのだが、その彼が「この後に怖いところが待っていますよ」と教えてくれた。
合流点からさらに上りつづけると、大きな岩場に出た。左手に岸壁が垂直に切り立っている。下を見ると目も眩みそうなほど垂直に切れ落ちている。
風も強かった。私は岩場に座り込んで、まずウィンドブレーカーを羽織り、キャップを飛ばされないようにしっかりカバーした。
そこからの岩場は掴まるものもなく、バランスを崩したら大変と思い、岩場を這って進んだ。もうまったくのへっぴり腰である。
情けないのだが、もしバランスを崩したら、それを瞬時に立て直す筋力も瞬発力もすでに自分からは失われたと思っているため、余計に怖さを感ずるのだ。
 ※ この岩場に左から回り込むのです。
※ この岩場に左から回り込むのです。
 ※ この写真は反対側から、下山する人を撮ったのですが、その険しさを分かっていただけると思います。
※ この写真は反対側から、下山する人を撮ったのですが、その険しさを分かっていただけると思います。
 ※ 第一の岩場から、男性が立っている山頂に至る岩場を目ざします。
※ 第一の岩場から、男性が立っている山頂に至る岩場を目ざします。
 ※ 怖い思いをしながら、ようやくたどり着いた黄金山山頂です。
※ 怖い思いをしながら、ようやくたどり着いた黄金山山頂です。
ほんとうに恐る恐るといった感じだった。
8時35分、なんとか黄金山山頂に立つことができた。登頂に1時間30分を要したことになる。健脚の人であれば1時間程度の山なのだが…。
山頂は風は強かったが、見晴らしは素晴らしかった。360度遮るものがなく、遠く浜益の市街地や日本海、反対側にはまだ雪を被った暑寒別岳など増毛山地が遠望できた。
 ※ 最初の写真とは反対側の日本海方面を写したパノラマ写真です。正面に見える小さな集落が浜益集落です。その向こうが日本海。
※ 最初の写真とは反対側の日本海方面を写したパノラマ写真です。正面に見える小さな集落が浜益集落です。その向こうが日本海。
私の前後して上ってきた男性氏に問うた。「旧道の下山はどうでしょうか?」と問うと、「う~ん。難しいところがありますね」ということだった。
私の試練はまだまだ続いた。旧道の下山道はまたまた私を震え上がらせたのだった…。
その下山編は明日レポします。