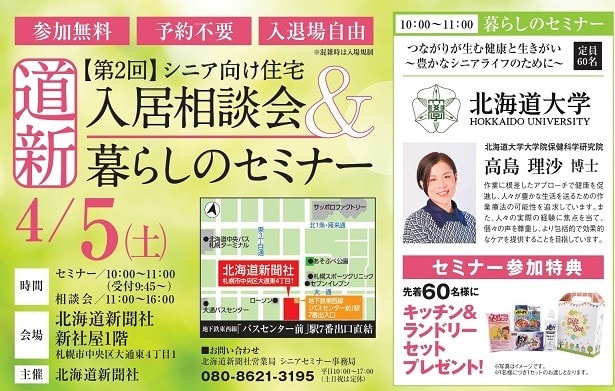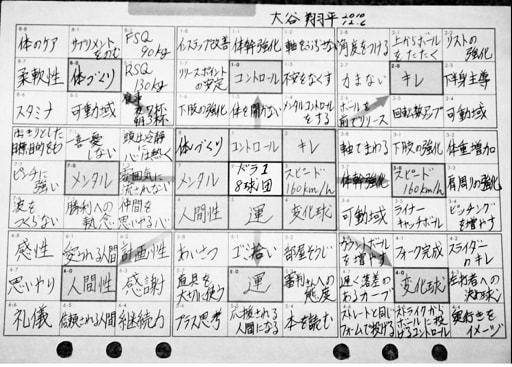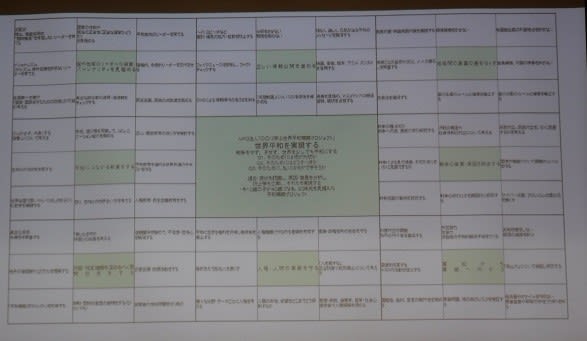著者の門井慶喜氏は「一から街ができる姿を描きたかった」と語った。一方、秋元札幌市長は「第二の開拓時代を率先したい」と述べた。お二人の「札幌誕生」にまつわるあれこれを興味深く聴くことができた対談だった。

本日午後、札幌コンベンションセンターにおいて「『札幌誕生』刊行記念 札幌市長・秋元克広さん×門井慶喜さん 特別対談」が行われたので参加し、お二人のお話に耳を傾けました。司会は元HBCアナウンサーの鎌田強さんが務めました。

※ 対談前のフォトセッションでのお二人です。
お二人の話を一生懸命にメモしながら聴いたのですが、その中から印象的な言葉を掘り起こしてみたいと思います。
まず、門井慶喜さんの言葉です。
門井さんの著書に「家康、江戸を建てる」があるが、家康が江戸を創ったときは、江戸はすでに住んでいた人たちがいる中で、江戸の街を創っていったが、札幌は一部アイヌの方々がコタンをつくってはいたものの、ほぼ何もない状態から街づくりが始まった。門井氏はそうした何もない原野を「一から街ができる姿を描きたかった」と語りました。

※ 著書について、札幌について語る門井慶喜氏です。
著書に出てくる具体的な場面に関して門井氏は…、
◇札幌農学校は、単なる農学を教えるだけではなく、宗教も含めて総合的な教育が展開されたことで多分野のリーダーを育成した。
◇島義勇が構想し、実現した碁盤の目状の札幌の街は、自分たちより他所から来た人たちを優遇する街に映る。
◇創成川(当時の大友堀)は、内陸都市である札幌にとって、水運を担い、札幌が発展するうえで大きな精神的位置づけがされる存在である。
◇札幌はいまだに発展中であるが、人口減少時代を迎えようとしている今日、二宮尊徳(その弟子である大友亀太郎)の取り組んだことは、それを克服するモデルとなり得る。
◇島義勇が短期間ではあったけれど、多くの仕事をし札幌人に讃えられたのは、明治政府から遠い蝦夷に派遣されたことによる「後がない」という思いと、島義勇の人間的魅力が部下に大きな影響を与えたことよる。
などなど、作品の興味深い背景についてお話されました。
一方、秋元札幌市長は…、
◇ご自身の出身校である北海道大学の前身の札幌農学校の先輩たちについて、「日本を支えるような人材を輩出した学校であり、先輩というよりは偉人たちを多く輩出した学校」だったと述べられた。
◇碁盤の目状の札幌の街については、昔も現代もイメージの違いはなく、伸びていく素地があるイメージである。
◇創成川(大友堀)は、住民の生活、産業などに大きく関わり、水路として石狩川と繋がり水運の通路として大きな役割を果たした。
◇これからの札幌、北海道は、国防、エネルギー、食糧といった面で日本の中でも重要な位置を占めている。そういう意味で「第二の開拓時代」を迎えているとも云える。
◇また、人口減少時代を迎え、人手不足などが懸念されるが、DX技術などを駆使して解決してゆきたい。
◇「札幌誕生」は一気読みするほど楽しく、また参考になった。世界のユートピアを目ざして都市づくりに邁進したい、と語りました。
著書に出てくる具体的な場面に関して門井氏は…、
◇札幌農学校は、単なる農学を教えるだけではなく、宗教も含めて総合的な教育が展開されたことで多分野のリーダーを育成した。
◇島義勇が構想し、実現した碁盤の目状の札幌の街は、自分たちより他所から来た人たちを優遇する街に映る。
◇創成川(当時の大友堀)は、内陸都市である札幌にとって、水運を担い、札幌が発展するうえで大きな精神的位置づけがされる存在である。
◇札幌はいまだに発展中であるが、人口減少時代を迎えようとしている今日、二宮尊徳(その弟子である大友亀太郎)の取り組んだことは、それを克服するモデルとなり得る。
◇島義勇が短期間ではあったけれど、多くの仕事をし札幌人に讃えられたのは、明治政府から遠い蝦夷に派遣されたことによる「後がない」という思いと、島義勇の人間的魅力が部下に大きな影響を与えたことよる。
などなど、作品の興味深い背景についてお話されました。
一方、秋元札幌市長は…、
◇ご自身の出身校である北海道大学の前身の札幌農学校の先輩たちについて、「日本を支えるような人材を輩出した学校であり、先輩というよりは偉人たちを多く輩出した学校」だったと述べられた。
◇碁盤の目状の札幌の街については、昔も現代もイメージの違いはなく、伸びていく素地があるイメージである。
◇創成川(大友堀)は、住民の生活、産業などに大きく関わり、水路として石狩川と繋がり水運の通路として大きな役割を果たした。
◇これからの札幌、北海道は、国防、エネルギー、食糧といった面で日本の中でも重要な位置を占めている。そういう意味で「第二の開拓時代」を迎えているとも云える。
◇また、人口減少時代を迎え、人手不足などが懸念されるが、DX技術などを駆使して解決してゆきたい。
◇「札幌誕生」は一気読みするほど楽しく、また参考になった。世界のユートピアを目ざして都市づくりに邁進したい、と語りました。

※ サイン会の様子です。
1時間という対談時間はとても短く感じられるほど、お二人のお話には魅せられました。
対談後には、予想されていたとおり門井慶喜氏のサイン会が催され、私も持参した「札幌誕生」の中表紙に、門井氏自慢(?)の万年筆で達筆のサインを頂いてきました。
1時間という対談時間はとても短く感じられるほど、お二人のお話には魅せられました。
対談後には、予想されていたとおり門井慶喜氏のサイン会が催され、私も持参した「札幌誕生」の中表紙に、門井氏自慢(?)の万年筆で達筆のサインを頂いてきました。

※ いただいた門井氏のサインです。(白丸の部分は私の名前を記していただきました)