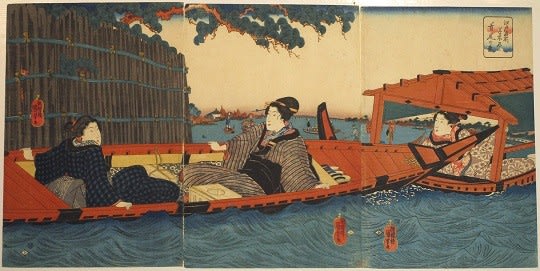札幌の食の特色というと ‟ビール” ‟ラーメン” そして ‟ジンギスカン” となると講師は云う。その特色ある食の歴史、特徴を知り、大いに売り込むべきと講師は強調された。札幌の‟ビール” ‟ラーメン” そして ‟ジンギスカン” の歴史とは?
昨日午後、北海道生涯学習協会が主催する「ほっかいどう学 かでる講座」の第2回講座が開講され受講しました。
今回の講師は、まち歩き団体Discover EZOの代表・伴野卓磨氏、テーマは「北海道のおいしい歴史物語~ビール・ラーメン・ジンギスカンはどう生まれたか?~」でした。
伴野氏は三つの食品について、実によく調べられて私たちに分かりやすく伝えてくれました。
昨日午後、北海道生涯学習協会が主催する「ほっかいどう学 かでる講座」の第2回講座が開講され受講しました。
今回の講師は、まち歩き団体Discover EZOの代表・伴野卓磨氏、テーマは「北海道のおいしい歴史物語~ビール・ラーメン・ジンギスカンはどう生まれたか?~」でした。
伴野氏は三つの食品について、実によく調べられて私たちに分かりやすく伝えてくれました。

※ 講演をする伴野卓磨氏です。
まずビールについてです。
札幌のビールを製造することになったそもそものキッカケは、明治初期(明治4年)にお雇い外国人の一人として来道したトーマス・アンチセルが鉱山調査をしていた際に岩内町で野生のホップが自生していたことを発見したのが始まりだと言われているそうです。
それからも札幌におけるビール製造が始まるまでには幾多の物語があり、伴野氏は詳しく、つまびらかに説明していただきました。その全てを記すことは私には荷が勝ち過ぎますので割愛させてもらいます。
結局、野生ホップの発見から5年後の明治9年、プロデューサー村橋久成、ビール製造責任者はドイツでラガービールの製造を学んだ中川清兵衛によって「開拓使麦酒醸造所」が開業しました。
その後も、札幌のビールは官製から民製に移るなどの歴史を経る中で、何度もの危機を迎えながらもその都度克服して現在に至っているとのことです。
続いてラーメンです。
札幌におけるラーメンの始まりは、大正11年に北大正門前に出店していた中華料理店「竹家食堂」で出していた「肉絲麺(ロゥスーミェン)」といわれています。この料理を奥さんが日本人に分かりよいように「拉麺(ラーメン)」と呼んでいたとも伝えられています。
札幌でラーメンが本格的に普及したのは戦後だと言われています。戦後、満州などから引揚者が薄野に屋台をつくって、豚骨から煮だした濃いスープが現在のラーメンの源流と言われているそうです。
その後、味噌ラーメンの開発、さらには札幌のラーメンを月刊誌「暮らしの手帳」が紹介することによって、札幌のラーメンは全国に知られることになったということです。
最後はジンギスカンです。
もともと日本には羊の肉を食する習慣はなかったと言われています。
それが何故、北海道で食されるようになったかというと、戦前に軍服用に羊毛生産として羊の飼育が北海道で盛んになったそうです。特に、滝川、札幌、月寒などに種羊場ができ、それらの地域で羊肉が食べられるようになったと言われています。
ところでジンギスカンの食しかたには大きく二つの食し方がありますが、札幌や月寒、あるいは沿岸部では生の羊肉と野菜を一緒に焼いて、別皿のタレに付けて食べる「後付けジンギスカン」が主流でした。
一方、滝川など内陸部では、あらかじめ羊肉をタレで味付けをして野菜と一緒に煮込むにようにして焼く「味付けジンギスカン」が主流となり、現在に至っています。
現在の札幌ではどちらも食することができるようですが…。
まずビールについてです。
札幌のビールを製造することになったそもそものキッカケは、明治初期(明治4年)にお雇い外国人の一人として来道したトーマス・アンチセルが鉱山調査をしていた際に岩内町で野生のホップが自生していたことを発見したのが始まりだと言われているそうです。
それからも札幌におけるビール製造が始まるまでには幾多の物語があり、伴野氏は詳しく、つまびらかに説明していただきました。その全てを記すことは私には荷が勝ち過ぎますので割愛させてもらいます。
結局、野生ホップの発見から5年後の明治9年、プロデューサー村橋久成、ビール製造責任者はドイツでラガービールの製造を学んだ中川清兵衛によって「開拓使麦酒醸造所」が開業しました。
その後も、札幌のビールは官製から民製に移るなどの歴史を経る中で、何度もの危機を迎えながらもその都度克服して現在に至っているとのことです。
続いてラーメンです。
札幌におけるラーメンの始まりは、大正11年に北大正門前に出店していた中華料理店「竹家食堂」で出していた「肉絲麺(ロゥスーミェン)」といわれています。この料理を奥さんが日本人に分かりよいように「拉麺(ラーメン)」と呼んでいたとも伝えられています。
札幌でラーメンが本格的に普及したのは戦後だと言われています。戦後、満州などから引揚者が薄野に屋台をつくって、豚骨から煮だした濃いスープが現在のラーメンの源流と言われているそうです。
その後、味噌ラーメンの開発、さらには札幌のラーメンを月刊誌「暮らしの手帳」が紹介することによって、札幌のラーメンは全国に知られることになったということです。
最後はジンギスカンです。
もともと日本には羊の肉を食する習慣はなかったと言われています。
それが何故、北海道で食されるようになったかというと、戦前に軍服用に羊毛生産として羊の飼育が北海道で盛んになったそうです。特に、滝川、札幌、月寒などに種羊場ができ、それらの地域で羊肉が食べられるようになったと言われています。
ところでジンギスカンの食しかたには大きく二つの食し方がありますが、札幌や月寒、あるいは沿岸部では生の羊肉と野菜を一緒に焼いて、別皿のタレに付けて食べる「後付けジンギスカン」が主流でした。
一方、滝川など内陸部では、あらかじめ羊肉をタレで味付けをして野菜と一緒に煮込むにようにして焼く「味付けジンギスカン」が主流となり、現在に至っています。
現在の札幌ではどちらも食することができるようですが…。

※ 伴野氏が提示してくれた「後付け」地域と、「味付き」地域の分布図です。
さて、タイトルの「そして売れ!」ということですが、講師の伴野氏はまち歩き団体Discover EZOの代表をされています。伴野氏は札幌の食ばかりではなく、札幌のさまざまな特色を取り上げ、それを深堀りすることで、札幌の魅力を発信できるのではないかと強調されました。
そして得た知識をもとに観光客などのガイドツアーとして自立できるガイドを育てたいと考えられていて、実際にその活動を実践に移されているとのことでした。
実際に実践されているパンフレットを拝見することができましたが、これまでボランティアさんたちが行っていたガイドツアーと比較すると割高に見えますが、内容が充実しているとしたら、私たち札幌人にとっても興味あるテーマのガイドツアーであれば参加してみたいなぁ、と思いました。
まち歩き団体Discover EZOの今後に注目したいと思います。
さて、タイトルの「そして売れ!」ということですが、講師の伴野氏はまち歩き団体Discover EZOの代表をされています。伴野氏は札幌の食ばかりではなく、札幌のさまざまな特色を取り上げ、それを深堀りすることで、札幌の魅力を発信できるのではないかと強調されました。
そして得た知識をもとに観光客などのガイドツアーとして自立できるガイドを育てたいと考えられていて、実際にその活動を実践に移されているとのことでした。
実際に実践されているパンフレットを拝見することができましたが、これまでボランティアさんたちが行っていたガイドツアーと比較すると割高に見えますが、内容が充実しているとしたら、私たち札幌人にとっても興味あるテーマのガイドツアーであれば参加してみたいなぁ、と思いました。
まち歩き団体Discover EZOの今後に注目したいと思います。