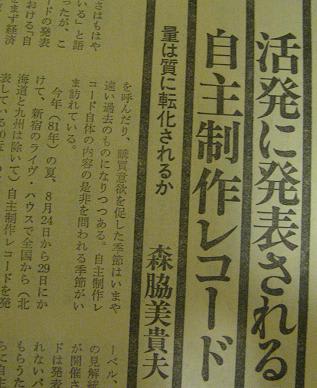【アラーキー 「東京物語」より】
1987年3月、何の運命か1つだけ偶然としか言いようの無い引っ掛かった大学合格。
では、1つの苦しみは終えたのか?
と言えば、ある種の意味ではそうだったが、周囲が迫ってくる幻覚に襲われることは終わっていなかった。
弛緩剤を呑むと、カラダのチカラが抜けて、ろれつも回らないようなラリった状態になる。
それが、ごまかしであり、本質的な解決で無いことは重々承知だった。
しかし、そうするしか方法は無かった。
他人をうらやんだ。
普通に過ごす人々を。
なぜ、自分だけが、こういう思考のスパイラルの穴に入り込んで出られないのか?
どうして、きちがいのような日常を、しらーっとした顔をして過ごせるのか?
本心から疑問に思った頃。
***
晴れて、何もしないでも良い状況は救いだった。
ただ、自分にとっての音楽シーンは、1986年に一旦終わっていた。
何もしないでも良い状況と同時に空っぽの時空を与えられた、
そんな感じがした。
肉感が無い、とでも言うのだろうか。

その中でもあらがいとして、毎日毎日絵を描いていた。
あらゆる道具を使って、手を汚した。
しかし、大して良いと思えるものは出来なかった。
それでも、毎日毎日描いた。

むかし、三ノ輪に住んでいた頃、物干しから下町の家並みと空を見ていたことを、よく想い出しては「あそこに戻りたい」と思った。
それは、かなわないことはわかっていたが。