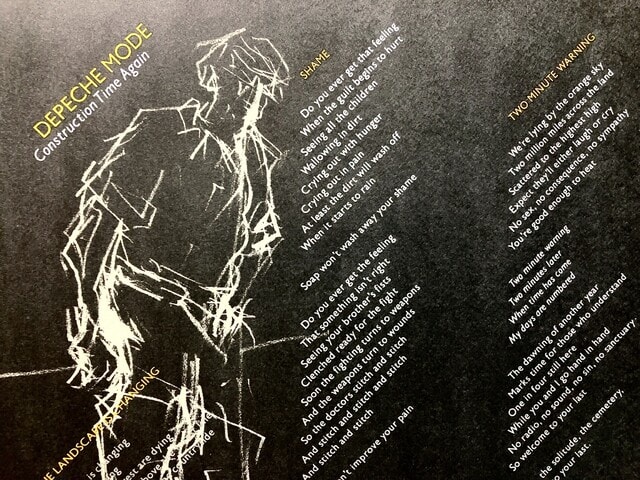本日も個人的備忘録。
今のじぶんは、光熱費の支払いすら困るくらいの“すずめの涙”程度の収入で生きている。
物価は高騰するは、医療費はかさむは・・・。毎月赤字で生きているこの数年。
しかし、そんな“カネ“のゼロの数ばかりながめ、プラス/マイナスにだけ注視して生きていてもまるで味わいの無いコスパ野郎の人生みたいで、”後は死ぬだけ”な生活になってしまう。ということで、出来るだけカネはあまり気にしないように、”まあ何とかな~るだろう~“と植木等ばりの適当さで生きている。結果がどうなるかは神のみぞ知る世界。。。
***
・・・絶望に満ちた現代のこのクニは、無理矢理祝日を動かして連休を増やしてきている。やたらクニが作り出したそんな最近の祝日や連休は、基本“カネ“を使わせるためにある。本来はそれに忠実に従い、カネを落としてくれる”正しい家族”だけがレジャーを楽しむ時間なんだろう。
自分みたいな貧乏人は小さい頃から”正しい家族”が行くようなレジャー場所など無縁で育った。昔の用語「ヨソはヨソ/ウチはウチ」ではないが、家族が全員でにこやかにどこかへ一緒に行く、なんていうこととは無縁であり、行きたくもなかった。一緒に行った数少ない機会も、全員がバラバラで、問題行動や喧嘩やいさかいなど、想い出すにも恥ずかしいありさまであった。

今の自分らはクニからすれば”正しい家族”ではない“まがいものの家族”。
どこか代表的なレジャー場所に行くことについて、大して価値を見い出していない者同士が集まった家族。まあそれでも、たまには”正しい家族“が行くような場所に行って、NHKニュース記事の映像のバックに流れるみたいな、そんな人たちがするような笑顔のふりをして楽しんでみるのも良いだろう。。。
ということで、・・・肺炎にやられてダウンしていた数週間を経て、治癒へ向かうさなか。。。この連休(13-15日)に”ちかてつ博物館“に行ってきた。入場料は、おとな一人当たり220円と懐に優しい。

実は、自分は小学1年生のときから小中9年間も越境入学を強いられ、地下鉄で下町から赤坂まで、蒼い顔でゲロを吐きながら1時間かけて通学していた。まだ身の回りもロクに分からない6歳児のときからのそんな通学経験によって、かなり長い間地下鉄に夢中な“ちかてつ少年”だった。
しかし、その割には”ちかてつ博物館“は初体験だった。
・・・というのも、この博物館が出来たのは1986年のこと。もう自分はすでに大きくなり、“ちかてつ少年”ではないところに居たからである。それでもいつかは一度は行ってみようと思いながら来られなかった博物館。。。
この博物館がある葛西駅という場所は、絶縁した会社に依存した社畜が多く住まう鬼門だが、そんなクソな悪縁は吹いて飛ばし、思い切って38年目にして初上陸してみた。





★本日の一曲
この曲は1990年当時、小林克也さんサイドがnack5で放送していた“続・スネークマンショー”でコントのはざまに掛かったもの。80年代から90年代に向け学会等新興宗教がバブルの如く巨大に膨張し、勢力を伸ばしていた。そんな怪しい時代の中、空気を引き裂くように、あえて軽~く安易な歌い方でもって 宗教(あるいは人や思想を妄信するありさま)を揶揄している様が心地良い一曲だった。半分笑いつつ好きになったこの曲。エアチェックしたカセットを一時はヘヴィーローテーションでかけていた。今聴いても大槻さんのこの唄は素晴らしい。
本日11:00、東京の梅雨明け宣言アリ。そんな夏の日の始まりにも景気付けにも良い曲かもしれない。。。
■筋肉少女帯「僕の宗教へようこそ (Welcome to my religion)」1990■

わたしは“ゆりこ教“でもNo.2の応援団でもない。そもそも彼らには投票していない。
いくら狂っても、そんなおかしな宗教は信じないし所属しない。