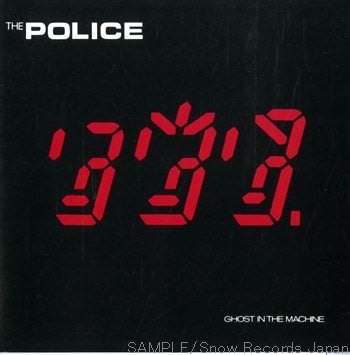「デュラン・デュラン」は、1枚目のアルバムが出たのが、自分が中学3年生の頃、1981年だった。
当時「ニュー・ロマンティクス」というブームの中の1つの重要なバンドだった。
***
「ニュー・ロマンティクス」の立役者として、ウラで動いていたのは、ウルトラヴォックス(第2期)、及び、その中心だったミッジ・ユーロ。
ミッジ・ユーロは、「ニュー・ロマンティクス」の核となったVisageの音をほとんど創っていた。
その元は?というと、YMOである。
【ヴィサージ 「ヴィサージ」】・・・音楽史には不可欠なアルバム
Visageのヴォーカル、というかフロント・マンは、「スティーヴ・ストレンジ」という男で、彼はロンドンで「カムデン・パレス」(革命舞台!)というディスコを経営しており、自分の好きなロキシー・ミュージックやデヴィッド・ボウイ、YMO、YMOファミリーの音楽、それに最新の音楽を流していた。
彼は「ロンドンで初めてYMOを流したのは自分だ」と自慢していたという逸話もあり、そこからも「ニュー・ロマンティクス」がYMOの影響下で生まれた若い新しい世代のムーブメントだったのがわかる。
***
「ニュー・ロマンティクス」は、自分の当時の認識としては、第2期ウルトラヴォックス、その配下にあったVisage、そして、デュラン・デュラン、スパンダー・バレエが中心。
その他、ザイン・グリフ(彼は幸宏の1982年の「WHAT, ME WORRY?」に参加している)、ランドスケイプといったミュージシャンが居た。
現代では、「ニュー・ロマンティクス」はお化粧すれば「ニューロマ」の影響とか言われてるが(ほとんどがガラクタバンドだが)、そんな低次元の問題ではなく、80年代の日本の音楽の革命がYMOだったと同時に、ロンドンでの音楽の革命が「ニュー・ロマンティクス」であったのだ。
特にVisageの音楽(ミッジ・ユーロ+スティーヴ・ストレンジ)は、その後のハウス~アンビエントへの流れに、実は大きな影響力があった、と自分は思っている。(クラフトワークもそうだが)
***
日本(YMO)発でイギリスへの影響という流れだった。
実際、ミッジ・ユーロ/VisageがYMOの影響で音楽を創ったように、デュラン・デュランのメンバーも「サディスティック・ミカ・バンド」がイギリス公演を行った際のTV番組の画面に向かってポラロイド写真を撮ったり(大事に飾ってあったという)、YMOのアルバムを好んで聴いていた。
ザイン・グリフも、デヴィッド・ボウイの影響が強いが、YMOが好きで、結果、幸宏のアルバムに参加することになる。
一方、かたくなにオモテに出さないのが、スパンダー・バレエで、1980年YMOはイギリス公演を行ったが、幸宏・教授曰くは「影響を受けながら、会ってもそっけない態度で、気に食わなかった」そうである。
(ちなみに、このYMOのイギリス公演には多くの著名なミュージシャンが聴きに来て、楽屋に訪れ、その後の交流に繋がっていくわけであるが、ジャパンのデヴィッド・シルヴィアンもその1人である。)
***
「デュラン・デュラン」は、YMOの影響も受けながらも、非常にポップでメロディアスで贅沢な音楽を展開し、自分もずっと1枚目以降追いかけてきた。
そこで、MTV(ヴィデオ・クリップ)が、アメリカ中心に一気に広まり、そういう影響で、1982年「デュラン・デュラン」はイギリスを越えてアメリカのトップ・チャートに入り込むことになる。
当時は、「ブリティッシュ・インベンション」と呼ばれていた。
アメリカの音楽が、1970年後半から息切れし出して、まったく面白見を欠き、新しい音楽を生み出せていなかったことが主要因だと思われる。
ここ以降、イギリスの新しい音楽は、どんどんとアメリカに流入していくことになる。
イギリスでヒットしたものは、貿易のように海を渡って、数ヵ月後にアメリカでヒットするという流れが生まれる。
***
そのような流れの中、「デュラン・デュラン」という「ブランド」力が音楽市場(アメリカ+日本+イギリス)で確立し、この1985年には、その「ブランド」力を背景に、5人のメンバーは、それぞれ、「パワー・ステーション」と「アーケイディア」という2つのユニットでの実験活動に入っていく。
「パワー・ステーション」の方に、ジョン・テイラー、アンディー・テイラーが参加し、アーケイディアの方に、サイモン・ルボン、ニック・ローズ、ロジャー・テイラーが参加という形に2分される。
これも、「デュラン・デュラン」というブランドあっての、自由な音楽活動だった。
しかし、一方では、「デュラン・デュラン」があまりに売れすぎ、5人のルックスの良さもあり、その「ブランド」が(日本では特に)アイドル・バンド的な安直な見方をされる事にも繋がっていたため、そういう見方への「反逆」も、このそれぞれのユニットには含まれたような気が、自分はしていた。
往々にして、ポップスの「王道」にいつの間にか行ってしまったがゆえの不幸というのを、ポップ・バンドが背負ってしまう、という流れがある。
「デュラン・デュラン」の不幸もそこにあった気もする。
イギリスの「革命児」だった彼らも、いつのまにか、それが「王道」になってしまった世界を壊したくなり、それぞれの実験活動に入っていく要因になったように思えた。
***
「アーケイディア」は、「情熱の赤い薔薇(So Red the Rose)」というアルバムを1985年11月にリリースする。
その1曲目に当たる「エレクション・デイ」がシングル・カットされ、ヒットすることになる。
【アーケイディア 「情熱の赤い薔薇」】
「エレクション・デイ」は、2009年の今になって聴いても、非常にポップ、かつ、カッコイイ。
ラジオのようなノイズ混じりの音から始まるイントロがたまらなく良い。
このアルバムでは、ギターに土屋昌巳を起用し、彼の独自の音色・アクセントが隠し味となっている。
また、「エレクション・デイ」でも聴けるサックスは、ロキシー・ミュージックのアンディ・マッケイ、曲の途中でのクールな語りはグレイス・ジョーンズと、豪勢なバック・アップを得ている。
***
土屋昌巳さんの話では、このアルバム制作時に、3人はほとんど居ない状態で、ギターを弾いていたそうで、かなり周囲のエンジニア、それにプロデューサーの力で創られた部分も大きいとは思う。
ちなみに、プロデューサーは、トンプソン・ツインズでも力を発揮したアレックス・サドキンである。
「エレクション・デイ」≒「デュラン・デュランの音楽」という差異は、エロティックな妖しさであろうか。
アルバム全体にしてしまうと、緩慢さが目だってしまうのは、ヴォーカルがサイモン・ルボンである事に因るところが大きい。
それゆえ、デュラン・デュランと変わらない部分が大きいのは否めないが、「エレクション・デイ」は、自分のよく聴く80年代の音楽としては欠かすことの出来ない曲である。
6曲目に「Rose Arcana」という、夜の鳥が飛び立つ音が入った51秒だけのインストゥルメンタルの曲があったり、8曲目の「El Diablo」では、ヴァイオリンやオカリナ、土屋昌巳のスパニッシュ風のギター、テープループのような音が入ったりとさまざまな要素を取り込んでいる。