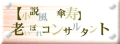■【小説風老いぼれコンサルタントの日記】 3月23日 3章 ◇経営コンサルタントへの道 ◇いじめっ子 ◇ウォーキングと並行した動作で副次効果を狙う 17 タオル体操 ~ 肩こり防止・解消
平素は、私どものブログをご愛読くださりありがとうございます。
この度、下記のように新カテゴリー「【小説風 傘寿】 老いぼれコンサルタントの日記」を連載しています。
日記ですので、原則的には毎日更新、毎日複数本発信すべきなのでしょうが、表題のように「老いぼれ」ですので、気が向いたときに書くことをご容赦ください。

紀貫之の『土佐日記』の冒頭を模して、「をとこもすなる日記といふものを をきなもしてみんとてするなり」と、日々、日暮パソコンにむかひて、つれづれにおもふところを記るさん。
【 注 】
日記の発信は、1日遅れ、すなわち内容は前日のことです。
■【小説風 傘寿の日記】
私自身の前日の出来事を小説日記風に記述しています。
3月23日
読売新聞トップに、明治以来続いてきた日本の商習慣に欠かせない決済手段としての手形と小切手が、2026年度末で全て廃止される見通しと大きな活字が躍っていました。
2022年に紙の交換所が廃止、代替策として電子交換所が設けられましたが、それが廃止されます。
中小企業いじめのようなこの決済手段が廃止される背景には、中小企業対策と言うよりは、事務手続きが煩雑なための銀行側のご都合主義です。
手形の代わりに、ネットバンキングや、印紙税なしで債権を取り引きできる「全銀電子債権ネットワーク」への移行となるそうです。
それ以降も従来の手形や小切手利用は可能ですが、金融機関が現金化をしてくれるかどうかの問題が残りますので、事実上は廃止ということですね。
*
早朝ウォーキングの効果を持続または改善するために、今朝のウォーキングで、自分でどの様にやっているのか反復してみました。
◆3章 ウォーキングと並行した動作で副次効果を狙う
ウォーキングの効果は知られていますが、その効果をさらに高めたり、付帯的な効果を上げたりするという「ながらウォーキング」をしています。これは、ボケ防止になると痴呆を研究している人達が研究発表をしていますので、それを励行するようにしています。
「ながらウォーキング」も、ウォーキング・ミックス(いろいろな歩行法の組み合わせ)と同様に、いくつかの方法があります。それらを適宜組み合わせてウォーキングすると効果的ですので、その方法を紹介いたします。
【 注 】
ここで紹介する情報は、自分で思考したり、入手したりした情報をもとに、ご紹介します。
それが皆様にも良い方法であるとは限りませんので、皆様ご自身のご判断で参考にしてくださるようお願いします。
17 タオル体操 ~ 肩こり防止・解消
もう一つのタオル体操は、肩こり防止とその解消のために行います。
タオルの両端を持つのは、ストレートネック対策と同様です。片手を頭の後ろに、他方の手をお尻の後ろに持ってゆきます。
頭の後ろ側にある手を上方に伸ばします。他方の手は、それに反発するように下方に引きます。上方の手をできるだけ高く引き上げます。ここで一旦力を緩め、次に、下方の手をしたにできるだけ引き下げます。他方の手は、それに抵抗するように上方に引き上げます。
これを数回繰り返しますと、肩こり防止や解消に効果があります。
タオル体操の三番目は、体側伸ばしです。タオルの箸を握るのは、上述と同じで、身体の前で握ります。
それを上方に上げながら、左右の手を開くようにし、腕を伸ばします。最上方に手が上がりましたら、身体を左右に曲げます。
その時に、たとえば左手方向に曲げて、右体側を伸ばすときには、左手を身体の横方向に引きます。右手は、それに反発する方向に力を入れます。右体側が伸びるようにし、次のその逆を行い、これを繰り返します。
これで体側の固まった筋肉をほぐします。方頃解消にも繋がります。
これが終わったら、タオルの端を持って左右に引っ張りながら、手を水平の高さに持ってゆきます。
水平にした状態で、左に身体をゆっくりと拈ります。あまり無理をせず、しかしできる限り、左手が左後方に行くようにします。次にそれを右方向に拈ります。これを繰り返します。
タオル体操は、タオルがあるだけで効果が高まりますが、無理をしますと痛めたりしますので、自分の体調に合った力加減をとることが重要です。

■【今日のおすすめ】
【経営コンサルタントへの道】7 経営コンサルタントとしての成功のポイント 4 モットーを持つ
コンサルタント・士業として独立起業することは勇気が要ることです。
どの様な資質を備えている人が、成功する確率が高いのでしょうか、経営コンサルタント歴半世紀の経験からお話しています。

■【今日は何の日】
当ブログは、既述の通り首題月日の日記で、1日遅れで発信されています。
この欄には、発信日の【今日は何の日】と【きょうの人】などをご紹介します。
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/7c95cf6be2a48538c0855431edba1930

■【知り得情報】
政府や自治体も、経営環境に応じて中小企業対策をしています。その情報が中小企業に伝わっていないことが多いです。その弊害除去に、重複することもありますが、お届けしています。
*
◇再掲《公募》ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(19次締切)について、令和7年4月25日(金)まで公募をしています。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2025/250217kobo.html
出典:e-中小企業庁ネットマガジン

■【経営コンサルタントの独り言】
その日の出来事や自分がしたことをもとに、随筆風に記述してゆきます。経営コンサルティング経験からの見解は、上から目線的に見えるかも知れませんが、反面教師として読んでくださると幸いです。
◆ 「いじめられっ子」ではなく「いじめ被害者」 323
たまたまいじめをテーマにしたテレビ番組を観る機会がありました。
40代、50代になっても、子供の頃のいじめがいまだに尾を引いている人がいらっしゃるようです。
その人達の生活というのは、われわれの想像を絶するところがあると思います。
そのような人達に手を貸している先生が登壇していました。
そのような人は、真面目な人が多く、そのために自責の念が強すぎるようです。
自分が何かを言われるのは、自分が悪いからだ、と自分を責めてしまうようです。
その先生からの「あなたは被害者であって、あなたは悪くない」というひと言で、ある女性は立ち直ることができるようになったと述懐していました。
その先生は、「いじめられっ子」ではなく、「いじめ被害者」と言うべきだともおっしゃっていました。
私達は、相手を傷つけようと思っているわけではないのに、相手を傷つけてしまっていて、自分は気がつかないということがあるように思えます。
言ってしまってから、言い過ぎたと気がつくこともあります。
いじめ加害者がしていることのインパクトは、いじめ被害者にとっては、いじめ加害者側が想像するより遙かに大きいです。
いじめ被害者に対して、私自身、もっともっと理解を深め、配慮をすべきだという反省をする機会が多くなりました。
*
◆ 煩悩に満ちて彼岸を明けました 324
中日を挟んで7日間がお彼岸です。
今年は、20日がお中日でしたので、23日が明けになります。
閏年などもあって、年によって日付が若干変動しますので、その年の彼岸の入りはいつなのかを確認する必要があります。
改めて「彼岸」という言葉を考えてみました。
煩悩や迷いに満ちた現世を「こちら側の岸」という意味で「此岸」(しがん)というのだそうです。
それに対して、煩悩を脱した悟りある人の地は、「向う側の岸」という意味の「彼岸」と呼ばれます。
「七十にして、心の欲するところに従がって矩(のり)を踰(こ)えず」
まだまだ煩悩に満ちていますので、心の欲するままですと、「矩」を超えるばかりです。
あな恥ずかしや!

■【老いぼれコンサルタントのブログ】
ブログで、このようなことをつぶやきました。タイトルだけのご案内です。詳細はリンク先にありますので、ご笑覧くださると嬉しいです。
明細リストからだけではなく、下記の総合URLからもご覧いただけます。
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17
>> もっと見る

■【小説風 傘寿】老いぼれコンサルタントの日記 バックナンバー
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/a8e7a72e1eada198f474d86d7aaf43db
© copyrighit N. Imai All rights reserved