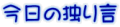先生らしく、実体験や博識から、謙虚に、しかも大胆に、辛口も含めてお感じになっていることを皆様にお届けしています。その号外編として、下記をお届けします。
「欧州各国では、倒産手続とは別に、倒産状態前において裁判所の認可の下で債権者の多数決により債務整理を行う制度が存在するが、日本には存在しない。」という問題があり、それを補強する法案である「早期事業再生法」が閣議決定され今国会へ提出される予定らしいです。
https://www.meti.go.jp/press/2024/03/20250304003/202503004003.html?fbclid=IwY2xjawJNkohleHRuA2FlbQIxMAABHcvigzbNqPu63oHedR0z35XOJqPC1YQ2DyVtELB3Mld-ZenQF7RJyxbiwg_aem_6Sz0y_OYQiH6HLFRh6us2A
多分、大きな効果は無いと個人的には考えます。
手続をどう変えても再生するには?が問題の核心であって、倒産する前の資金余裕、人的余裕、社長の心を変えられるなど余裕のある時にやるべきことが多く、手続きは逆に債務処理を早くするだけでは?と思います。
傾いてどうしようもなくなる少し前に、「ウチの会社は今後5年~7年、通常通り、【あたり前に】、やっていけるのかどうか」という企業の健康診断を受けておけば、まだどうしようかと、動くことができます。
企業健康診断を受けていなければ、傾く少し前かどうかがわかりません。V字回復ストーリーがこの世の全てではありません。既に遅かったというのが現実です。
「あたり前」に毎日会社経営してるからといって、来年も再来年も、「あたり前」に経営できるとは限りません。
「あたり前」経営は、企業を今後も継続させる大きな源になるものです。足腰の強い、イノベーションを起こす力をも生み出す、基礎力を作り上げるのが「あたり前」経営というものです。だから「あたり前」は創るものです。
・・・こう説明しないと理解されるかもしれません。
・・・何もかも全ての「あたり前」のことが常に将来も出来て継続する企業って、存在しません。でもあたり前を無視したり過小評価したりでやっていないから、どこかで危機を迎えるのではないでしょうか。「成長しなくとも絶対に潰れない」だけでなく改善の中から新しい成長を見つけて再度成長軌道に乗せられるのも、優良企業の「あたり前」です。
でも、「あたり前」経営には「方程式」はありません。
あたり前の実践の中から、自社の方程式を見出す、これだと思います。両利きの経営・二項動態経営・〇〇戦略経営・DX経営・・・、やり方を示したところで、実際の経営は自らオーダーメイドするもので、それもあたり前のことです。コンサルに答えを求めることもおかしいです。答えは自社の中にあって、コンサルや外部の頭の中には真実の答えはありません。
人間味溢れるあたたかい心と現場主義コンサルこそ、日本経営士協会のスピリッツ(精神)じゃなかろうか。
あたり前経営の普及活動をどこかの時点でやらないと・・・。
その前にしっかり学び、狼狽えることがないよう自分も基礎基本を身につけないといけないです。日本経営士協会の長い歴史を特徴とか強みと言うだけでは、長い歴史はあたり前じゃん!と我々が歴史的価値を過小評価する様では良質化循環に繋がらないと思います。
長い歴史が・・・といっても、So What ?となります。
温故知新も大事です。協会のルネサンスが大事かと。
まったく偉そうな口を長々と、本当にすみません。
なんでいつも熱っぽくなるのかわかりません。
申し訳ございませんでした。
*